「静かな退職(Quiet Quitting)」という言葉を耳にしたことはありますか?
米国発でSNSやメディアで話題になり、Z世代を中心に20代・30代の間でも注目されているこの働き方は、
「最低限の業務だけをこなし、プライベートを優先する生き方」を指します。
株式会社マイナビが⾏った『正社員のワークライフ·インテグレーション調査2024年版(2023年実績)』によると、20〜50代の正社員48.2%が「静かな退職をしている」と回答しており、日本でも広がっています。
がんばりすぎない働き方として魅力的に映るかもしれませんが、果たしてそれは本当にあなたに合った選択肢なのでしょうか?
この記事では、「静かな退職」とは何か、その背景やメリット・デメリットを整理し、
会社員歴15年以上の筆者の視点からおすすめできる人・おすすめできない人の違いをお伝えします。
あなたが、自分らしい働き方を見つけるヒントとして、ぜひ参考にしてください。
転職活動をはじめる決心がついている方はこちら
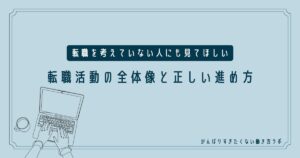
“静かな退職”は多くの会社員におすすめしません

「静かな退職」は一見ストレスの少ない理想的な働き方のように見えますが、がんばりすぎない働き方ラボとしては、基本的にはおすすめできません。
なぜなら、静かな退職は短期的には気楽でも、長期的にはキャリアの停滞や市場価値の低下を招くリスクが高いからです。会社員の働き方のメリットである”安定”という観点において、これは大きなマイナスです。
もちろん、ライフステージや一部の状況によっては適した選択肢になるケースもありますが、「なんとなく気持ちが疲れたから」「仕事がつまらないから」という理由だけで選ぶのは要注意です。
会社員という働き方とモチベーションについては下記の記事でも解説しています。
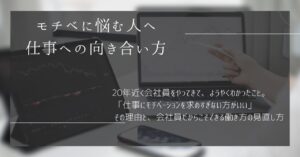
安定を損ない、継続のハードルも高い
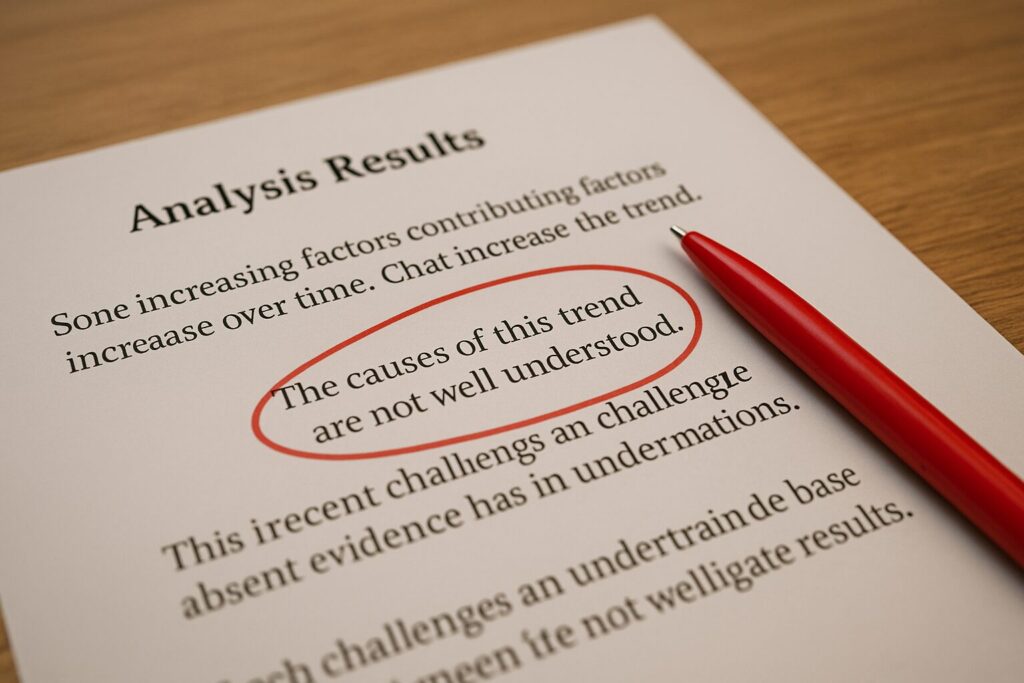
理由1:スキルも実績も積めず、市場価値が下がるリスクがある
静かな退職では、自分から新しい仕事に手を挙げることはなく、最低限の業務だけをこなすスタイルになります。
その結果、新しいスキルや経験を得るチャンスが少なくなり、成長機会を自ら手放すことになりかねません。
近年は、ITやAIなどの技術革新によって仕事のレベルがどんどん高度化しています。
転職が当たり前になり、キャリアの「粒度」も細かくなっている今の時代、職務経歴書に書く実績やわかりやすいアピールポイントの乏しい人材は、選ばれにくくなってきています。
会社の存続や現在の条件は絶対的なものではありません。
もしも今の職場を離れざるを得なくなった時、「自分はどこでも通用するのか」と考えると、静かな退職は決して安定とは言えないことが見えてくるでしょう。
理由2:収入や人間関係、モチベーションの面で継続が難しい
静かな退職では昇進や評価を目指さないため、収入アップはあまり期待できません。
むしろ、年齢や物価の上昇、ライフイベント(結婚・出産・住宅購入など)に対して、将来的に不安が残ります。
また、周囲から「やる気がない人」「貢献しない人」と見なされることで、職場の人間関係が悪化する可能性もあります。
たとえば、自分より若い後輩がどんどん昇進したり、自分の上司になったりする状況に対して、割り切れる人は多くないはずです。
さらに、「やりがい」や「達成感」を感じにくくなるため、モチベーションを保ち続けるのが一段と困難です。
結果として、「淡々と業務をこなす毎日が、むしろ精神的にしんどい…」と感じてしまうケースも珍しくありません。
静かな退職は、これらを耐えうる人のみに許された選択肢なのです。
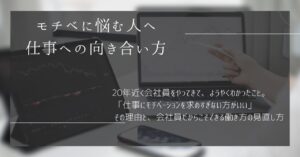


“静かな退職”、誰もが一度は思い描く…けど

現実には「静かな退職」を選んで苦しくなる人が多い
SNSでは「静かな退職」でゆるく働いて人生を楽しむ姿がもてはやされがちですが、実際には「うまくいかない」「思っていたよりしんどい」と感じている人も少なくありません。
たとえば、わたしの同僚には、
・上司からのプレッシャーに疲れ、プロジェクトのリーダーをボイコット、静かな退職に近い働き方を選んだものの
・「周囲の目がつらい」「評価が下がって将来が不安」と悩んで、結局転職を決意した
という人がいました。
わたしもこのブログが「がんばりすぎたくない働き方ラボ」とあるように、頑張ることを賛美する価値観ではありません。若い時分に「評価や昇進なんていいから、ほどほどに働こう」と考えた時期もありました。
ただ、結論としてその選択は自分の未来から前借りしているだけだなと判断し、「未来でがんばりすぎなくてもいいように、今はがんばりすぎない程度にがんばろう」というスタンスになりました。
実は、静かな退職は「耐えられる人」が少数派
「静かに働く」のは聞こえがよくても、実際にはかなり難しいスタイルです。
というのも、仕事に対して成長欲求も達成感も見出せず、収入も増えず、職場での評価も高まらない中で、
精神的にも経済的にも自立し続けるには、強い意思と環境の安定が求められるからです。
たとえば、十分な貯金があって「別に給料が上がらなくてもいい」というシニア層なら、
プライベートを重視した働き方として「静かな退職」は選択肢になるかもしれません。
でも、20代〜40代の現役世代がこの働き方を長く続けるには、あまりにも多くのリスクが伴います。
めのめMEMO
わたしの先輩の一人が、まさにこの「静かな退職」を地で行く人でした。
「言われたことだけする」「残業はしない」「出世には興味がない」「結婚もしない」
上司に何度叱咤されても、後輩に職位が抜かれても、自分が最年長のプロジェクトで一番下っ端でも、怒りも悲しみもせず、ただ淡々と最低限の仕事だけをし続ける。
静かな退職を選択し、実現するにはこのぐらいの精神力や耐えうる価値観であることが必要です。
まとめ:”静かな退職”ではなく自分だけの働き方を探そう

「静かな退職」は、働きすぎの反動や、ワークライフバランス重視の価値観の変化から注目されています。
しかしその実態は、キャリアの停滞・収入の頭打ち・職場での孤立といったリスクを伴う、“消耗しない代わりに積み上がらない”働き方でもあります。
もちろん、「家庭や健康を最優先したい」「もう十分働いた」という方にとっては、選択肢の一つになるかもしれません。
ですが、もしあなたがまだキャリアの途中にいて、「今の働き方がしっくりこない」「もっと自分らしく働きたい」と感じているのなら、静かに離れるのではなく、自分に合った働き方を見直すことをおすすめします。
🌱 次にとるべき一歩
✔ 自分が「何に疲れているのか」「本当はどう働きたいのか」を書き出してみる
✔ 今の職場で変えられそうなこと、変えられなそうなことを整理する
✔ 必要なら転職や副業も視野に、自分らしいキャリアを検討してみる
がんばりすぎなくていい。けれど、諦めるように働くのはもったいない。
あなたが納得できる働き方に、辿りつけるようがんばりすぎたくない働き方ラボは引き続き情報発信をしていきます。
転職活動をはじめる決心がついている方はこちら
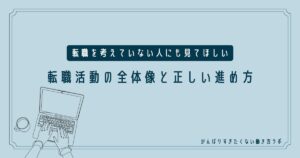
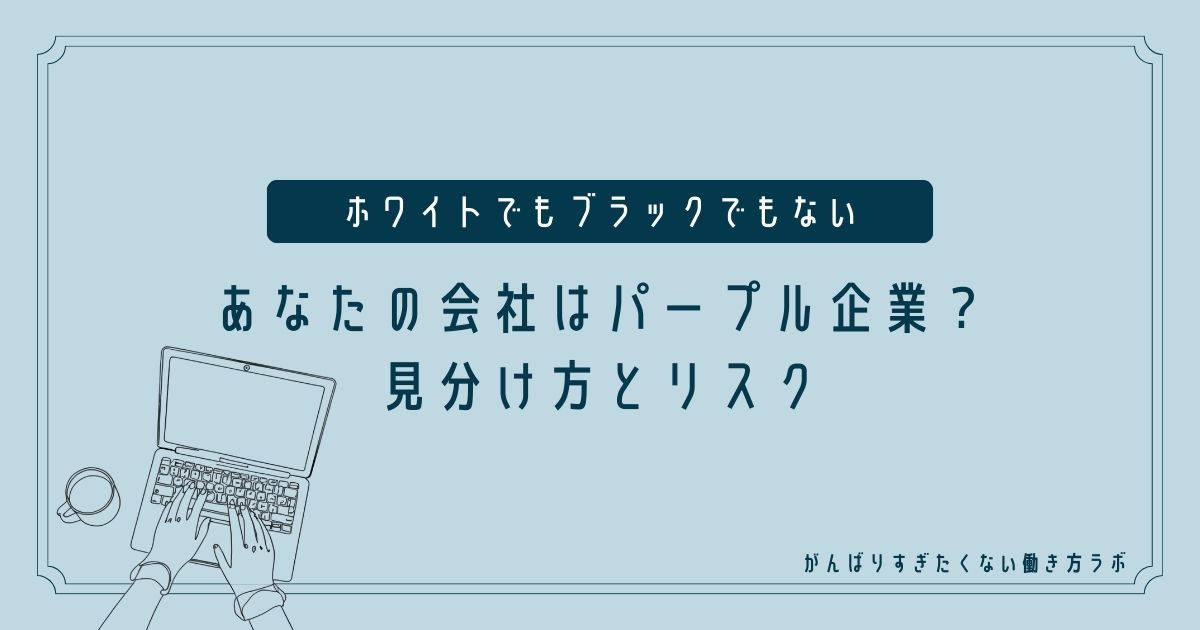
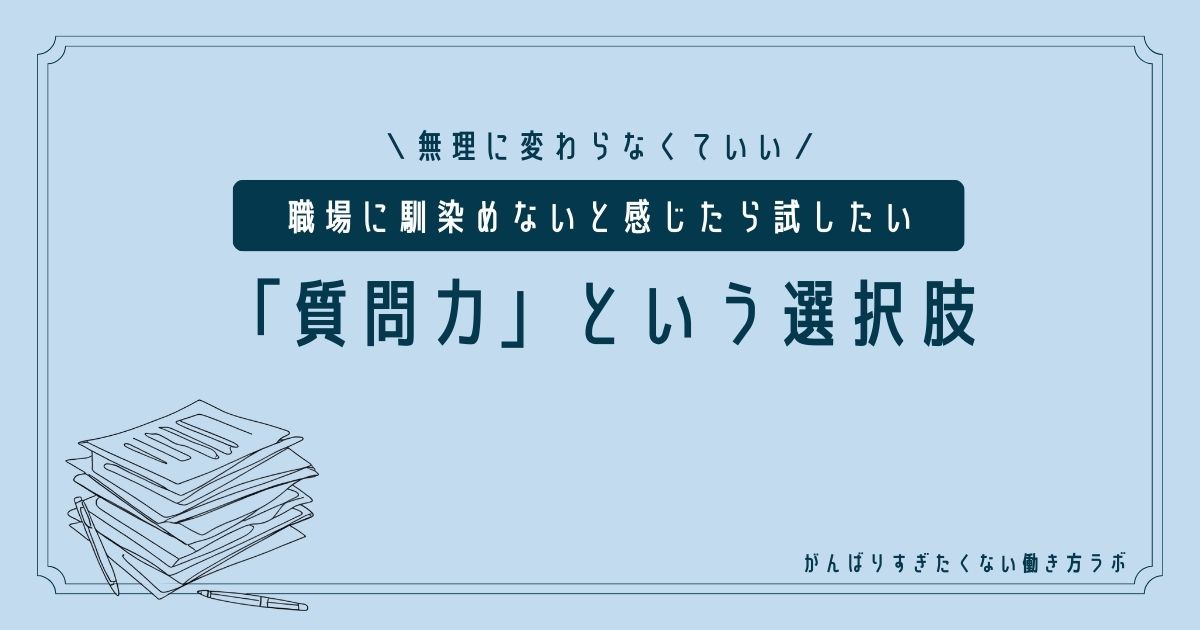
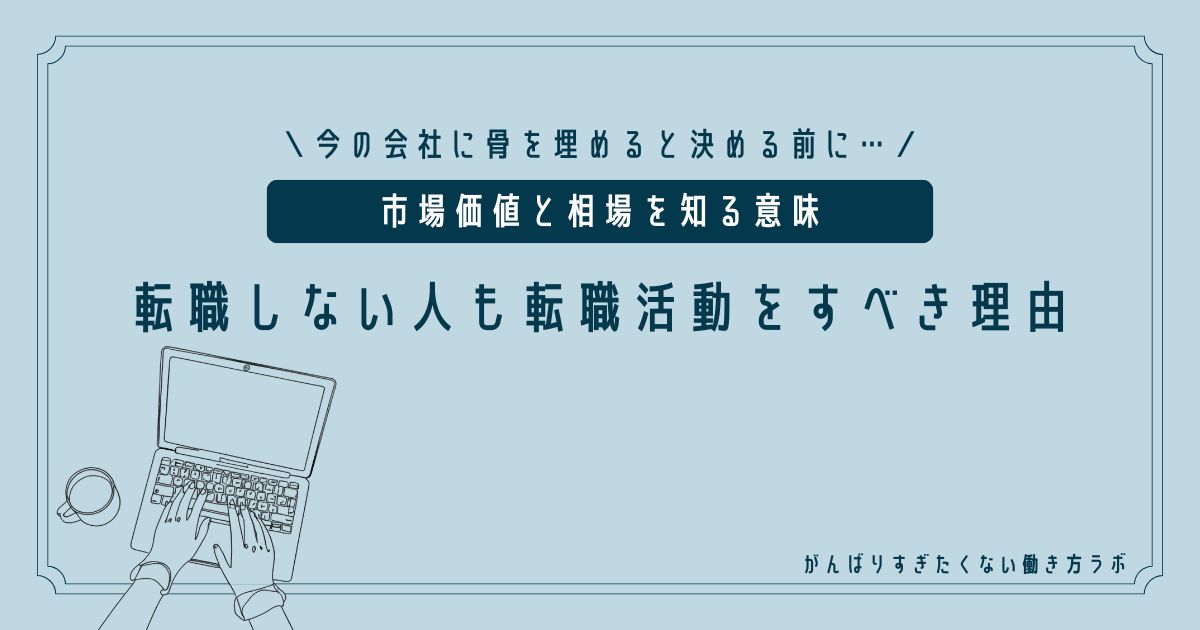
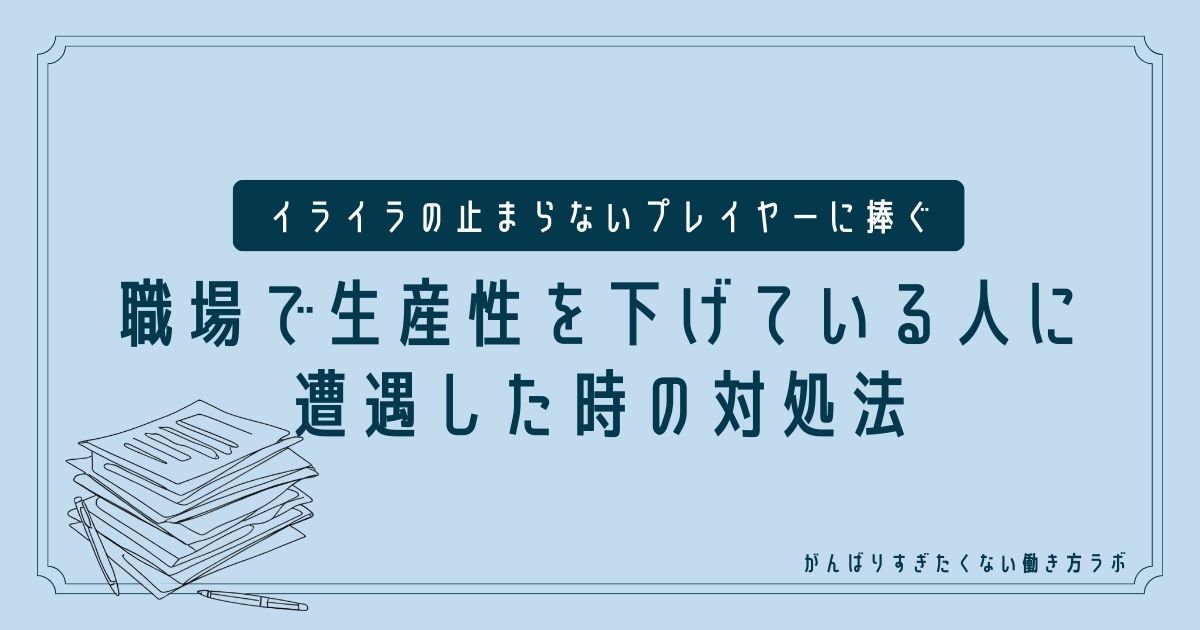
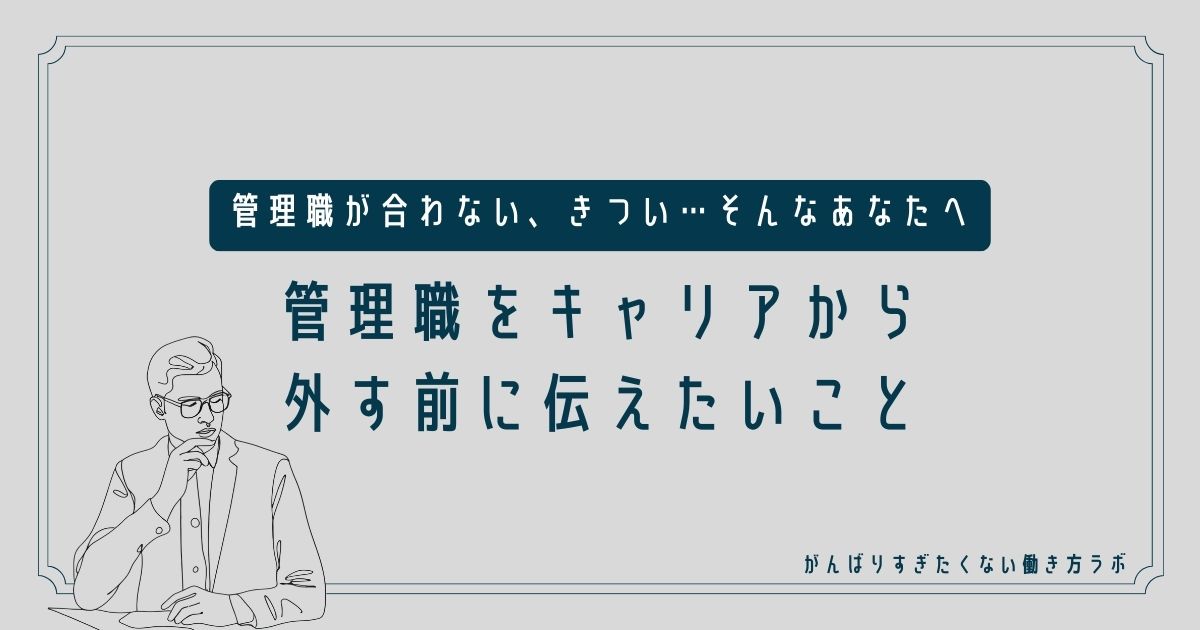
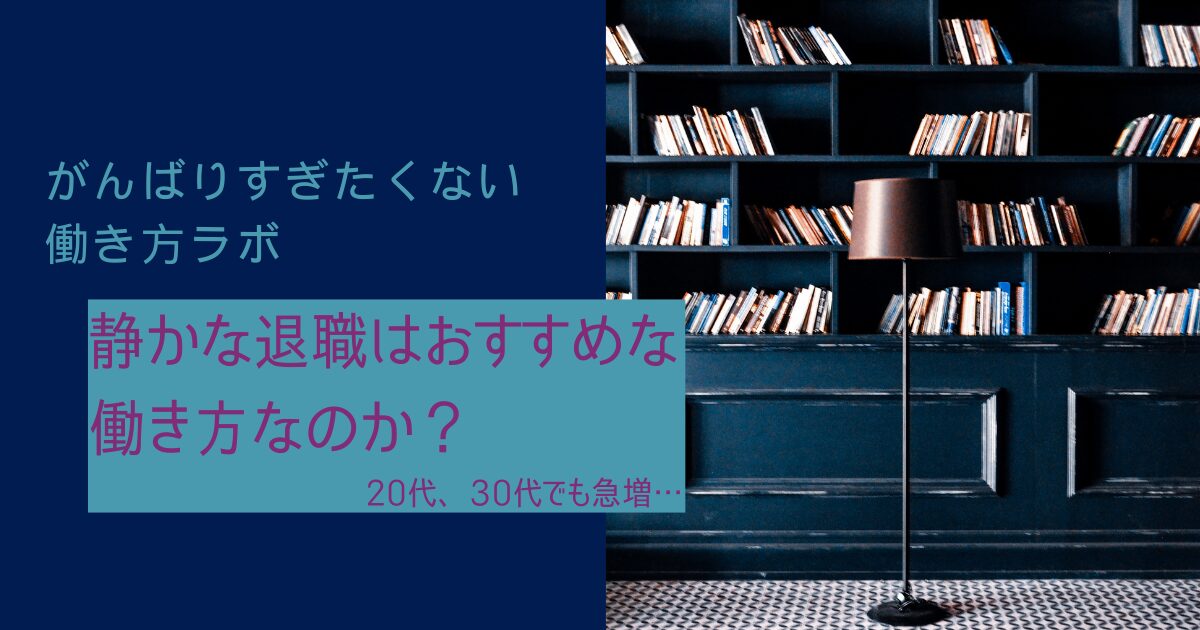
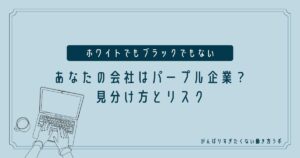
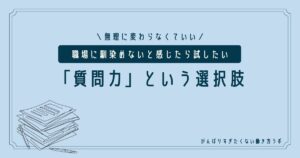
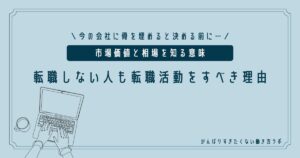
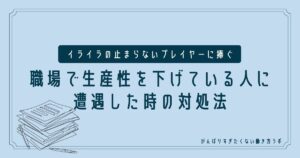
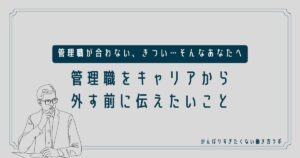
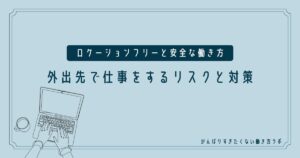
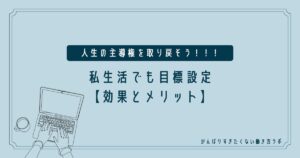
コメント