「心理的安全性が大切だ」と、最近よく耳にしませんか?
1on1やチームマネジメント、会議運営など、多くの場面で「心理的安全性を高めよう」という言葉が使われるようになってきました。しかし、いざ自分が実践しようとすると――
- 「そもそも、心理的安全性ってどういう意味?」
- 「気を遣いすぎて“ぬるま湯”にならない?」
- 「チームの雰囲気って、リーダー次第なの?」
そんなふうに、疑問や違和感を覚える方も多いのではないでしょうか。
この記事では、会社員歴15年以上、現役で10名の部下を持つ筆者が、
心理的安全性の定義や重要性をわかりやすく解説したうえで、高いチームと低いチームの違い、チェックリスト、実践のヒントを紹介します。
特に、中間管理職やリーダーの方にとって、部下との1on1やチームの雰囲気づくりに直結する内容です。
「どうすれば、チームが活き活きと意見を出せるようになるか」を考えるヒントとして、ぜひご活用ください。
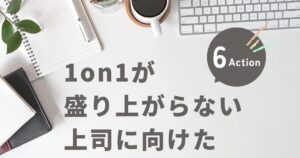
心理的安全性とは「本音で話せる関係性」
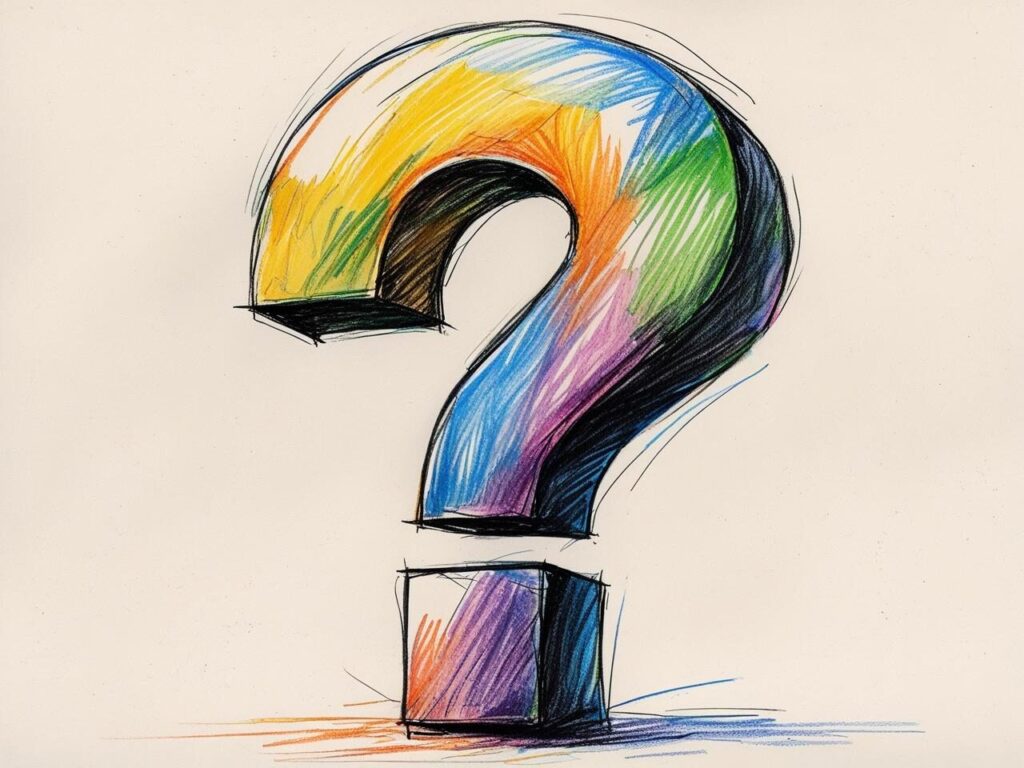
心理的安全性(Psychological Safety)とは、「自分の意見や気持ちを率直に表現しても、非難されたり馬鹿にされたりしない」と信じられる状態のことを指します。
この言葉を広めたのは、ハーバード・ビジネス・スクールのエイミー・エドモンドソン教授です。彼女の研究によれば、心理的安全性があるチームでは、以下のようなことが可能になります
- わからないことを「わからない」と言える
- ミスを素直に報告できる
- 意見が異なっていても、安心して発言できる
端的に言えば、本音で話せる場や相手との関係性といえます。
“人の性格”ではなく“チームの性質”

心理的安全性というと、個人の気持ちやメンタルの問題と思われがちですが、実際はチームの文化や関係性、もう少しラフに言えば雰囲気に関わるものです。
たとえば、ある人がAチームでは積極的に発言できるのに、Bチームでは黙ってしまう――これは、その人が変わったのではなく、「安全だ」と感じる環境が変わったということです。
心理的安全性は、個人のスキルよりも、その集団がどう機能しているかがカギなのです。
心理的安全性やその土台になる信頼関係については、以下の記事でも触れているので、心当たりのある方は合わせてご確認ください。
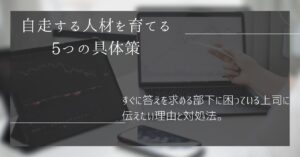
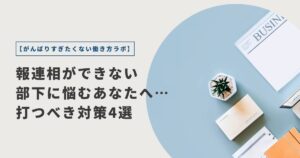
「ぬるま湯」との違いは?

心理的安全性という言葉に対して、「馴れ合いになりそう」「ただの優しさと違うの?」といった懸念の声もあります。
遠慮しあって何も言えない“ぬるま湯組織”と混同されることがありますが、本質は正反対のものです。
心理的安全性とは、異なる意見をぶつけ合える土壌であり、それは建設的にぶつかっても、関係が壊れない信頼感に支えらているものです。
なぜ心理的安全性が重要なのか
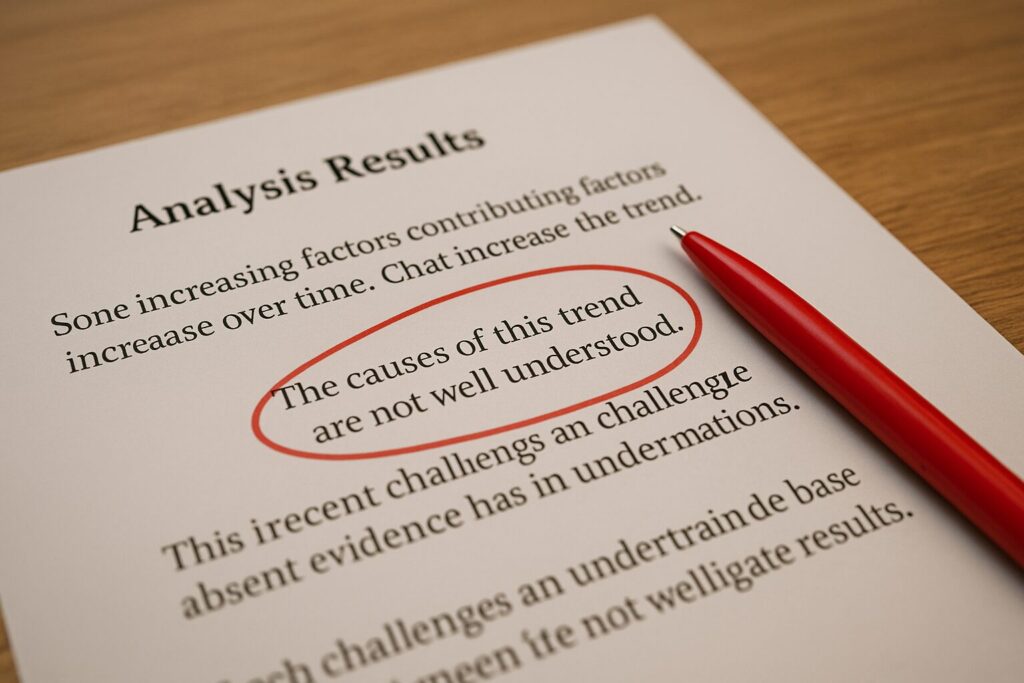
心理的安全性が注目されるようになった背景には、成果を出すチームとそうでないチームの決定的な違いに、この要素が深く関わっていることがわかってきたからです。
その代表的な例が、Googleが行った「プロジェクト・アリストテレス(Project Aristotle)」と呼ばれる大規模調査です。
Googleが導き出した“最強のチーム”の条件

このプロジェクトでは、「成果を出すチームにはどんな共通点があるのか?」を明らかにするための分析が行われ、その結論として、最終的に最も強い相関があったのが、心理的安全性(Psychological Safety)でした。
心理的安全性が高いチームでは、
- ミスを隠さず共有できる
- アイデアを否定される心配なく話せる
- 意見の違いを恐れずに議論ができる
こうした風土が、学習・挑戦・協働のサイクルを促進し、結果として高いパフォーマンスにつながっていたと結論づけたのです。
心理的安全性は組織に成果をもたらす

これらの調査結果から、一般的に心理的安全性が高い組織では、以下のようなプラス効果が報告されています。
- 生産性の向上(無駄な忖度や確認の減少)
- 主体性・創造性の発揮(挑戦や提案がしやすい)
- 離職率の低下(働きがい・関係性の質の向上)
- 学習文化の定着(失敗を糧にする姿勢)
つまり、単に“話しやすい雰囲気”というだけではなく、組織の成果や持続的成長に直結する要素なのです。
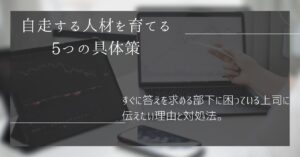
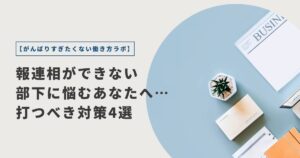
中間管理職・リーダーこそ鍵を握る

そしてこの心理的安全性、最大の影響を与えるのが、チームリーダーや中間管理職のふるまいです。
- 「それ、どういう意味?教えて」と聞けるか
- 「わからない」と言っても咎めないか
- 発言の少ないメンバーにも声をかけているか
集団のリーダーの日々のちょっとした言動や姿勢が、チーム全体の安全性を左右します。
チームメンバーの多様性が高まる現代において、「意見の違い」を歓迎しつつ、迎合するだけでなく建設的に扱えるリーダーシップがより重要になってきているのです。
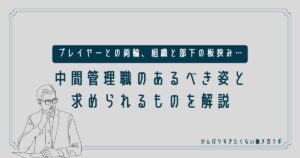
心理的安全性が高い組織と低い組織の差

心理的安全性が高いチームと低いチームでは、日々の会話・行動・空気感に明確な違いが表れます。
以下に、その違いを比較しながら整理してみましょう。
| 心理的安全性が高いチームの特徴 | 心理的安全性が低いチームの特徴 |
|---|---|
| 自由に意見が言える ミスや課題を共有できる 役割に関係なく発言できる 自由に意見が言える 挑戦を応援する空気がある | 発言者が限定的 ミスを隠す傾向 上下関係が強すぎる 異なる意見を出しづらい 新しいことに消極的 |
心理的安全性が高いチームでは、「この場で話しても大丈夫」「自分の存在が受け入れられている」という安心感から生まれます。一方で心理的安全性が低いチームは、チームとしての創造性や成長は抑えられ、結果として成果にも影響が出やすくなります。
“ぬるま湯組織”との違いはここ
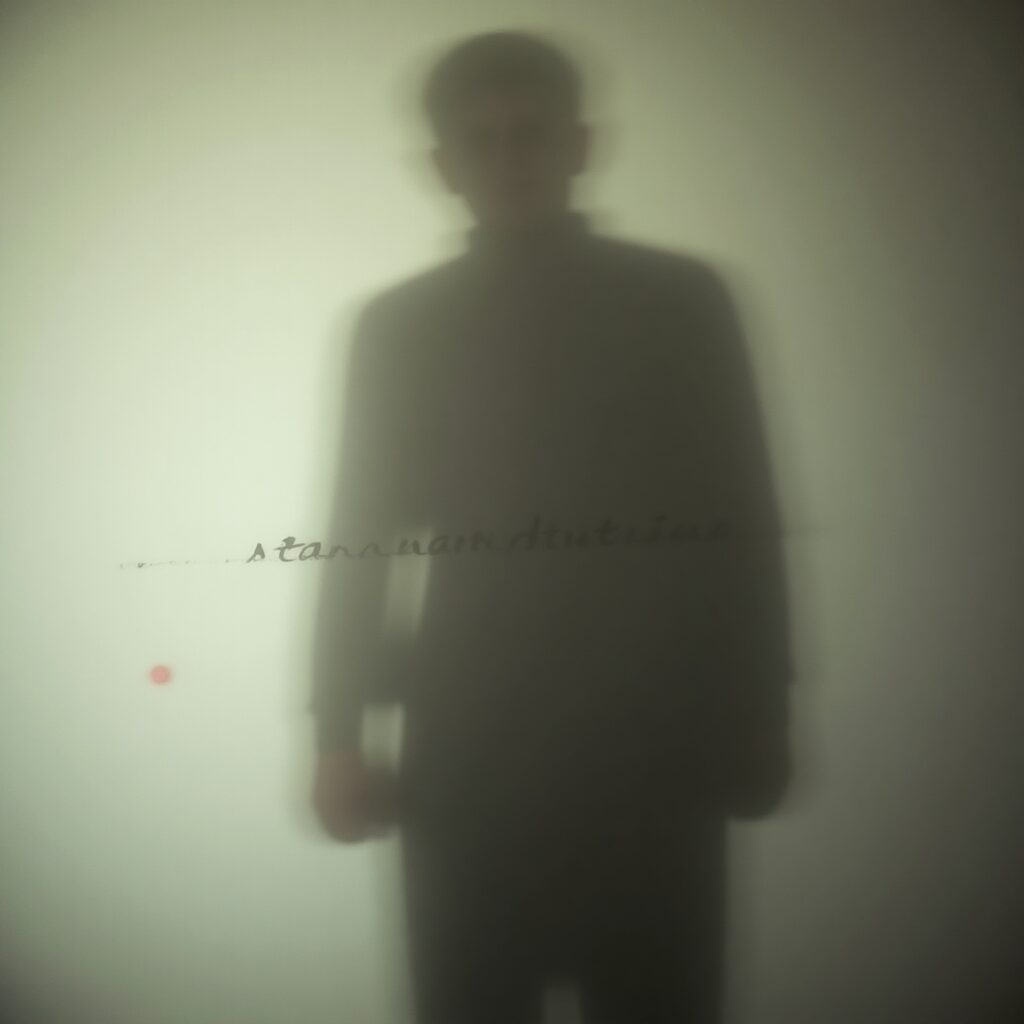
心理的安全性が低いチームの中には、一見すると「仲が良さそう」「和気あいあい」など、コミュニケーションが活発と見えるケースもあります。
しかし実際には、
- 本音は言わずに流す
- 衝突を避けて問題が放置される
- 空気を読みすぎて誰も決断しない
といった、いわゆる”ぬるま湯組織”になっていることも少なくありません。
本当の意味での心理的安全性とは、心地よさだけでなく、率直さと建設的な対話が両立している状態です。
心理的安全性を測る7つの質問
「心理的安全性が大事」と言われても、自分のチームがどうなのか、客観的に把握するのは難しいものです。
そこで役立つのが、心理的安全性を広がりに寄与したエイミー・エドモンドソン教授が提唱した「7つの質問」です。
質問リスト
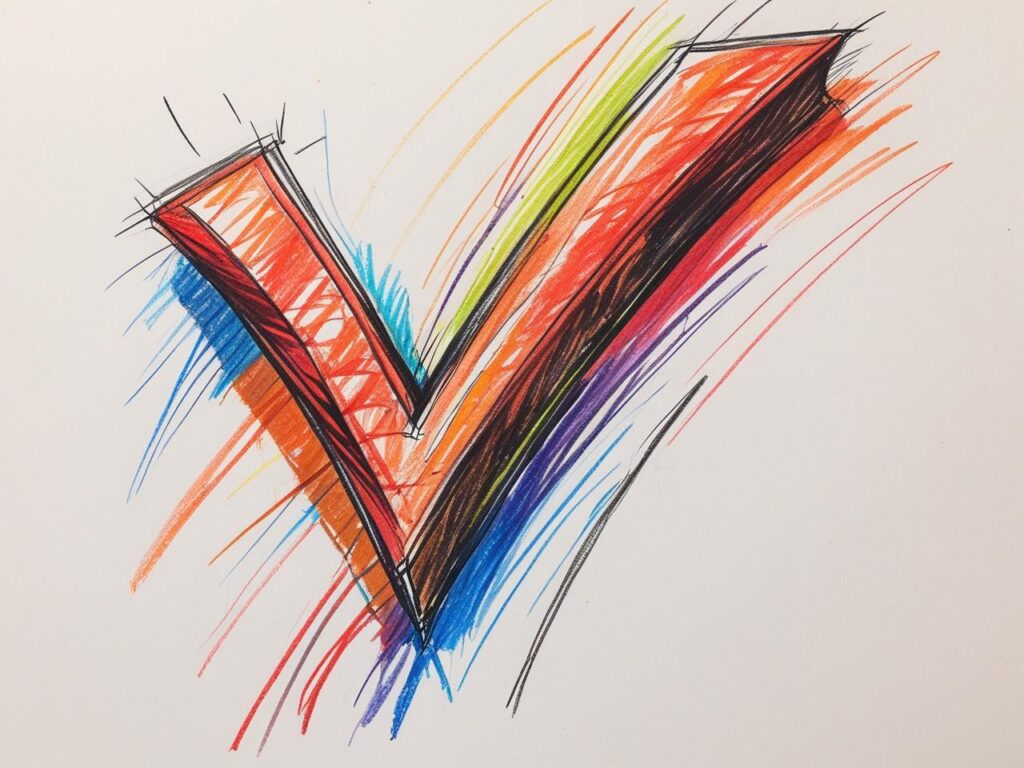
チームメンバーがどれだけ安心して率直に行動できる環境かを測るための、シンプルで実践的なチェックリストです。
以下の7つの質問に、「そう思う」「ややそう思う」「あまりそう思わない」「まったくそう思わない」の4段階で、チームメンバーに答えてもらうシンプルな内容です。
- このチームでは、ミスをしても非難されることはない。
- このチームのメンバーは、困ったときに助け合おうとする。
- このチームでは、異なる意見を持つことが歓迎される。
- チームの中で、誰でも問題や難題を提起できる。
- 他のメンバーに無知・無経験・弱みを見せても安全だと感じる。
- このチームでは、発言が無視されたり拒絶されたりしない。
- このチームで仕事をする人たちは、互いに尊重し合っている。
チェックや捉え方のコツ
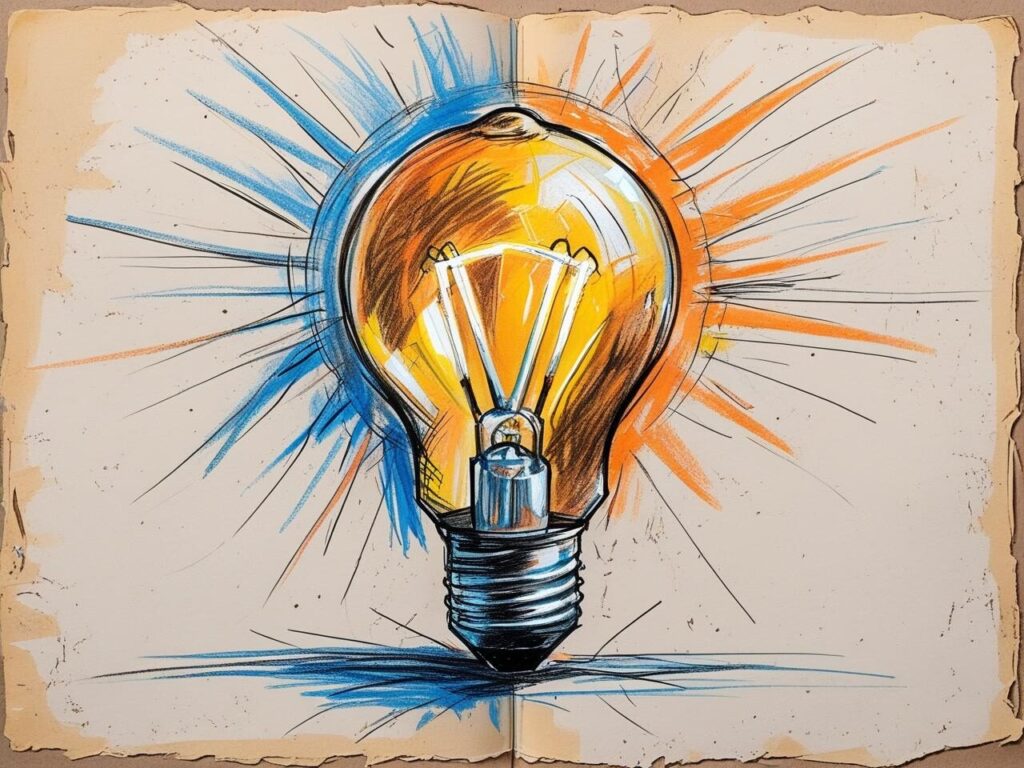
- 匿名での回答がおすすめ
→率直な回答を引き出すために、名前は書かずに集計しましょう。 - 定期的に実施する
→一度きりではなく、半年ごとなどに実施することで、チームの変化が見えてきます。 - 結果は“フィードバックの材料”と捉える
→低い点数が出ても、それは失敗ではありません。むしろ、改善へのヒントです。 - Webサービスやツールを利用する
→GoogleフォームやMicrosoft Formsなどを利用すると手軽に、答えやすく、集計しやすいアンケートが作成可能です。 - 「あるなし」ではなく「程度」
→心理的安全性は、「ある・ない」ではなく、「どれくらいあるか」を意識することが大切です。
とはいえ、悩んでいるあなたがこれをいきなり部下たちに聞いて回るのはハードルが高いと思います。
そういう方はまず自分で回答してみましょう。その結果を踏まえて、部下たちに改めて聞いてみるもよし、心理的安全性を高める施策を打ってからチェックしてみるのもよいです。
いずれにせよ、この7つの質問を通じて、自分のチームの“現在地”をぜひ確認してみてください。
心理的安全性を高めるリーダーの行動

心理的安全性を「高めたい」と思っても、
何から始めたらいいのか分からない
具体的にどんな行動を取ればいいのか迷う
という方も多いのではないでしょうか。
ここでは、明日から実践できる小さな行動に焦点を当て、リーダーの視点でご紹介します。
リーダーが取るべき行動

心理的安全性の土台は、リーダーのふるまいによって大きく左右されます。
以下のような行動を意識することで、メンバーに安心感を与えることができます。
①「わからない」と言える姿勢を見せる
自分の弱さや迷いを見せることで、部下も安心して発言できるようになります。
「分からない」があることが、この場では当たり前であると示すことが、発言のハードルを下げるのです。
例:「ちょっと私も確信がないんだけど、みんなの意見を聞きたいな」
②リアクションは“即・肯定”から始める
発言に対してすぐに否定や指摘をせず、まずは受け止めることで、話しやすさが格段に変わります。
例:「面白い視点だね」「それ考えてなかった、ありがとう」
③発言していない人にも声をかける
会議で話していない人には、個別に意見を求めることで“置いていかれていない”感覚を与えられます。
例:「○○さんはどう思う?ぜひ聞かせて」

声をかけても、ウンともスンとも意見が出てこない部下がいる場合は、こちらの記事も参考にしてみてください。
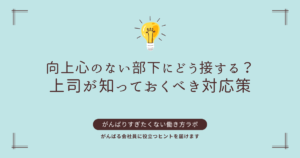
④失敗を責めるのではなく、“学び”を共有
ミスがあった時は、「なぜ起きたか」より「何を学んだか」を一緒に考えましょう。
原因の特定が必要な場合も、「なぜ」は基本的に相手の中にしか答えが存在しないものなのでプレッシャーの強い投げかけです。そのため、「何があったの?」など環境や状況に向くような質問をおススメします。
例:「この経験から、次にどう活かせそう?」
めのめMEMO
心理的安全性の担保に一番重要なのは、リーダーですが、当然メンバの振る舞いも重要になってきます。周囲に意識してもらうべきアクションも示しておくことをおススメします。
- 相手の話をさえぎらず、最後まで聞く
- 「それいいね」「なるほど」といった承認の一言を添える
- 自分の意見も、遠慮せずに出してみる
- 他者のアイデアに「乗っかる」姿勢を持つ(Yes, andの発想)
1on1は“心理的安全性を高める最前線”

特にリーダーや中間管理職にとって、1on1は心理的安全性を築く絶好の場です。
日常のちょっとした1on1の質が、チーム全体の安心感を育むベースになります。
1on1については、こちらで解説しているので是非参考してください。
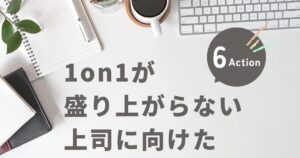
まとめ
心理的安全性まとめ

ここまで、心理的安全性の基本から実践方法までをご紹介してきました。
改めて、この記事のポイントを振り返ってみましょう。
| 要点 | サマリ |
|---|---|
| 心理的安全性とは? | 「自分らしく、率直に発言しても否定されない」と感じられる状態 単なる「仲の良さ」や「優しさ」ではなく、率直さと信頼のバランスが大切 |
| なぜ重要なのか? | 高パフォーマンスチームの土台 生産性・創造性・エンゲージメント・離職率に影響 |
| チェックするには? | 7つの質問で、現状の安全性を可視化 |
| どうやって高める? | リーダーの姿勢:弱さの共有・傾聴・承認・声かけ メンバーの行動:共感・尊重・自発的な発言 特に1on1の質が、チーム全体の空気を左右する |
まずは「一つだけ」変えてみよう

心理的安全性は、一朝一夕で高まるものではありません。
しかし、小さな一歩が確実に空気を変えていきます。
- 会議でのリアクションを変えてみる
- 1on1で「最近どう?」と聴いてみる
- いつも発言が少ないメンバーに声をかけてみる
そんなちょっとした行動が、
「このチームなら、自分の意見を言ってもいい」
そう思える人を一人、また一人と増やしていくのです。
心理的安全性は、高い成果とメンバが自分らしさを職場で活かす鍵となります。
この記事が、あなたのチームの風通しが良さとパフォーマンスの向上に役立つことを祈っています。
本記事は以下の資料を参照しています。
Google re:Work – ガイド: 「効果的なチームとは何か」を知る(Google)
https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team-effectiveness
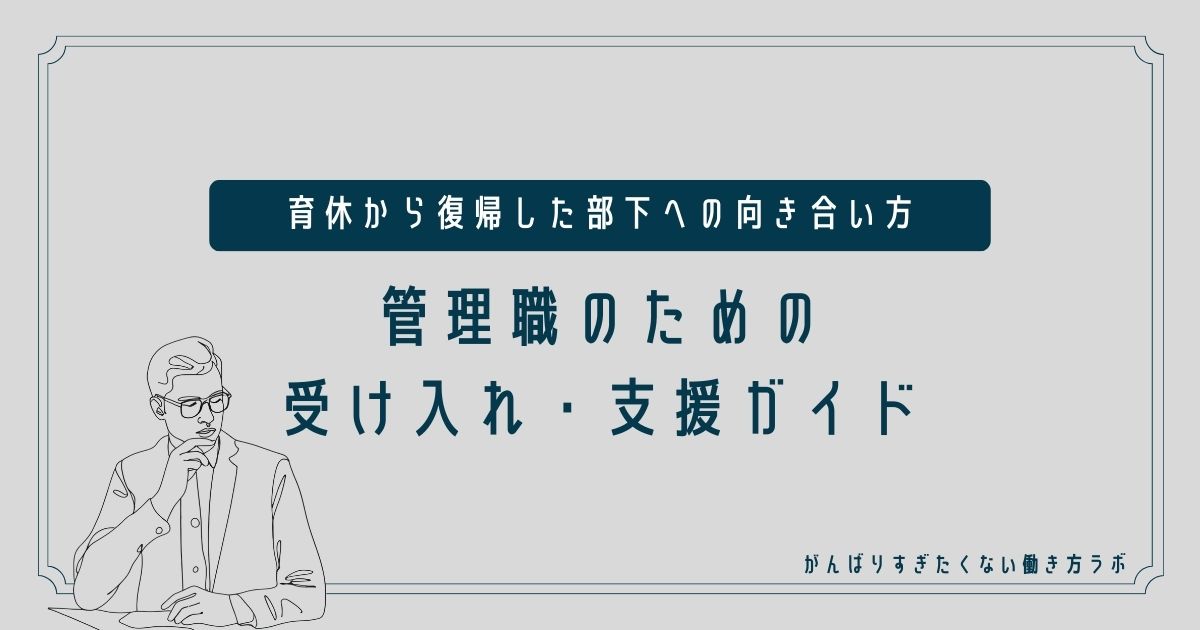
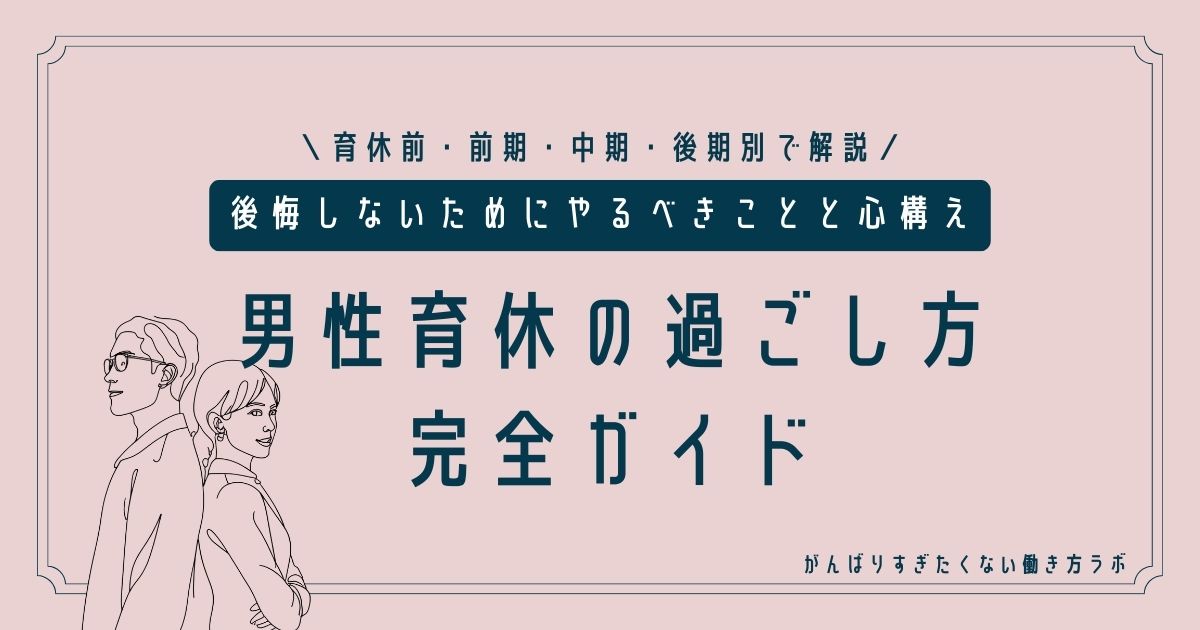
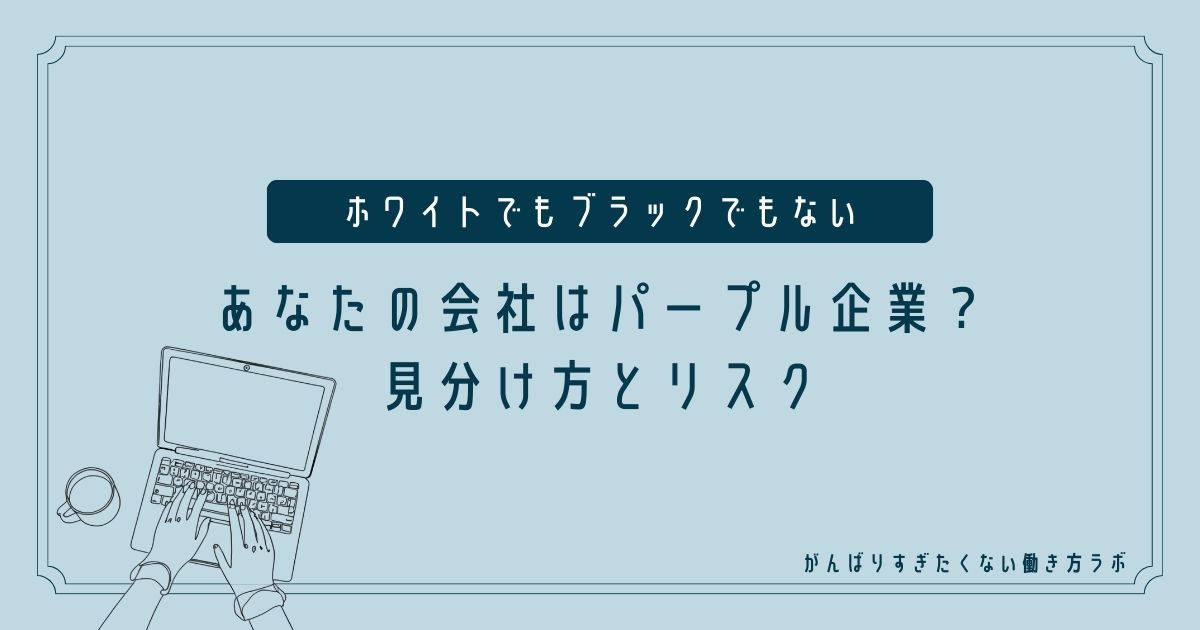
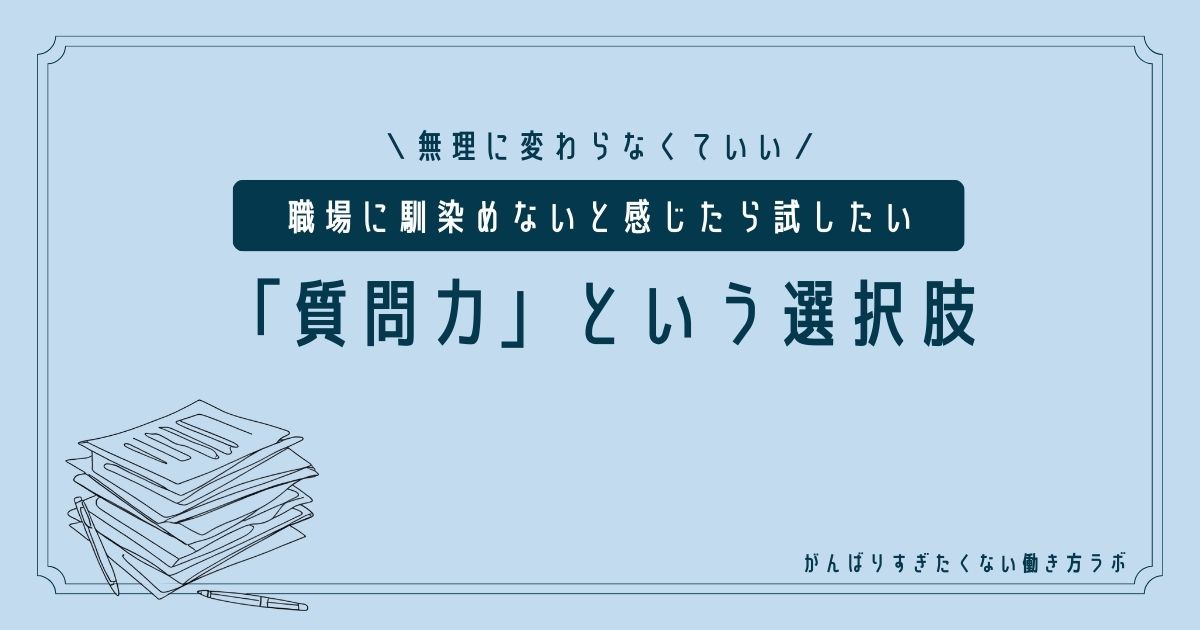
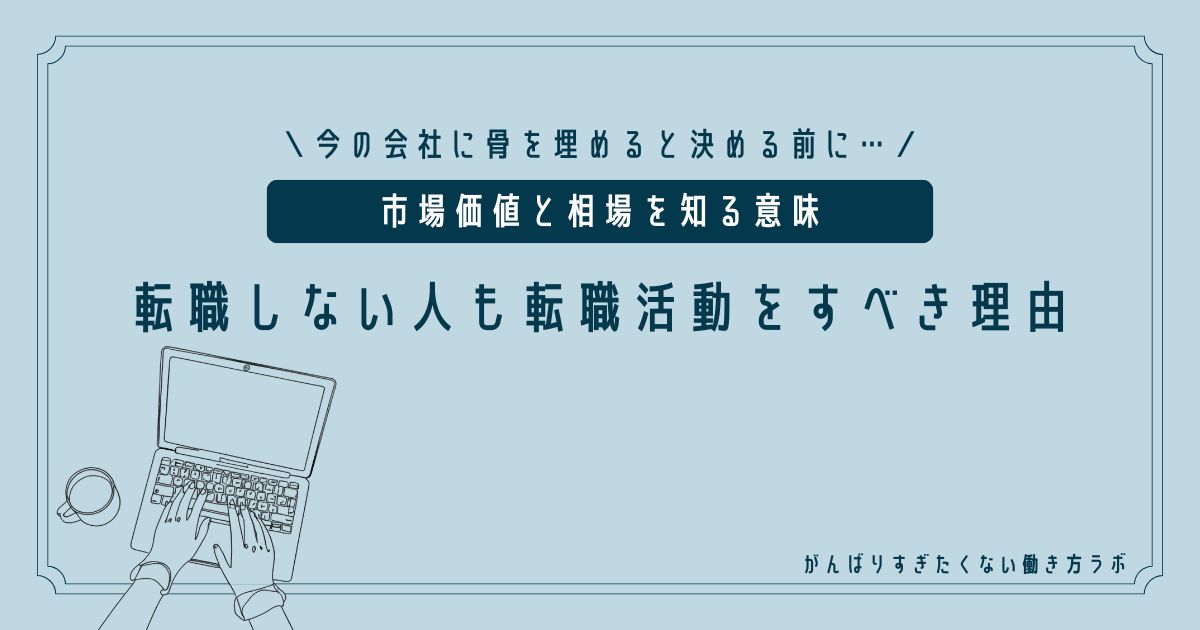
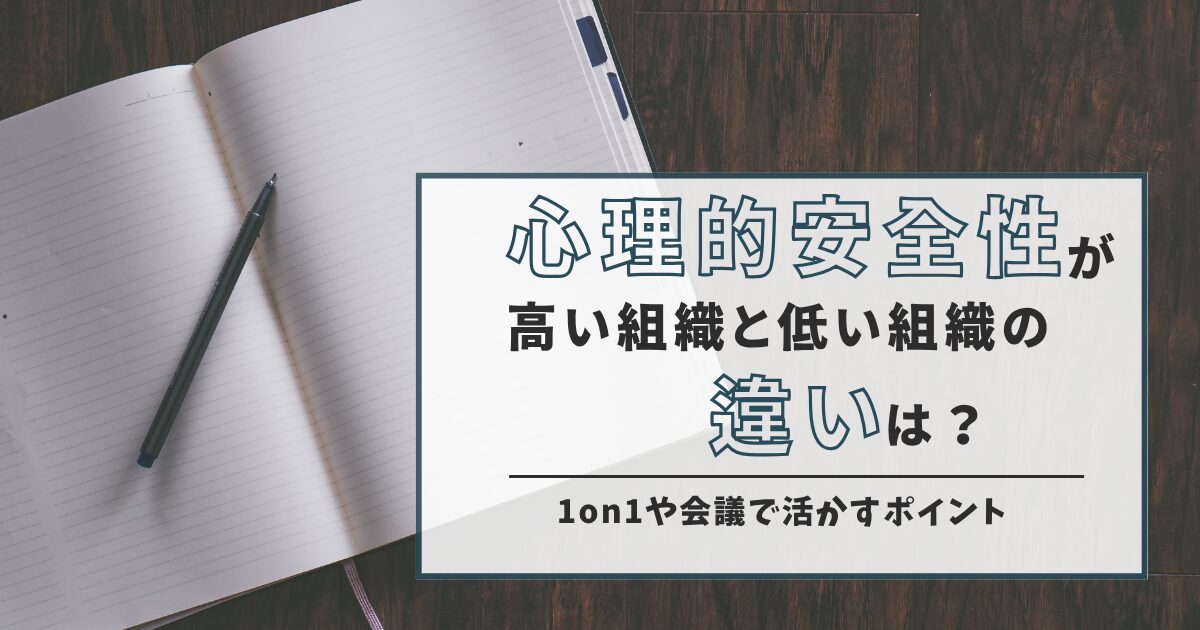
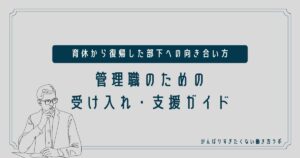
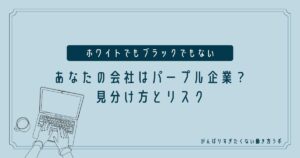
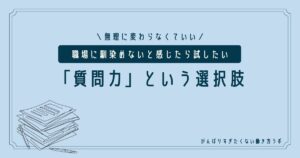
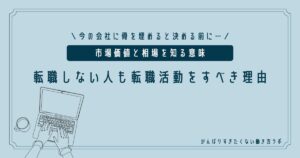
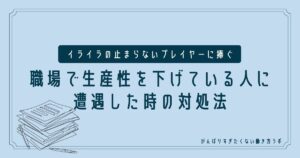
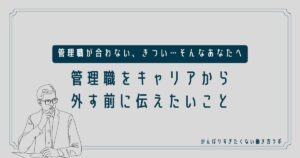
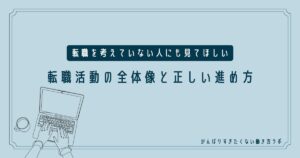
コメント