 部下
部下これって、どうすればいいですか?
毎日のように聞かれるこの質問に、正直うんざりしていませんか?
資料の作成方針、クライアント対応の判断、ちょっとした社内調整。
そのたびに答えを求めてくる部下に、
「もう少し自分で考えてから来てほしい」と思うのは、決してあなただけではありません。
上司としては、成長のためにあえて答えを与えない場面もあるはずです。
けれど、部下はまるで「正解探しゲーム」のように、あなたの顔色ばかり伺っている。
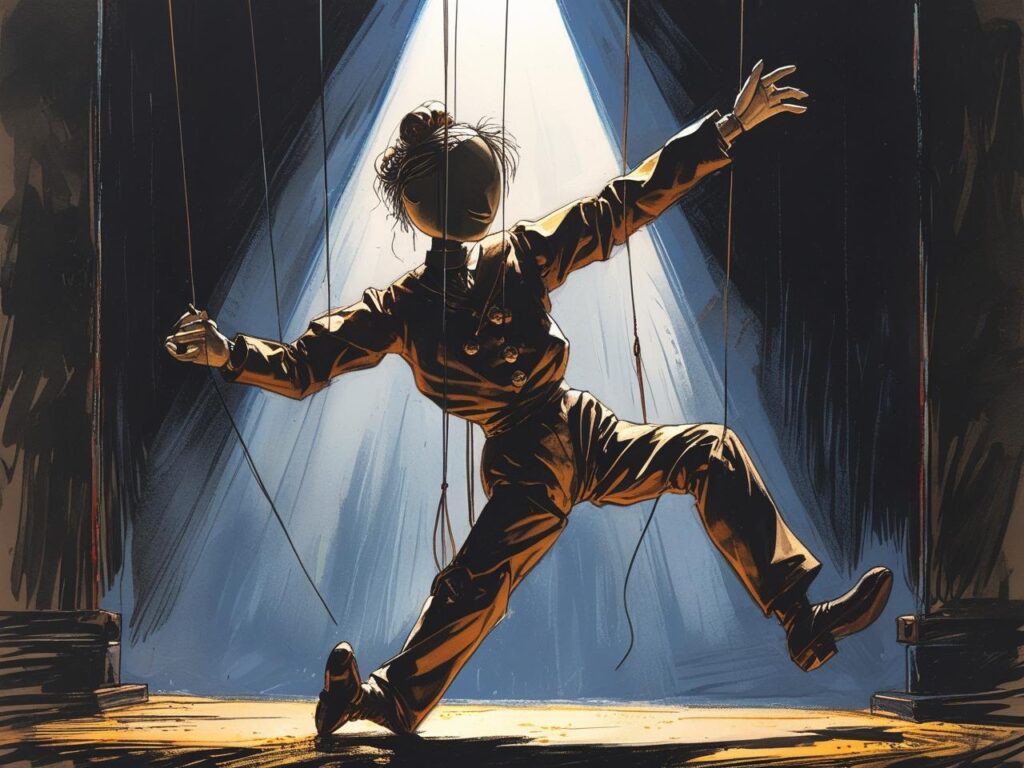
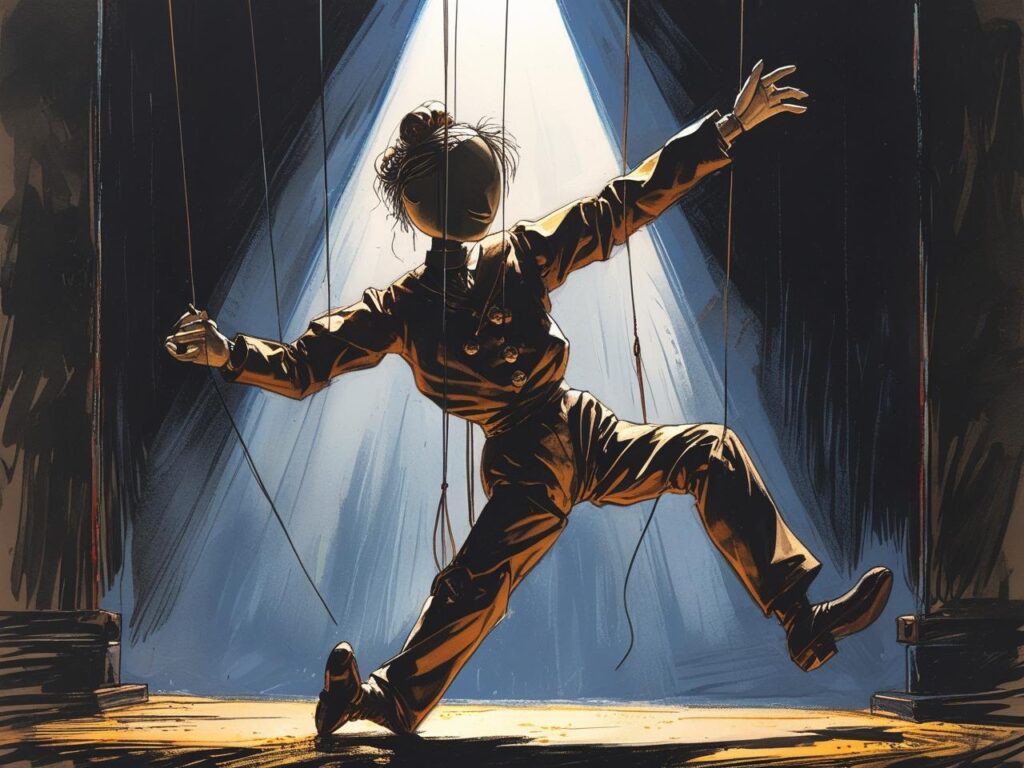
——いったい、なぜ部下は自分で考えようとしないのか?
——どうすれば、自走し、意見を出してくれるようになるのか?
本記事では、会社員歴15年以上、現役で10名の部下を持つ筆者が、部下が“すぐに答えを求めてしまう”理由と、
そこから脱却し「自分で考える力」を引き出すマネジメントのヒントをお伝えします。
自走したい部下の方はこちらの記事を読んでみてください
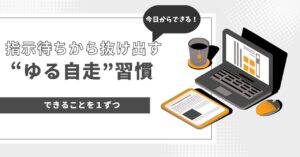
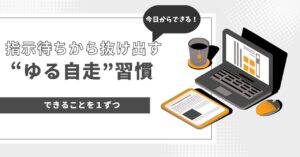
部下の思考を育てる指導ができているか?


部下が「考える力」を育てるためには、上司自身が“考えさせる環境”を整え、
支援と信頼をセットで提供することが不可欠です。
具体的には、
- 「教えるべきこと」と「考えさせるべきこと」を明確に分ける
- 部下の成長段階に応じて、必要な思考のヒントや安心感を与える
- 信頼関係を土台にしたコミュニケーションを重ねていく
上司の一言ひとことが、部下の“答え待ち”を助長することもあれば、
“自ら考え抜く力”を育てるきっかけにもなります。
部下の行動改善に向けた原因分析
部下がすぐに答えを求める理由5選
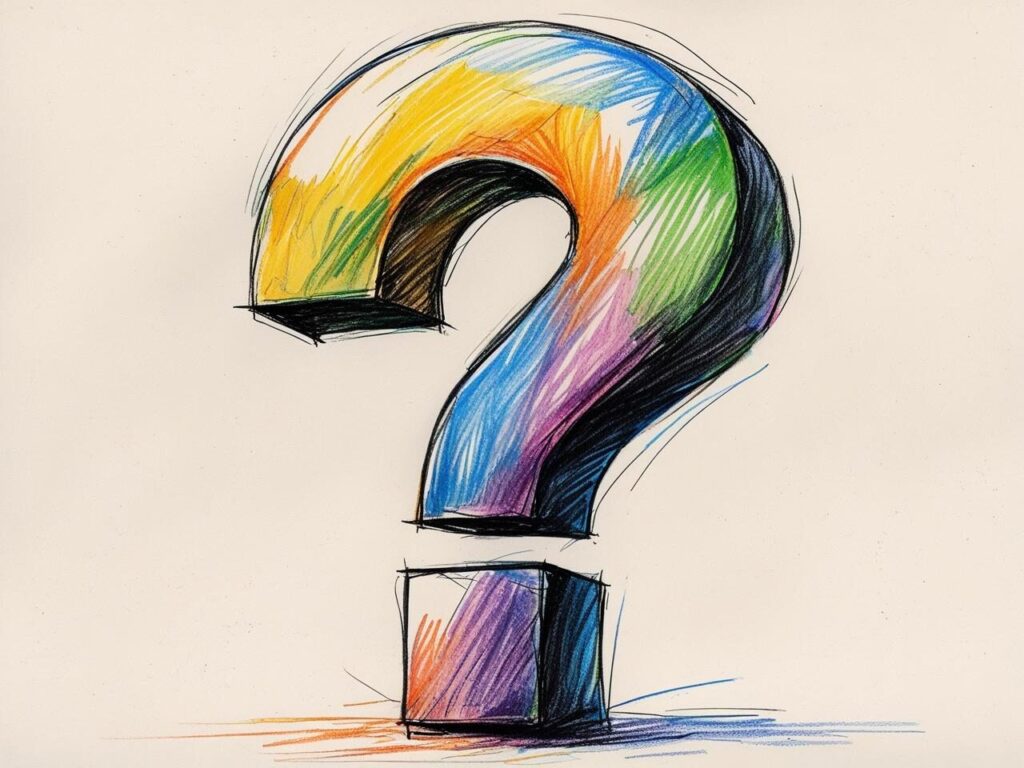
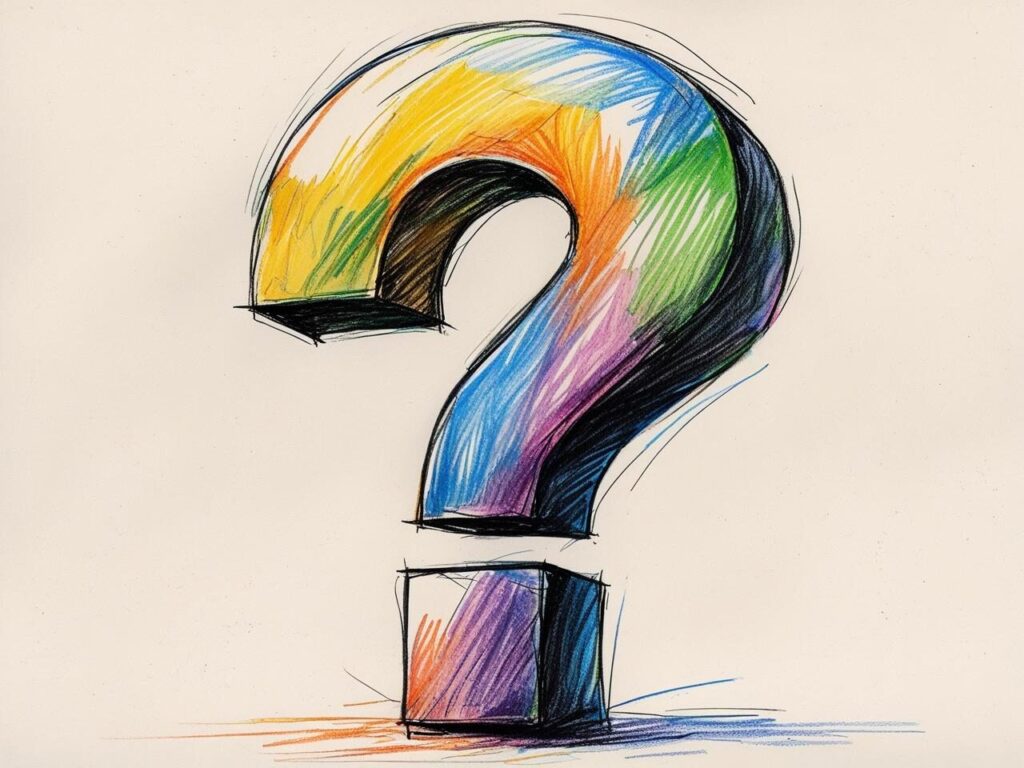
そもそも、部下がすぐに答えを求めてしまう背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。
代表的な理由を5つに整理すると、以下のようになります。
① 「失敗してはいけない」という心理的プレッシャー
近年の若手社員は「怒られること=評価が下がる」「失敗=信用を失う」と考える傾向が強く、
極端に失敗を恐れています。
そのため、少しでも曖昧さがあると自らの判断を避け、上司に答えを求めがちです。
② 正解主義に慣れた思考パターン
学校や新人研修で育ってきた「正解が必ずある」という環境に慣れているため、
ビジネスのように“グレーな判断”が求められる場面に不安を感じやすい傾向があります。
そのため、答えを探す=安心を得る手段になっています。
③ 自分の考えの言語化が苦手
自分の考えや感情を言語化すること自体が苦手な社員もいます。
なんとか捻りだした回答を、上司に指摘や指導を受けることで、余計に苦手意識が強くなり、
自分の意見を述べにくくなるという悪循環に陥ります。
④ 関係構築不足
部下とのコミュニケーションが不足しているか、信頼関係が築けていないために、
そもそも意思疎通がうまくいっていない場合もあります。
このような状況では、部下は上司を「自分の意見を積極的に述べるメリットがない」と判断し、
受け身になってしまうことがあります。
もし、この文章を読んで「部下が上司に自分の意見を述べるのは当然だ、けしからん」と思った方は要注意です。
あなたが部下を個人ではなく「部下」とみているように、
部下もあなたを「たまたま会社にあてがわれただけの上司」と思っている可能性が高いです。


⑤ 上司側の「育てるつもりのない指導」も原因
部下が考えないのは、実は上司側のスタンスに原因が潜んでいる場合もあります。
「思考の手がかりを与えない指導」や「答え合わせ前提のフィードバック」が影響している場合も少なくありません。部下にとって「何を考えるべきか」がわからなければ、自ら考えようにも考えようがないのです。
自分を変えて、部下の“答え待ち”が改善
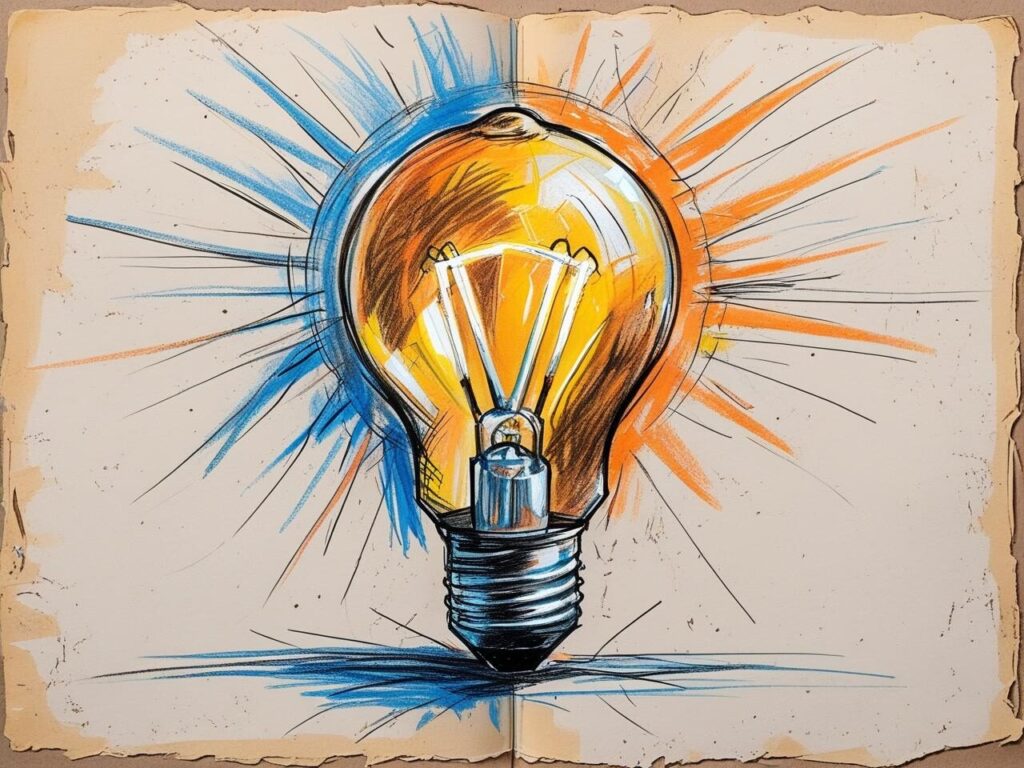
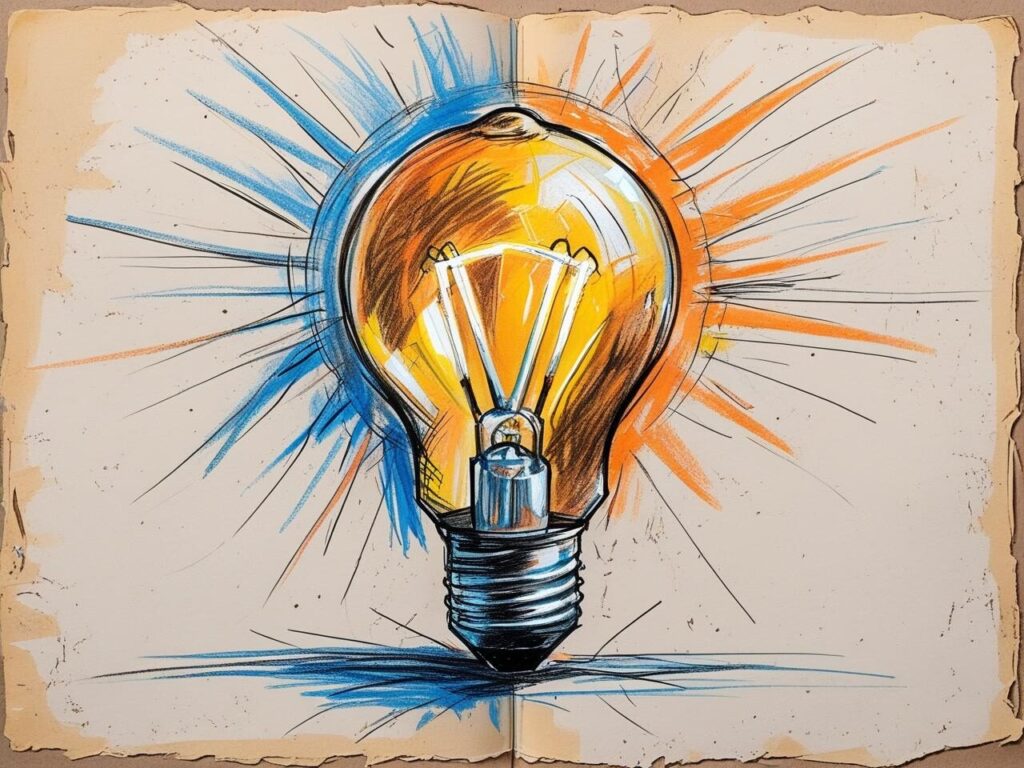
部下が「すぐに答えを求める」背景には、本人の性格や価値観もあるかもしれません。
しかし、それ以上に上司としての関わり方、
つまり「部下が考えやすい土壌をつくれているか」が大きく影響しています。
「教えるべきこと」と「考えさせること」をしっかり分け、
ヒントと安心感をセットで提供し、部下の思考や行動に寄り添うこと。
そうした日々の関わりこそが、部下の“自走力”を育てていきます。
そして、それはあなた自身の負担も確実に軽減する結果につながっていきます。
めのめMEMO
職場づくりや関係構築についてチェックリストを作ってみました。チェックが多いほど、赤信号です。是非あなたの職場の状態をチェックしてみてください
- 指示や質問に対して、部下が即「どうすればいいですか?」と返してくることが多い
- 部下が自分の考えを持たず、指示があるまで手を動かそうとしない
- 上司であるあなた自身が、「正解」を頭に描いて話していることが多い
- 部下に選択肢を与えるよりも、「こうして」と具体的な答えを与えることが多い
- 部下から「それってつまり何をすればいいですか?」と聞かれることが多い
- 失敗した際の原因分析では、プロセスよりも結果への指摘が中心になっている
- 部下からの報連相の頻度が過剰で、軽微な内容でも都度確認してくる
- 「自分で考えろ」と伝えたものの、部下が混乱し沈黙してしまった経験がある
- 会議や打ち合わせで、部下の意見よりも自分の意見が先に出てしまう
- 部下がミスをしたとき、「なにがあった?」ではなく「なぜそうした?」ときいている
状況改善のため上司にできる5つの具体策


具体的な対応に取り組みましょう。
部下に“考える習慣”を根づかせ、自走を促すために、上司として意識したい5つの行動をご紹介します。
①”教える”と”考えさせる”を分ける
すべてを“考えさせる”のは逆効果です。
たとえば、社内ルールや数字、手順といった「事実ベース」の情報は、迷わず教えた方が効率的。
一方、複数の選択肢がある場合や、判断が必要な場面では「考え方」や「判断軸」を伝え、
答えそのものは委ねるようにしましょう。
考えさせるべきことでも、部下がまだできていないポイントを一気に考えさせるときは要注意です。
わたしは、部下にプロジェクトマネジメントを引き継ぐ際、一気に役割の引継ぎを始めて、
すぐに部下がパンクしてしまった経験があります。
結果的に、役割を段階的に引き継ぐ方針に変えたところ、1か月ほどで引継ぎは終わってしまいました。
キャリアが長くなると、はじめて取り組むことへの感覚が鈍くなっていきます。
上司の手抜きで部下を苦しめないよう、「考えさせるべきこと」の与え方もしっかりと設計しましょう。
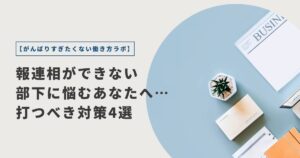
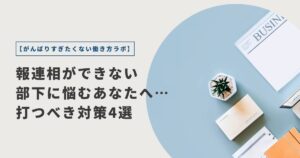
② 考えさせる時は「答えの出し方」を提示


「どう思う?」と聞くだけでは部下は困ってしまいます。
例えば:



このゴールに向けて、何から手をつけたらいいと思う?



もしAとBの選択肢があったら、どちらを選ぶ?その理由は?
このように、“考え始める入口”や“判断基準の枠”を示すことで、部下は前向きに思考を進めやすくなります。
③ 思考時間を与える
「今すぐ答えろ」は思考停止を招きます。
簡単に答えが出ない問いかけをしたなら、
「明日までに考えてもらえる?」
「15分くらい時間とって整理してみて」など、余白を与えることも重要です。
この時間を作るために、問いかけのタイミングを見極めることが上司の腕の見せ所です。
④ 信頼と安心の土台づくり


思考を促すには、まず「何を言っても大丈夫」という心理的安全性が欠かせません。
- すぐに否定しない
- 提案内容ではなく、考え方や姿勢を評価する
- うまくいかない場面でも分解して褒めるべき点をフィードバックする
- 感謝を伝える
こうした積み重ねが、部下の主体性を引き出す土台になります。
信頼関係の構築は小手先ではどうにもなりません。積み上げるためのそもそもの接点を増やすために、1on1ミーティングがおススメです。
私自身10名程度の部下がいますが、全員と定期で時間を設けて行っており、このおかげで普段の業務では接点の少ない部下からも相談されたり、直接ダイレクトメッセージがくる程度には関係性が築けています。
1on1ミーティングについてはこちらで解説しているので、興味がある方は是非ご一読ください。
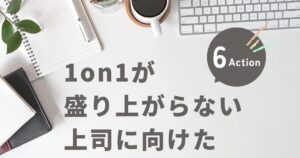
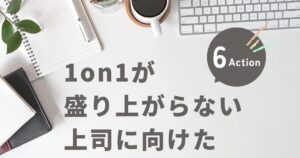
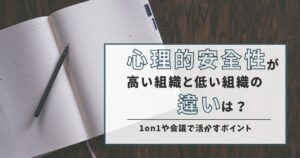
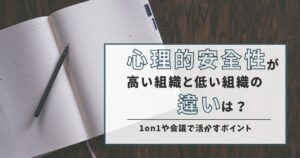
⑤ 部下の段階に応じて接し方を変える
当然、新入社員とベテラン社員では、考えられる範囲も経験も違います。
- 初心者:判断軸やプロセスを丁寧に見せてから、一緒に考える
- 中堅層:選択肢を並べさせ、理由を聞いてから方向性を修正
- ベテラン:自由に考えさせて、答えの“裏付け”に注目
また、能力や経験だけでなく、あなたとの関係性も段階に応じた接し方を意識してください
- 初期状態:まずは踏み込んだアクションよりも、お互いのことを知っている状態を目指す
- 関係構築済:本音で話せる関係のため、能力や経験に合わせた接し方を優先
部下の“今の段階”と、あなたとの関係性にあった投げかけを意識しましょう。
よくあるシーンとその改善ポイント


指示すると即座に答えを聞いてくる



で、どうすればいいですか?
→ 改善ポイント:まずは選択肢を与える。
「〇〇と□□の2つの方法があるとしたら、どちらを採用したい?その理由は?」というように、すぐに“正解”ではなく“考えるための材料”を提供することで、思考のプロセスを後押しします。
部下が提案してきたが、根拠が曖昧



○○をやってみたいです
→ 改善ポイント:思考の道筋を言語化させる。
「その考えに至った背景は?」「他に選択肢はなかった?」「それをやるとどんなリスクがある?」など、部下が自らのロジックを振り返る機会を作ることで、思考力が鍛えられます。
質問の嵐…こちらの手が止まってしまう



これって最初はどうすればよいですか



お客さんからメールがきたんですけど



今度の懇親会のお店、どんな風に探せばいいですか
→ 改善ポイント:「考えてから聞く」のルールを共通認識に。
「質問をする前に、どう考えて、どこで詰まったのかを書き出してから相談して」と事前条件を設けることで、
質問そのものの質が上がりますし、あなた自身の工数も下げられます。


全体に共通する話として、部下本人のパーソナリティによる可能性もありますが、
「過去の成功体験」から繰り返しに繋がっているケースもあり得ます。
例えばケース③でいえば、過去にあなたから



質問が多くてよいね



これからもわかないことがあれば何でもきいてね
と言われた過去があるケースです。
褒めるのはとてもよいことですが、
このようなケースで単に「質問をする前に、自分で考えてから相談して」と伝えてしまうと
“一貫性のない上司”という印象を与えます。



分からないことも減ってきたと思うし、次はステップアップして、自分で考えて何が分からなかったのか書き出してから相談してみようか
など、一貫性を持ちつつ次の期待を具体的に伝えるようにしましょう。
部下の成長を願う前に、上司ができること
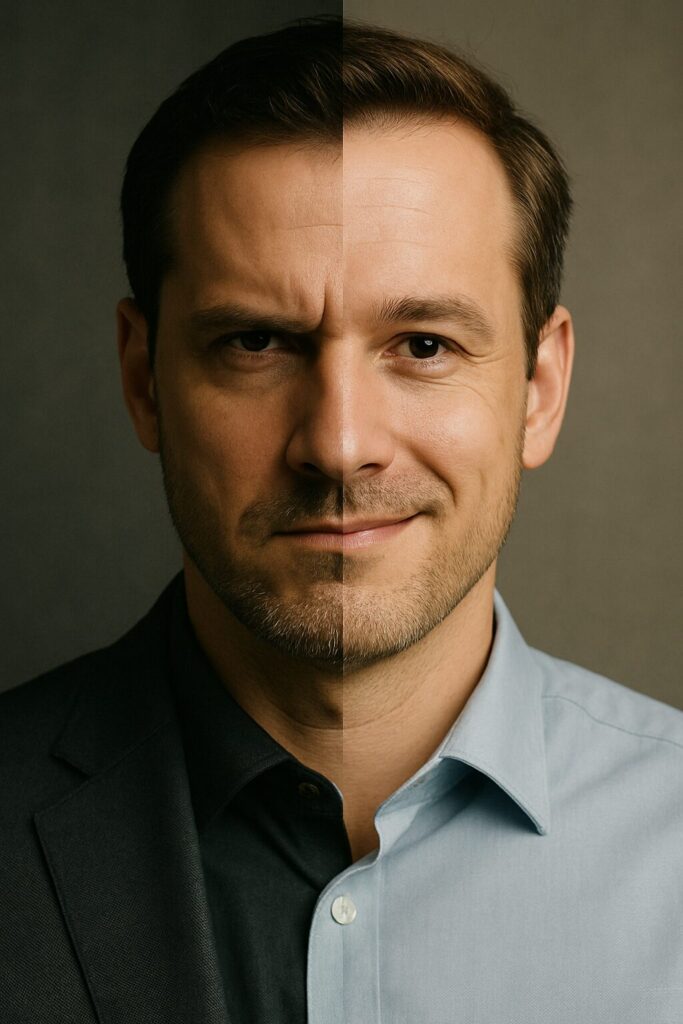
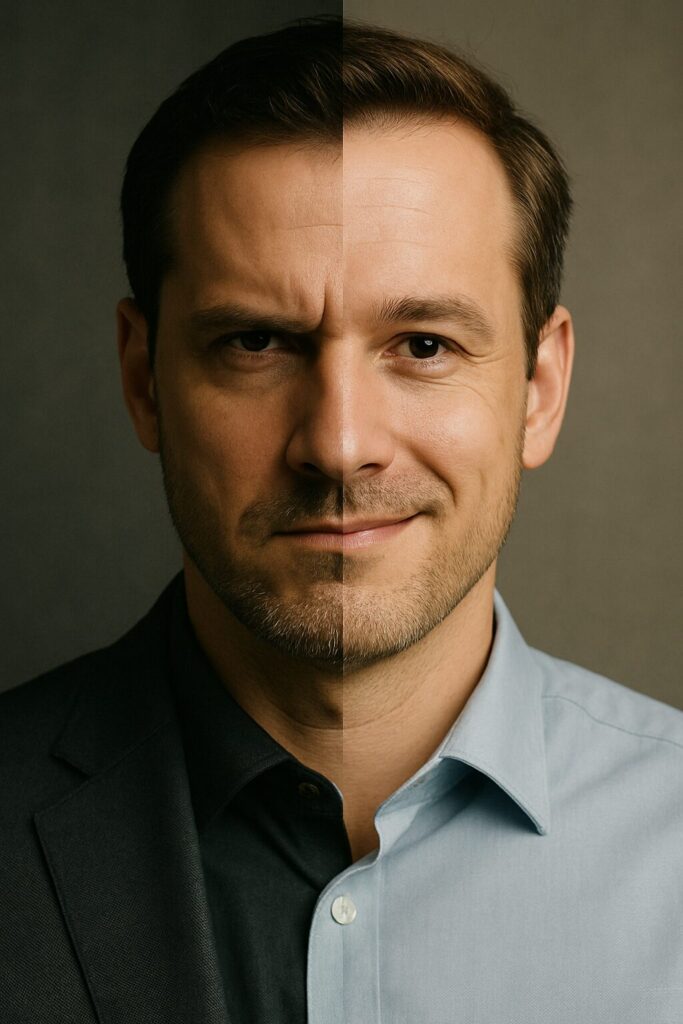
すぐに答えを求める部下に悩んだとき、まず見直すべきは、
「自分の指導が、部下の思考を育てる設計になっているか」です。
部下が自ら考え、意見を持ち、成長していくためには──
- 教えるべきことと考えさせることを明確に分ける
- 考え方の道筋や判断のヒントを提示する
- 即答を求めず、思考の余白を与える
- 部下の段階に応じて、問いかけやサポートを変える
- 心理的安全性のある信頼関係を築く
これらを意識したマネジメントが、「指示待ち部下」を「考える部下」に変える第一歩になります。
正解を“再現させる力”を育てるのが、育成です。
今日からできる一つの行動から、未来のチームが変わっていきます。
「部下に悩む上司」向けのシリーズはこちら
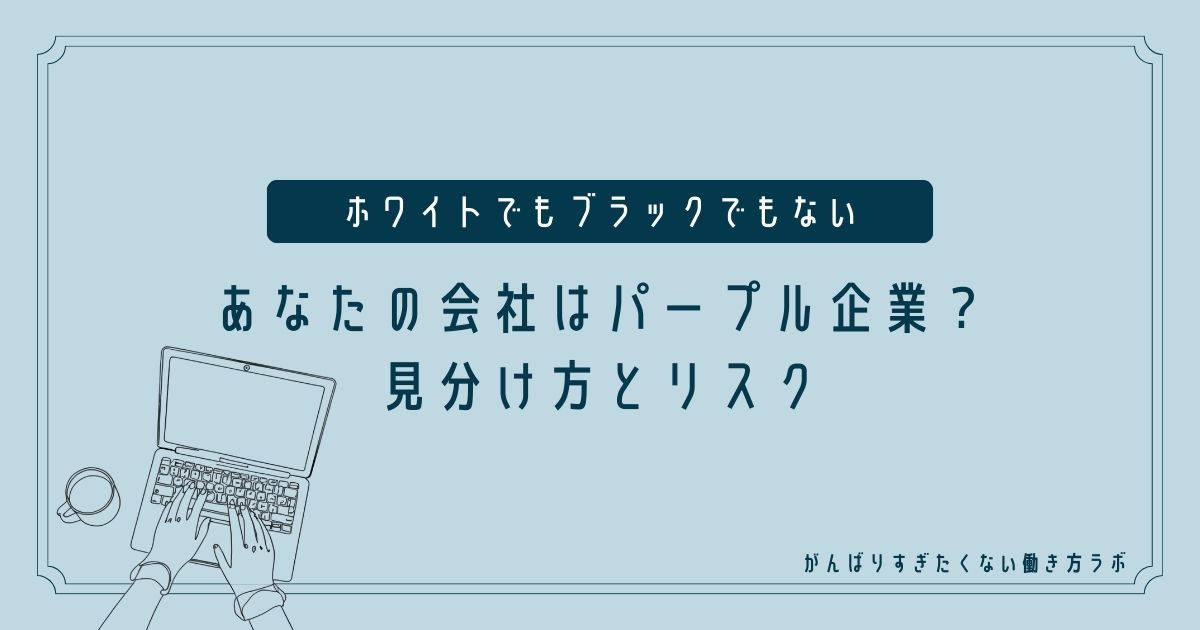
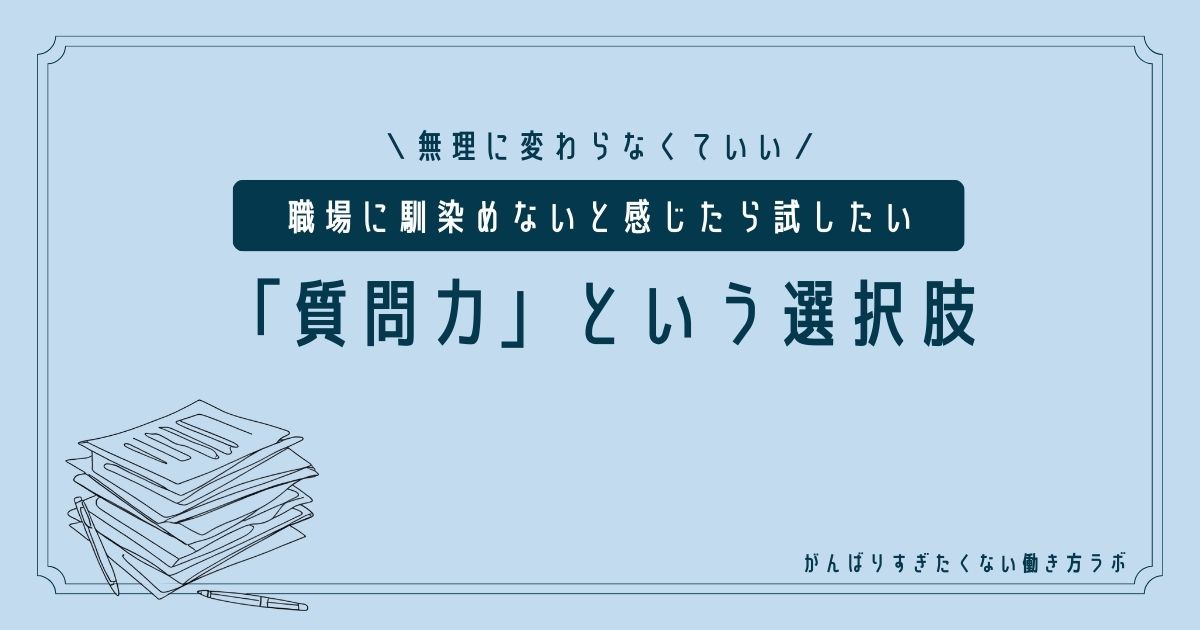
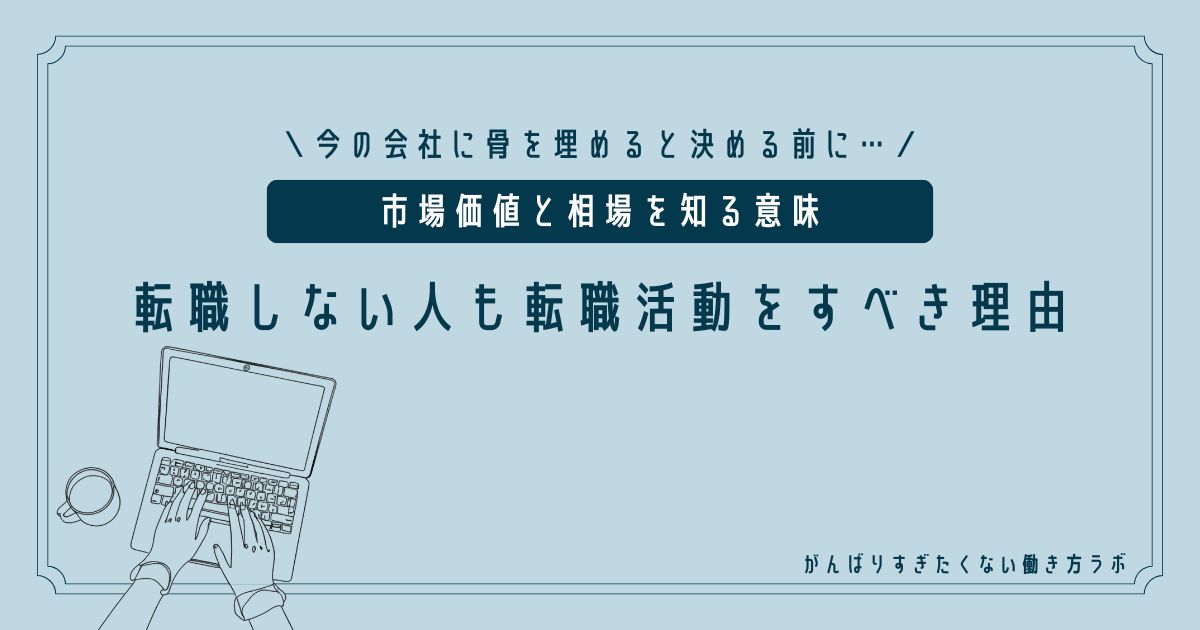
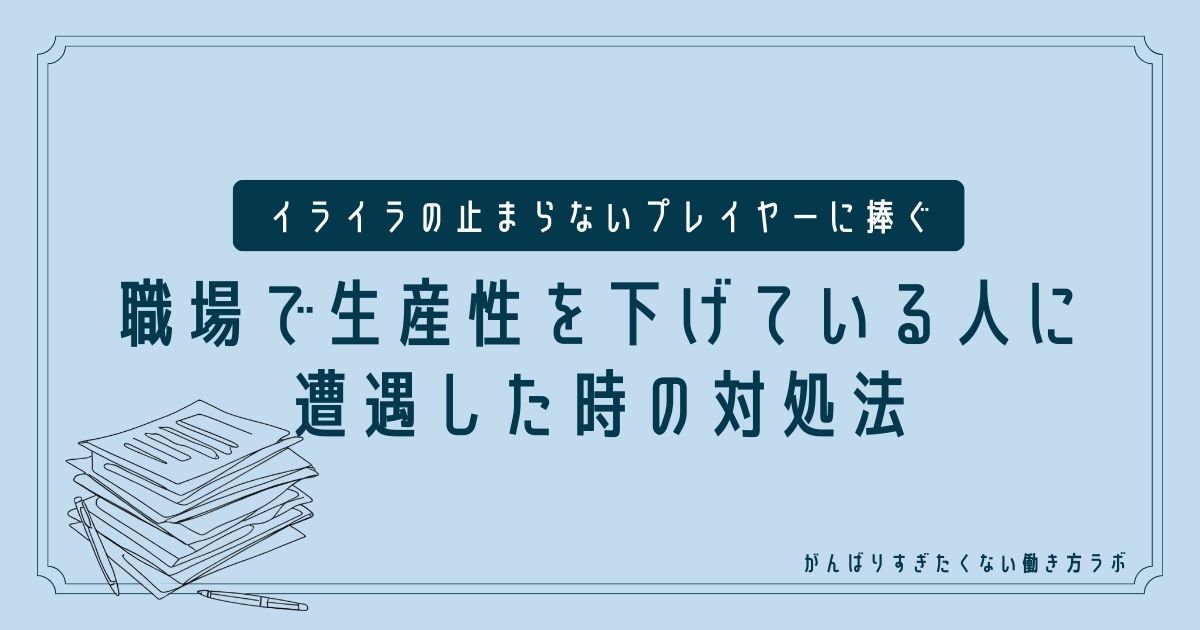
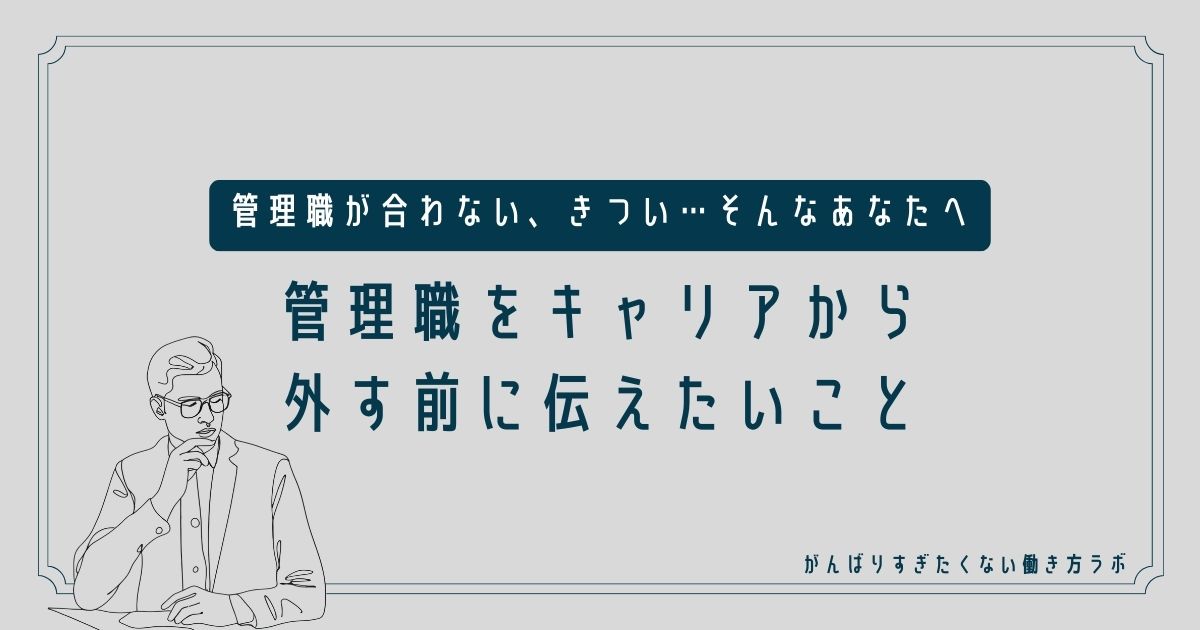
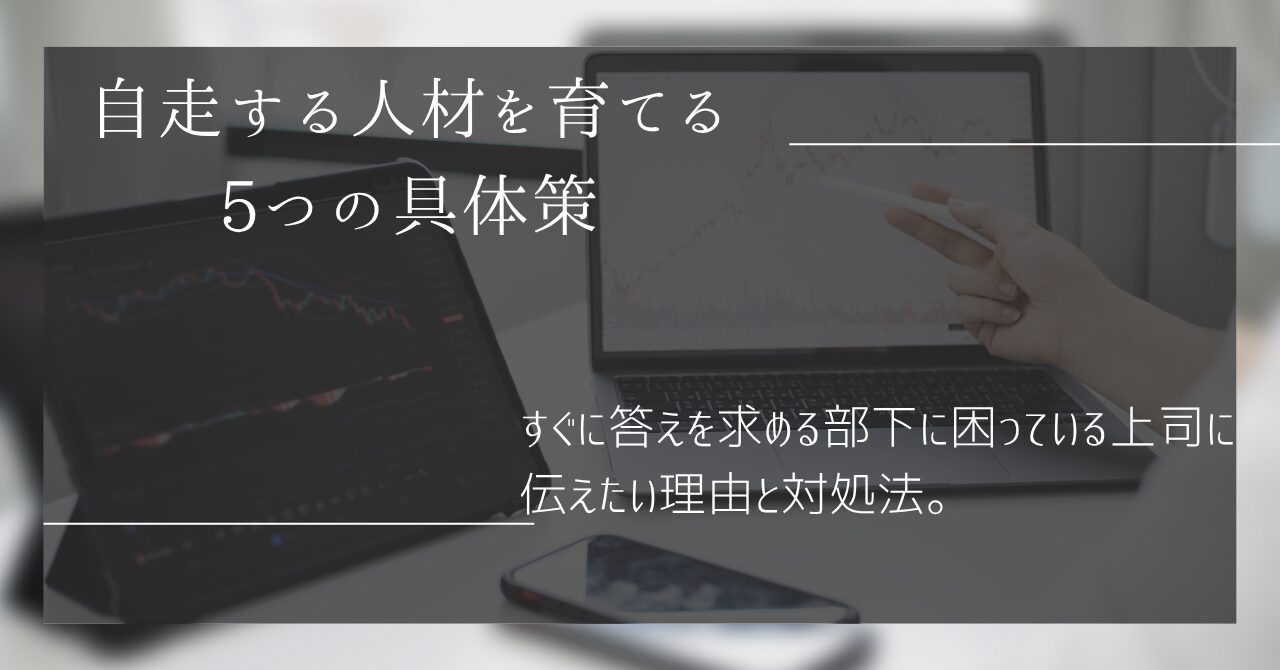
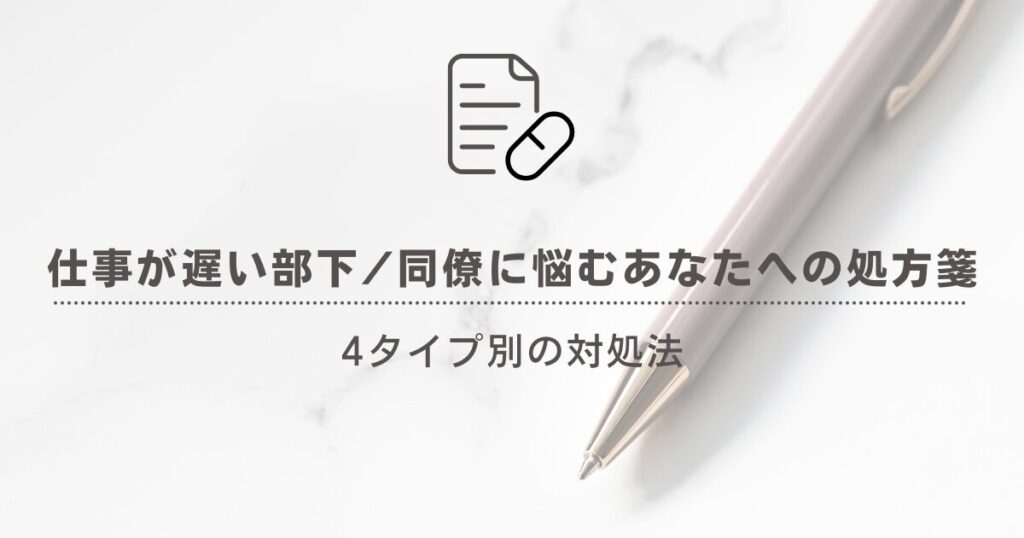
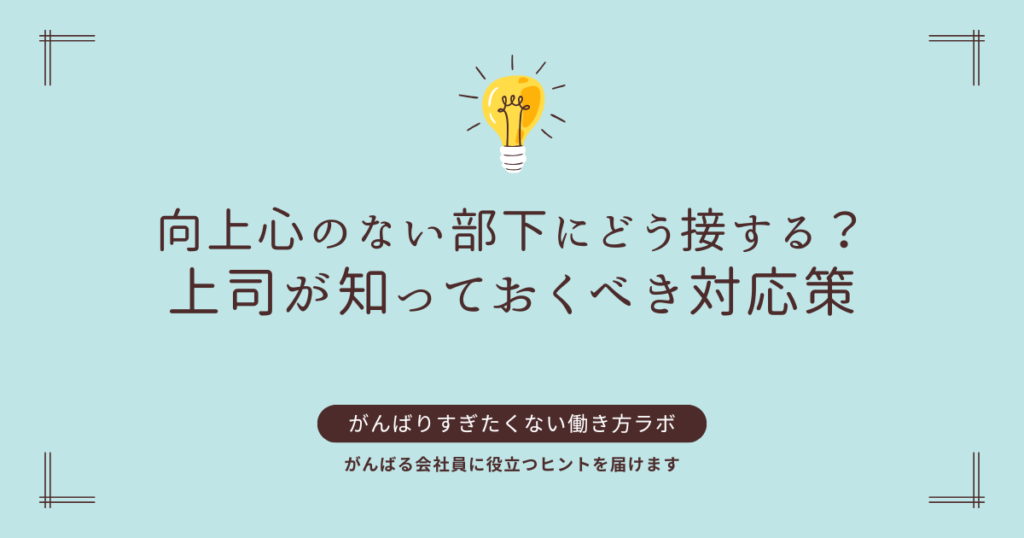
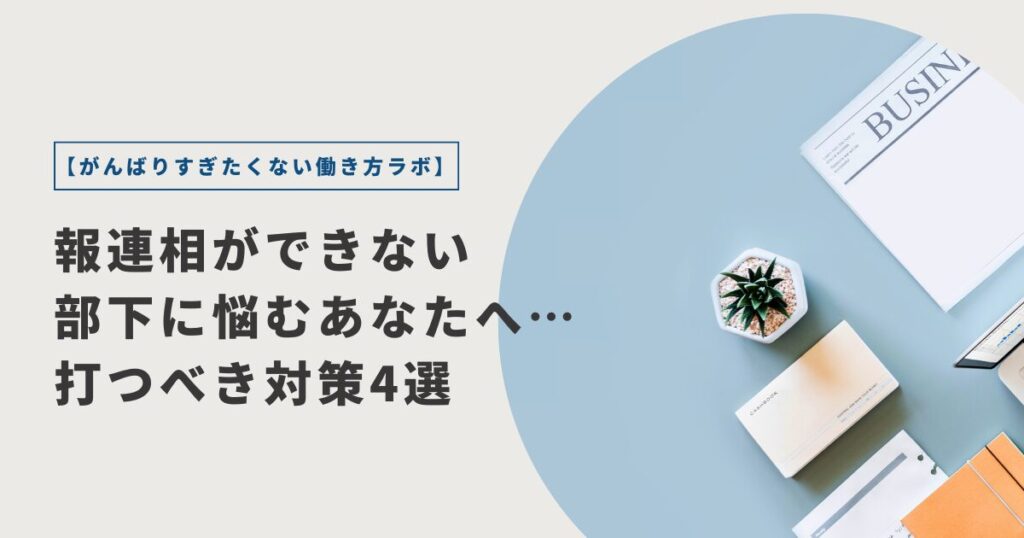

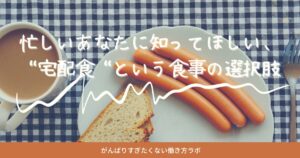
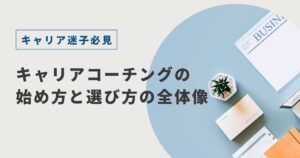
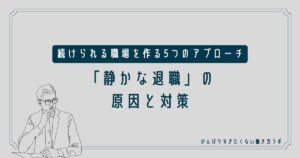
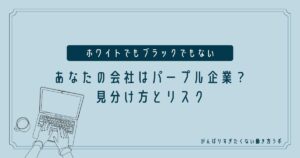
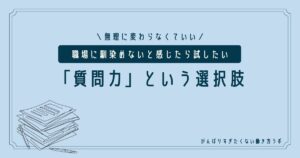
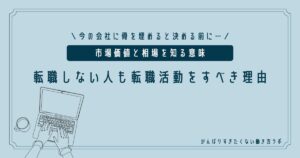
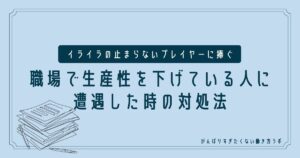
コメント