最近、「静かな退職(Quiet Quitting)」という言葉を耳にする機会が増えました。
表面上は問題なく働いているものの、心の中では“もうこれ以上は頑張らない”と線を引く、
「最低限の業務だけをこなし、プライベートを優先する生き方」、そんな静かな離脱を指す言葉です。
一見、本人の選択に見えるこの現象。
しかし実際には、チーム全体の活気を少しずつ奪い、成果や雰囲気にまで影響を与える“組織のサイン”でもあります。

最近、メンバーが自発的に動かなくなった



以前より会話が減った気がする
──そんな違和感を覚える管理職の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、会社員歴15年以上、現役で10名以上の部下を持つ管理職の筆者が、
「静かな退職」がなぜ起こるのか、そしてどうすれば“続けられる職場”をつくれるのかを、
マネジメントの観点から解説します。
読み終えるころには、「静かな退職」を防ぐために管理職が今日からできる具体的な一歩が見えてくるはずです。
静かな退職は職場環境のサイン
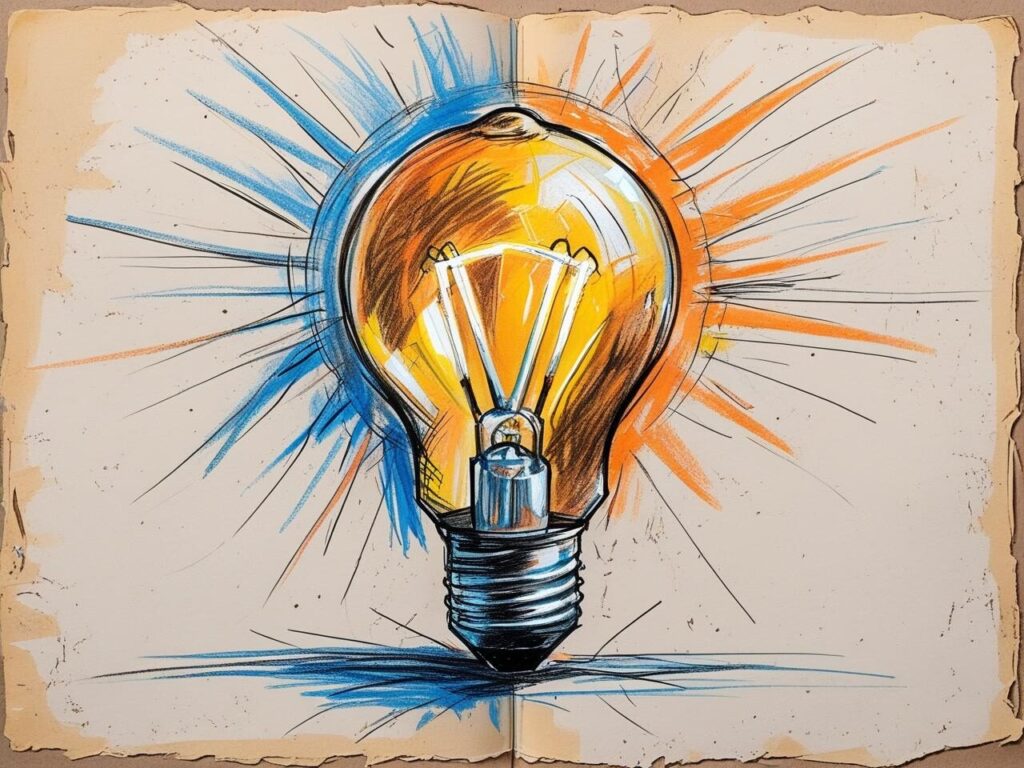
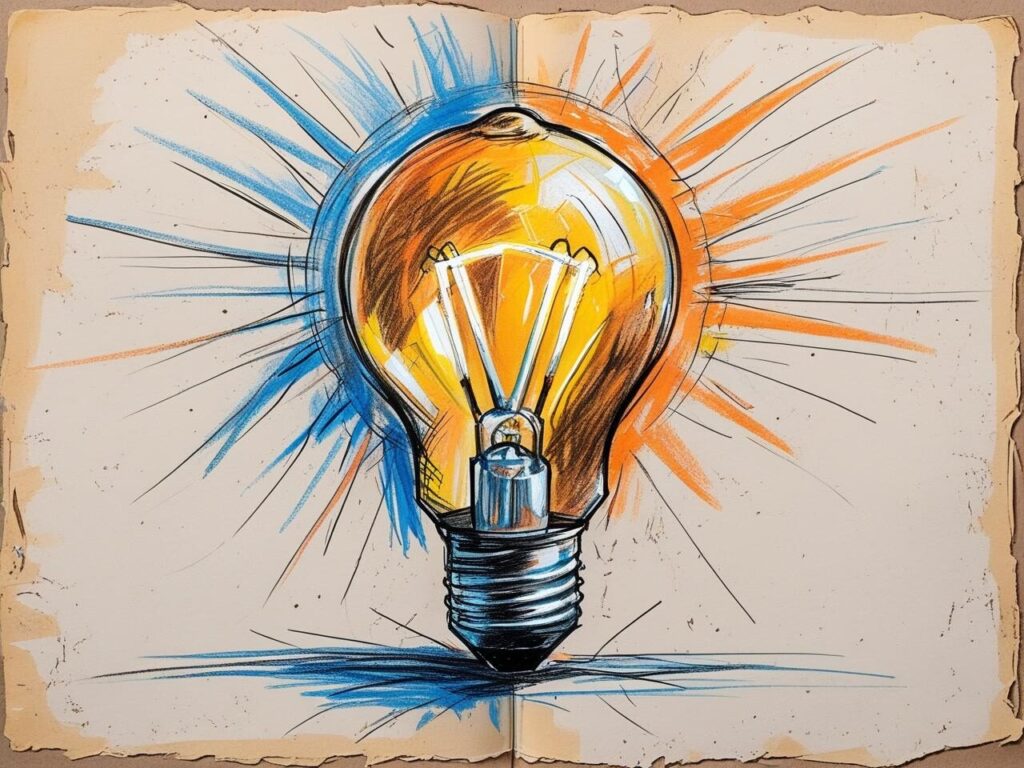
「静かな退職」は、決して“怠け”や“甘え”だけの問題ではありません。
その多くは、職場の環境や関係性が、本人の意欲を維持できない状態にあることのサインです。
つまり、職場のつくり方を見直すことで、改善できる余地があります。
一方で、すべてのケースが環境改善だけで解決できるわけではありません。
価値観の変化や人生の優先順位の違いなど、個人の選択としての静かな退職も確かに存在します。
だからこそマネジメントに求められるのは、「誰かを変えよう」とすることではなく、
まずは“話せる環境”と“試せる余地”をつくり、改善の可能性を探る姿勢です。
そして、アプローチを重ねても変化が見られない場合は、
本人の意思を尊重しつつ、異動や役割の再設計など、組織としての対応を検討する。
このような二段構えのマネジメントが、チーム全体の健全性を保つ鍵になります。



貯蓄や金融資産が十分あり、「上がり」が見えている人が「静かな退職」を選ぶ可能性はあります。現実的な話として、このようなタイプを周囲にが改善させるのは困難でしょう。
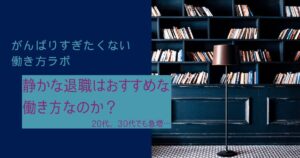
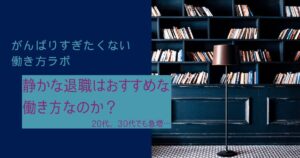
チームを蝕むのは沈黙の広がり
静かな退職は“静かに”チームを壊す


静かな退職は、目立つ問題行動がないぶん、気づかれにくいのが厄介です。
本人は最低限の業務をこなしているように見えますが、
主体的な発言や挑戦が減り、チームの活気がじわじわと薄れていくのが特徴です。
その結果、周囲のメンバーに「自分ばかり頑張っている」という不公平感が生まれ、
モチベーション低下や離職につながることも少なくありません。
つまり、静かな退職は“静かなまま”チーム全体の土台を侵食していく現象なのです。
価値観の多様化で「熱量の基準」が変わった


かつては「長時間働く」「会社に尽くす」ことが“やる気”の象徴とされていました。
このような人物がいる場合、後ろ指をさされたり、自然と集団から弾かれて、窓際に追い込まれたのです。
しかし、いまは働く人の価値観が多様化し、プライベートの充実や健康、家族との時間を重視する人が増えています。
そんな人たちにとって、一見「静かな退職」は魅力的に映ることもあるでしょう。
この変化にマネジメント側が対応できないと、「自分の価値観が否定された」と感じ、
心の距離を置くメンバーが増えてしまいます。
「静かな退職」は、時代の価値観に組織文化が追いついていないサインとも言えるのです。



「静かな退職」に限らず、雇用の流動性や、フリーランスの一般化など、組織文化や仕組みは常にアップデートを求められている時代です。
だからこそ、管理職は今後も需要の尽きない職だと考えています。
理由③:放置すれば“優秀な人”ほど離れていく


静かな退職を放置し、蔓延すると、最初に離れていくのは“熱意のある人”です。
「頑張っても報われない」「意見を出しても変わらない」――そう感じた主体性のある人間ほど、
成長意欲を保つために自ら別の環境を選びます。
逆に、組織が安心して挑戦でき、評価する環境を整えていれば、優秀な人材が定着し、周囲への好循環も生まれます。
つまり、“静かな退職”を防ぐことは、人材流出を防ぎ、チームの信頼と成長を守ることに直結しているのです。
「続けられる職場」を作る5つのアプローチ
静かな退職を防ぐために大切なのは、
“意欲を引き出す”ことよりも、“意欲を保てる環境”をつくることです。
ここでは、明日から試せる5つの実践アプローチを紹介します。
心理的安全性をつくる


まずは、「話しても大丈夫」な空気を整えること。
不満や違和感を話せる“対話の場”を意識的に作り、業務の進捗だけでなく、感情や価値観にも耳を傾けましょう。
小さな不満や違和感を早期に拾い、業務量の偏りや過剰な期待を見直すことで、
静かな退職の芽を摘むことができます。
また、会議で「意見を出してくれてありがとう」と反応し、「意見を述べること自体」に価値を持たせることで
安心して発言できる文化づくりにつながります。
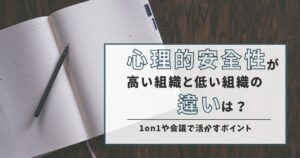
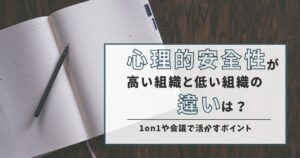
チャレンジを奨励し、失敗を許容する


「失敗を恐れて動かない」職場では、静かな退職は加速します。
人は、挑戦しても責められない環境でこそ、意欲を取り戻します。
大切なのは、失敗を減らすことではなく、失敗を通じて次へ活かそうとする姿勢を認めること。
上司が「責任は私がとる」と言葉にするだけでも、チームの空気は変わります。
挑戦を尊重する文化が根づけば、「静かな退職」に流されるメンバも自然と減っていきます。



当然、管理職本人がチャレンジしないことには文化の醸成はありません。
わたし自信は、顧客への新規提案や、組織へのルールの変更交渉など、積極的にチャレンジし、チームでおそらく一番失敗しています。
失敗の事実は隠さず、学びなども合わせてチーム内に発信することで、「正しい失敗」の仕方を示しています。
評価の透明性を高める


静かな退職の背景の1つに、「評価が不透明」という意識からくる無力感があります。
「努力してもしなくても何も変わらない」という認識が、「静かな退職」を選ばせるのです。
組織の評価制度を一個人が変えるのは困難でしょうが、
あなたが何を評価し、どう判断しているのかを言語化するだけで、メンバーの納得感は大きく変わります。
成果だけでなく、再現性を伴うプロセスやチーム貢献も評価項目に含めることで、
「報われる実感」を持てる職場に変わっていきます。



成果やプロセスは定量的/定性的に評価し、本人の努力には感謝を伝える。これが私の基本スタンスです。
学びと成長を支援する
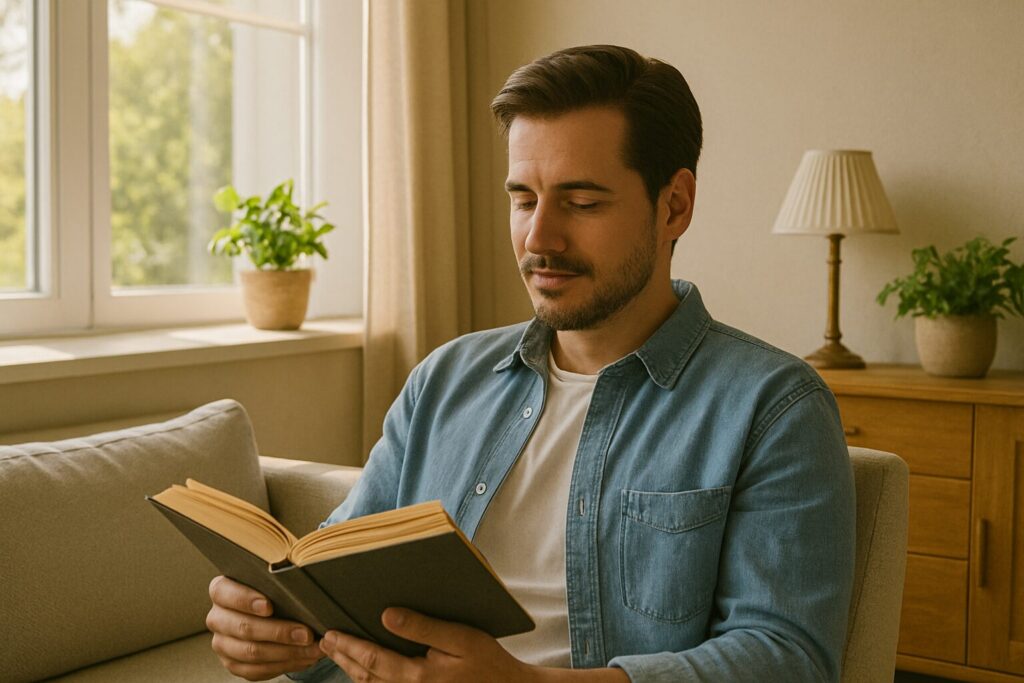
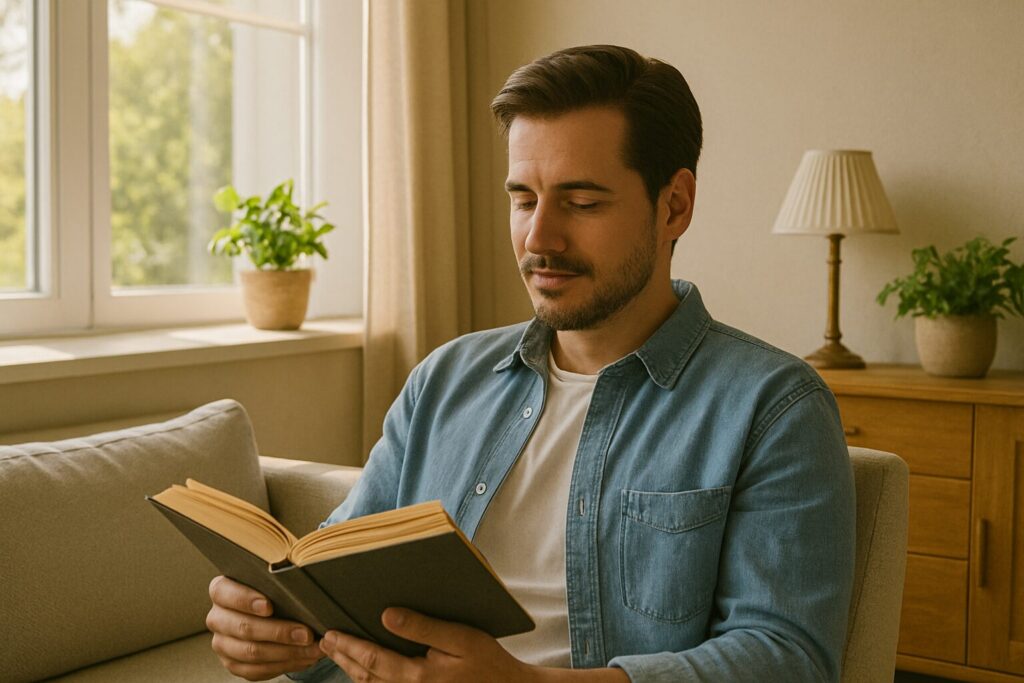
成長の停滞は、静かな退職を招く大きな要因です。
OJTに頼るだけでなく、社内勉強会や社外のセミナーなど小さな学びの機会をできるだけ提供しましょう。
「リスキリング」といった大掛かりな仕組みでなくても、“自分の成長や変化を感じられる”環境が、
仕事への前向きさを支えます。
組織の目的と理念を再確認する


「なぜこの仕事をしているのか」「自分たちは何を目指しているのか」。
この“共通の物語”が見えなくなると、個々がバラバラに動き始めます。
チームとしての方向性を定期的に話し合い、
仕事の意義や方向性を再共有する場を設けることで、静かな退職は確実に減ります。
これらに共通するのは、どれも大きな制度改革ではなく、小さな対話と設計の積み重ねで実現できるという点です。
「働く人を変える」よりも、「働く環境を少しずつ整える」。
それが、静かな退職を防ぐための現実的で持続可能なアプローチです。
こうした小さな改善が、静かな退職の予兆を和らげ、チームの空気を変えていきます。
静かな退職を防ぐ鍵は、対話から始まる


“静かな退職”は、個人の怠慢ではなく、職場の環境や関係性の「結果」として起こる現象です。
そのため、まず取り組むべきは「人を変える」よりも「環境を整える」ことと説明してきました。
しかし、それでも改善が見られない場合は、
本人の価値観やライフステージを尊重した上で、異動や職務再設計を検討することも大切です。
「無理に変えようとし、衝突する」よりも、「お互いにとって健全な距離をとる」ほうが、
長期的には双方にとって良い選択になる合理的な判断です。
静かな退職を“防ぐ”ことは、単に生産性を守ることではありません。
それは、「人が安心・納得して働ける職場」をつくる行為そのものです。
あなたのチームにいる“静かに悩んでいる誰か”を、見過ごさないためにも、是非一歩を踏み出してみてください。
静かな退職への対処は職場全体を健全にする


“静かな退職”という言葉を聞くと、どこか他人事のように感じるかもしれません。
人によっては「そんな働き方をしている人間に割く暇はない」と思う方もいるでしょう。
けれど実際には、誰もがいつその境界線に立ってもおかしくない時代です。
働く人の価値観が多様化し、「がんばり方」も人それぞれになりました。
だからこそ、「がんばらない=悪いこと」ではないという前提を、私たちがもう一度見直す必要があります。
そのうえで、チームとしてどう関わるのか――。
“静かな退職“を選んだ本人にフォーカスするのではなく、
管理職らしく”静かに退職”を選ぶような人間が増えない職場に変えていくこと。
それが、持続可能な職場づくりの第一歩になるはずです。
この記事が、あなたの職場がより良くアップデートしていくきっかけになれば幸いです。
「部下に悩む上司」向けのシリーズはこちら
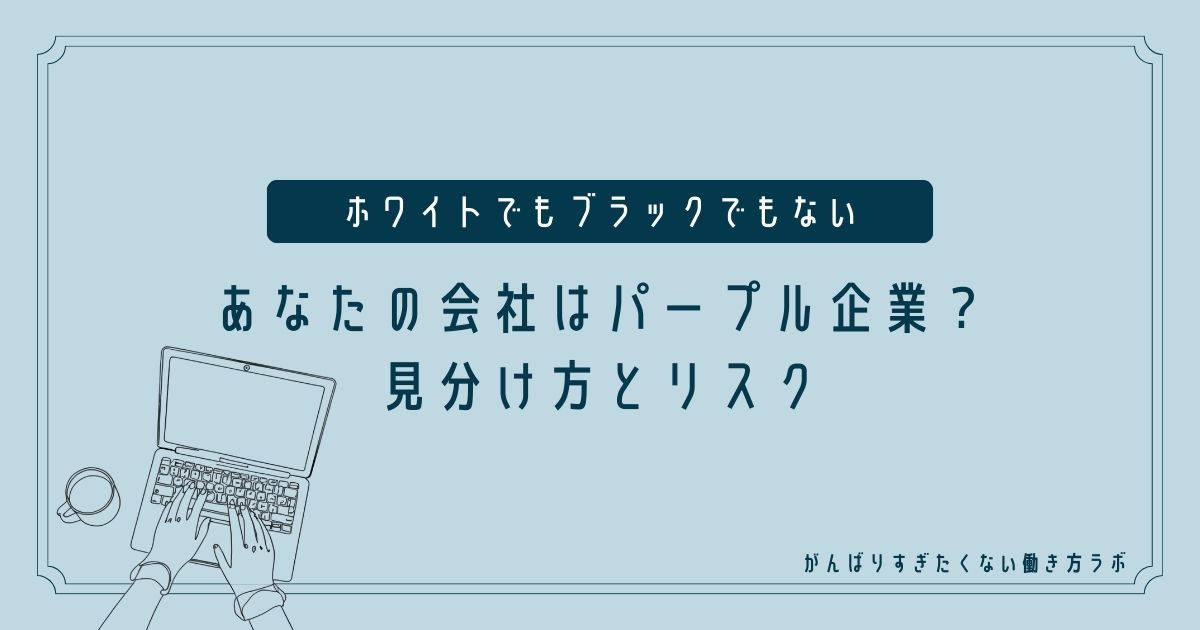
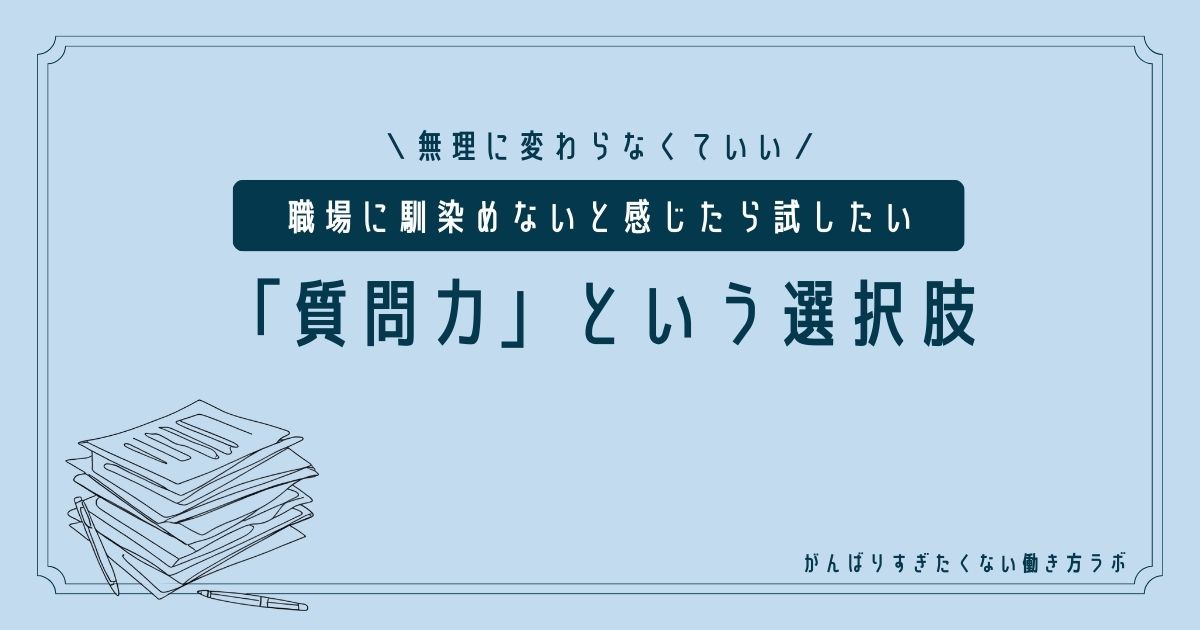
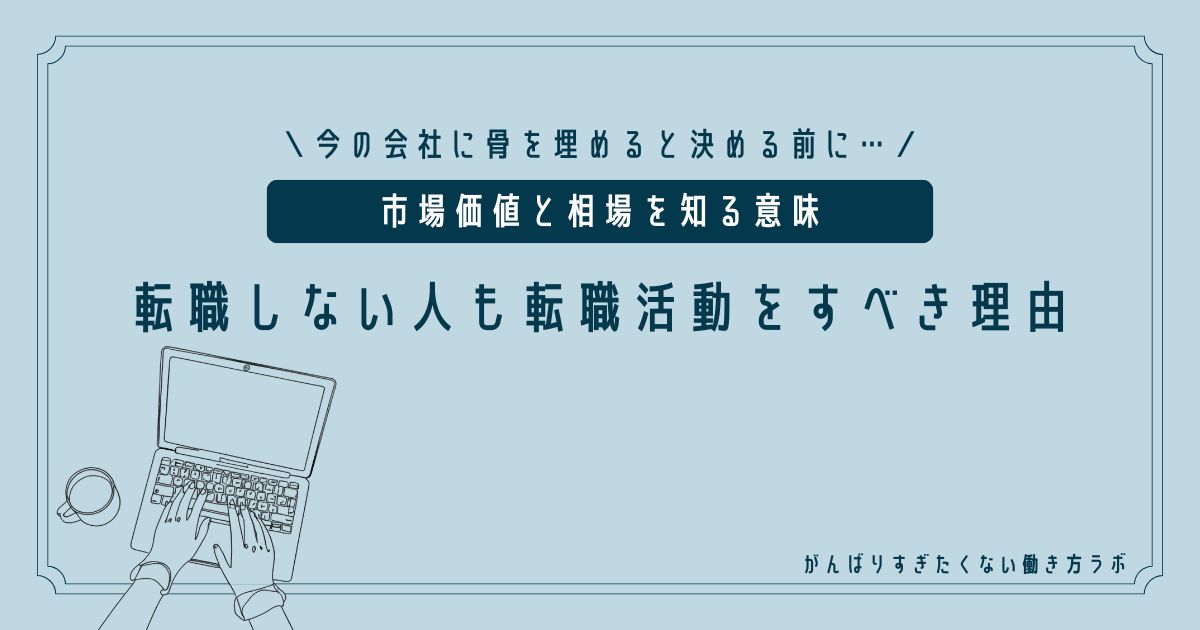
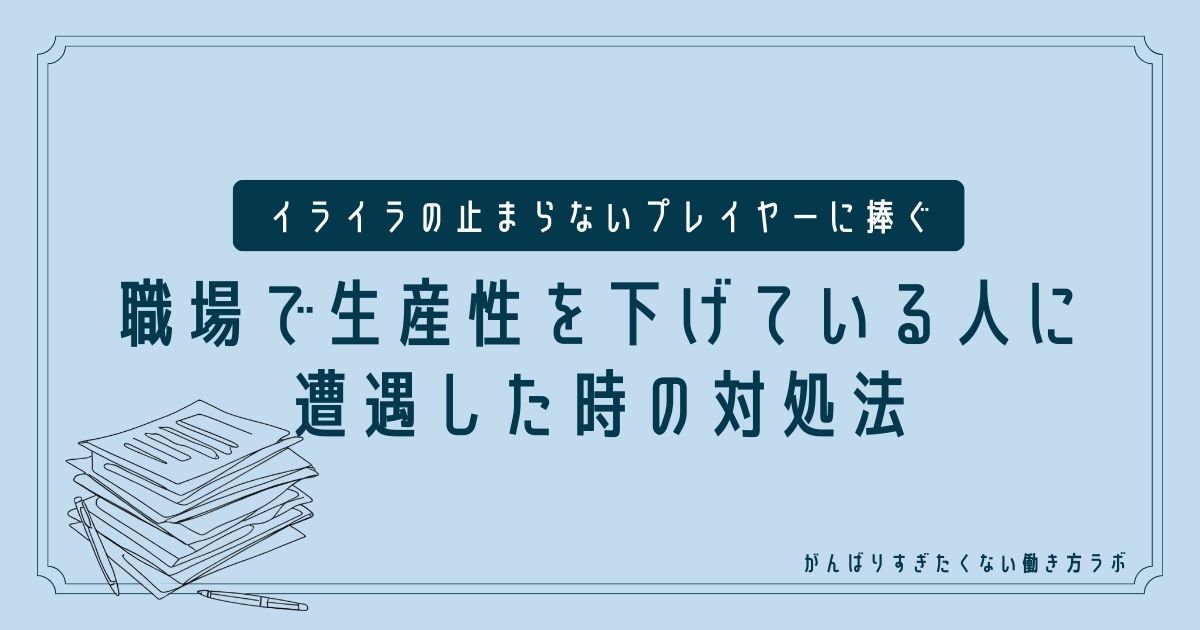
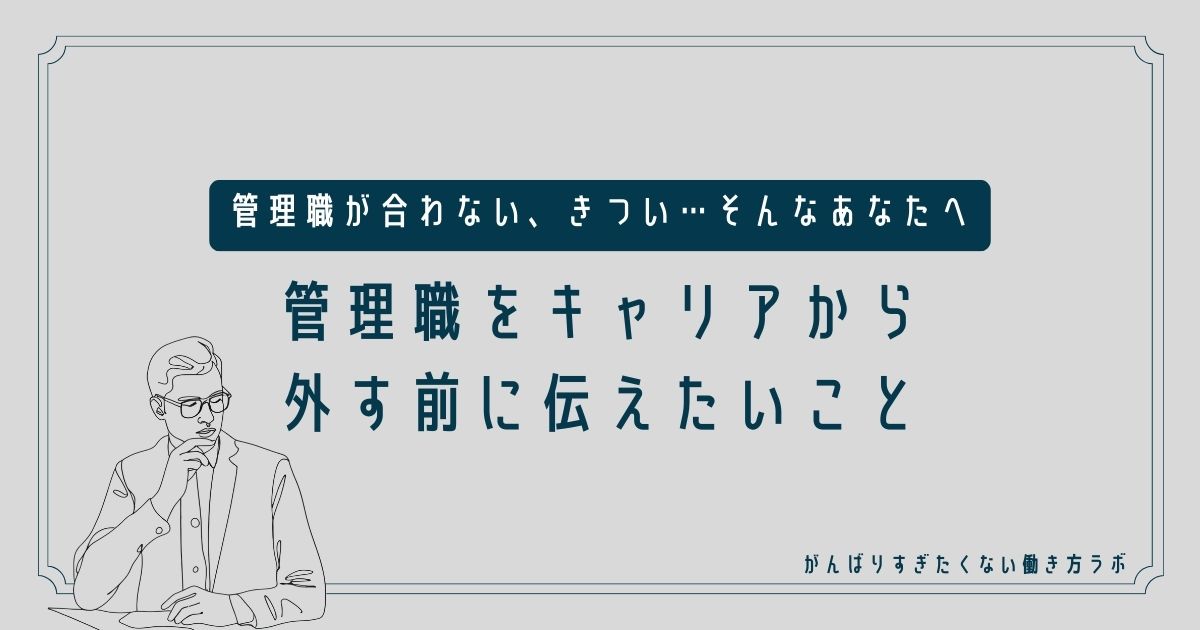
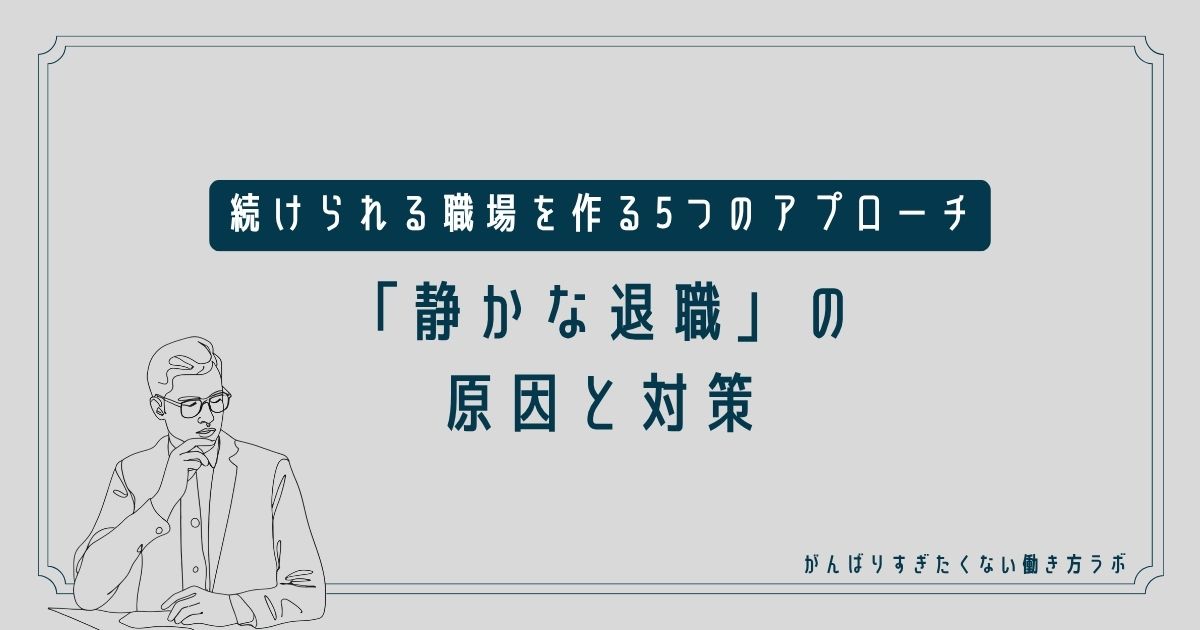
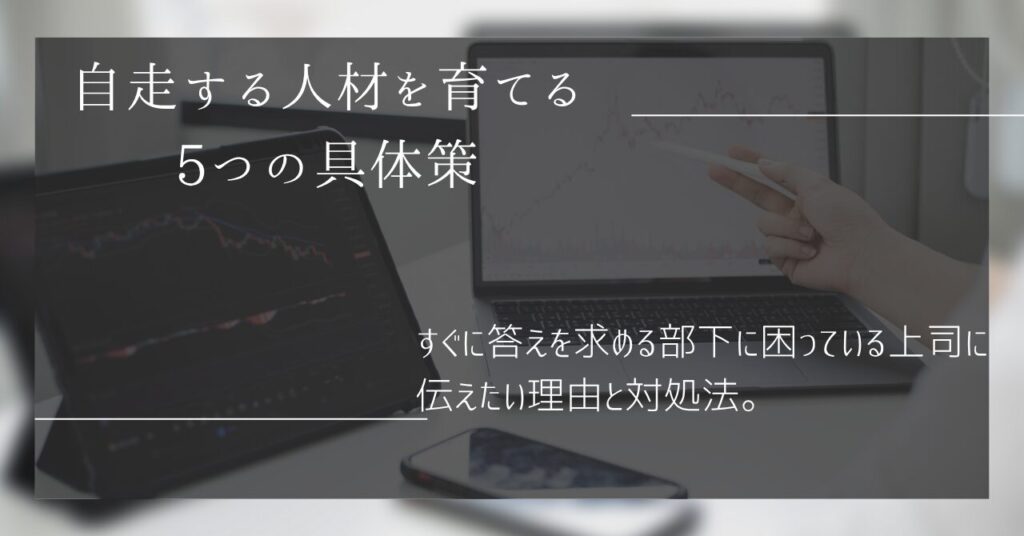
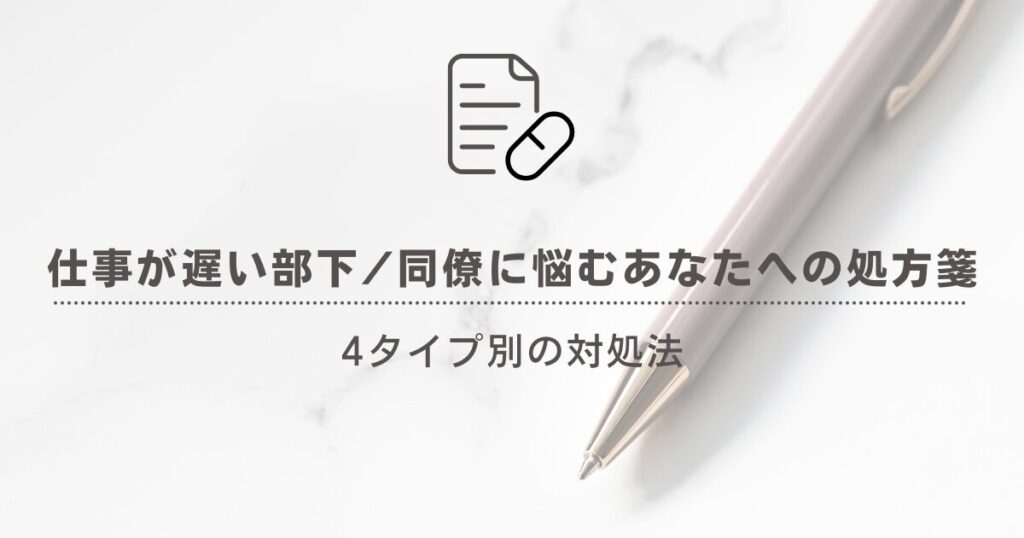
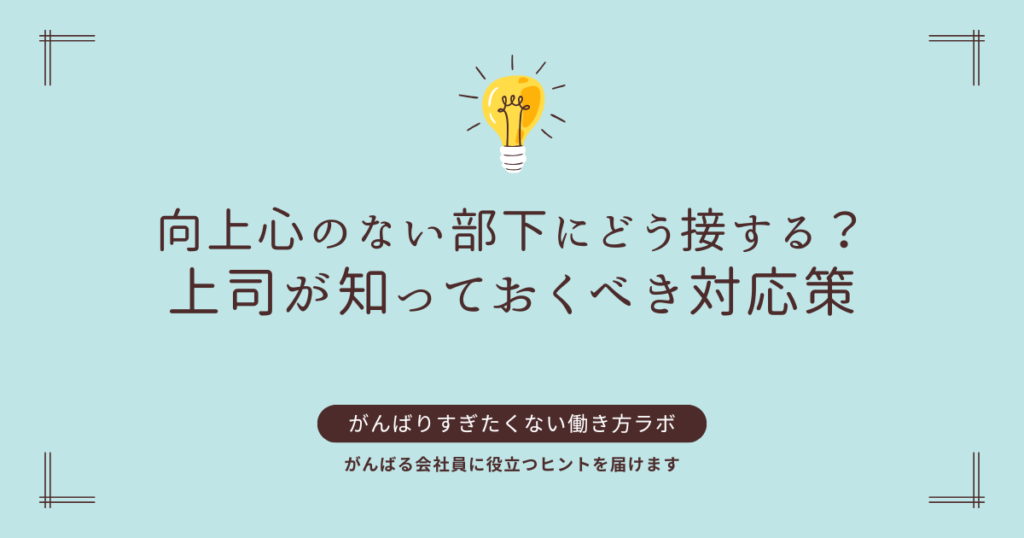
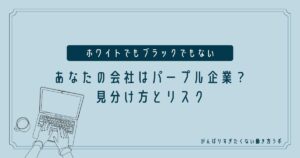
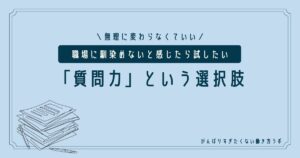
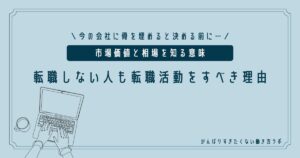
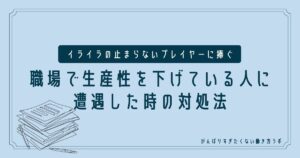
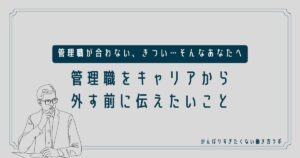
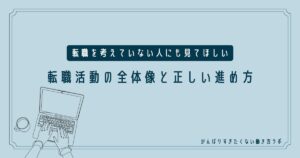
コメント