仕事を終え、家に帰ったら家事と育児。
子どもを寝かせて、ようやくひと息ついたと思ったら、もうヘトヘト。
何かしようと思っても、気づけばスマホをぼんやり見ているだけで、眠りに落ちてしまう──。
そんな「疲れすぎて何もできない夜」を、あなたも何度も過ごしてきたのではないでしょうか。
30代は、仕事で責任が増す一方で、家族や子どもとの時間も大切にしたいという思いが強くなる時期。
そのぶん「休む暇がない」「余裕がない」と感じてしまうのも無理はありません。

でも、本当にこのままでいいのでしょうか?
疲れをそのまま翌日に持ち越してしまうと、心も身体もどんどんすり減っていってしまいます。
大切なのは、「忙しい毎日でも、自分をちゃんと回復させる夜の過ごし方」を見直すこと。
筆者は、30代を会社員として片働きで稼ぎながら、2人の娘の育児と家事を妻と二人でこなして、過ごしました。
この記事ではその経験を活かし、慢性的な疲労に陥りやすい理由を整理しながら、
今日から取り入れられる“夜のリセット習慣”をご紹介します。
まずは、何かを頑張るのではなく、「頑張らずに休む方法」を見つけることから始めてみませんか?
夜にきちんとリセットできると、翌朝の目覚めが変わり、仕事も家族時間も自然と前向きに取り組めるようになります。
家事の外注化については、他の記事でも整理しているので気になる方はこちらの記事も確認してみてください。
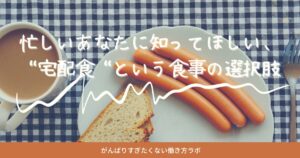
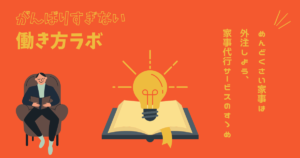
結論:疲れをリセットするために取り入れたい5つの夜習慣

30代の毎日は、とにかく忙しい。仕事に育児、家事、そして時には家族の調整役まで。すべてをこなそうとするうちに、知らず知らずのうちに心も体も限界を迎えてしまいます。
だからこそ、「夜の時間の使い方」がカギになります。
寝る前の数時間をどう過ごすかで、翌朝のコンディションは大きく変わります。
疲れを翌日に持ち越さず、気持ちのよい1日をスタートさせるために、次の5つの「夜のリセット習慣」をおすすめします。
- 早く寝て睡眠時間をしっかりと確保する
毎日十分な睡眠時間を確保しましょう。最も基本で、最も効果的です。 - 就寝前のリラックスルーティン
スマホを手放し、ぬるめのお風呂に入る、照明を落とす、ストレッチをするなど、心身を「おやすみモード」に切り替える時間をつくりましょう。 - 消化にエネルギーを割きすぎない夕食
疲労回復に必要な栄養をしっかりと取りつつ、胃腸に負担をかけない工夫が大切です。 - 30分の運動習慣
ハードな運動は不要です。継続可能な軽度の運動習慣をつけましょう。 - 完璧を手放す、タスクの見直し
やらなくてもいいこと、誰かに頼めることは手放す勇気を。1日の終わりに「やらないことリスト」をつくるのもおすすめです。
この5つです。1つずつ、説明していきます。
1. 早く寝て睡眠時間をしっかりと確保する

疲れがとれる理由
どんな疲労対策よりも根本的かつ確実なのが「睡眠時間の確保」です。
著書「HEALTH RULES 病気のリスクを劇的に下げる健康習慣」の中では、睡眠の重要性、特に睡眠時間について取り上げられており、睡眠時間の不足はパフォーマンスにも影響を与えることが述べられています。
睡眠不足は脳のパフォーマンスに悪影響を与える
引用:「HEALTH RULES 病気のリスクを劇的に下げる健康習慣」 – 津川友介 著- (集英社:2022年) 第1章
睡眠の質を考えるのは、まず7時間の睡眠時間を確保してからの話である。
引用:「HEALTH RULES 病気のリスクを劇的に下げる健康習慣」 – 津川友介 著- (集英社:2022年) 第1章
目覚めのスッキリしない感じは、タイミングの問題ではなく、シンプルに睡眠時間を延ばすことで解決する問題なのだ。
引用:「HEALTH RULES 病気のリスクを劇的に下げる健康習慣」 – 津川友介 著- (集英社:2022年) 第1章
具体的なアクション案
- 必要な睡眠時間と起床時間から、就寝目標時間を逆算してベッドに入る時間をルールとして設定
- 休日の“寝だめ”ではなく、毎日7時間以上の安定した睡眠を重視
- 子どもを寝かしつけたあとに起き直すのをやめて、一緒に寝て朝の時間を有効活用する工夫もあり
わたしの場合は、11時就寝、6時起床です。昔は中々朝活が続かなかったのですが、睡眠への意識を変えてから寝る時間も安定し、朝活を継続できています。
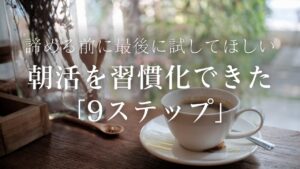
2.就寝前のリラックスルーティン

疲れがとれる理由
そもそも、中々寝付けない。その結果、スマホ弄ってしまったり、家事をしてしまい、睡眠時間が短くなるケースも多いと思います。これは身体が寝る準備を十分にできていないために起こることです。
深部体温が “上がってから下がる” という自然なリズムに合わせると、睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌が高まり入眠がスムーズになります。副交感神経が優位になり、ストレスホルモン(コルチゾール)が低下。結果として脳・筋肉の回復が進みやすい状態で眠りに入れます。
また、リラックスには趣味など自分が楽しめることも有効です。特に、人は「目的のないスクロール」より、自覚的に楽しい行為のほうが副交感神経が優位になり、脳波(α波)が増え、しっかりと休めます。
テレビや流れてくるニュースや動画をみるなどの受動的な過ごし方よりも、読書やオンデマンドのドラマをみるなどの能動的な過ごし方が有効です。
具体的なアクション案
- 38〜40℃の湯船に10〜15分:上がった体温が約1時間で下がるタイミングに就寝を合わせるのが理想。
- ベッドに入る1時間前にはスマホを封印:ブルーライトがメラトニンを抑制するため通知も含め遮断。
- 時間を決めて趣味タイム:ドラマ1話、読書1章、アロマを焚いて瞑想…短時間でも「自分で選んだ時間」が回復スイッチ。受動的な“読む系SNS”は朝に回すなど意図的にダラダラ枠を夜時間から排除。
現在において難しいのはスマホの封印ではないでしょうか?
私もそうでして、ベットでスマホゲームを続けて寝不足…なんというの日も多かったです。
そんな習慣を改善した経験や取り組みを、こちらの記事にまとめているので、苦戦している方は読んでみてください。
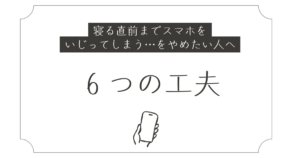
3. 消化にエネルギーを割きすぎない夕食

疲れがとれる理由
眠りと疲労の関連性は前述のとおりですが、就寝直前の高カロリー・高脂質食は、胃腸がフル稼働することで交感神経が優位になり、眠りが浅くなるという悪循環を生みます。
「血糖値スパイク」という単語を聞いたことがある方もいると思いますが、糖質や脂質に偏った食事は血糖値の急上昇を招きます。これにより、夜間に低血糖→中途覚醒し、睡眠が中断されるというリスクもあります。
なによりこんな難しい理屈がなくても、おなか一杯だと眠りにくく、それだけで疲れるというのはイメージできると思います。
具体的なアクション案
- 食事は就寝の2〜3時間前まで/腹八分目を鉄則に
- 仕事が夜遅くまでかかる人は、仕事途中で済ませてしまうのが◎
- 食事の内容自体も影響は大きいですが、ここの見直しはハードルが高いと思うので、まずは量とタイミングからでオッケー。ベッドで胃もたれして眠れない人は、炭水化物の量を減らすことと、油分の少ない食事を心掛けてみて下さい
私も残業が遅くまでかかりそうなときは、19時くらいまでに途中でサッと済ませるようにしています。
物足りない気持ちになることも多いですが、満腹は脳の集中力の低下にもつながるのでここはグッとこらえて、翌日にスイーツでも食べよう…と自分にご褒美をぶら下げて耐えています。
4. 30分の運動習慣

疲れがとれる理由
適度な運動は血流を促進し、疲労物質(乳酸や炎症物質)を流すデトックス効果があります。
また、運動によってセロトニンやエンドルフィンが分泌され、ストレス軽減・睡眠の質の向上にもつながります。
特に在宅勤務や通勤の少ないデスクワークの方は、日々の運動量が絶対的に少ないため、健康面においては少しの運動でも効果的です。
日頃の運動量がゼロの人が少しだけ運動した場合に得られる健康上のメリットが一番大きい
引用:「HEALTH RULES 病気のリスクを劇的に下げる健康習慣」 – 津川友介 著- (集英社:2022年) 第3章
具体的なアクション案
- 毎日合計で40-90分ほどの散歩が理想。とはいえ、難しい方は15分でも実行できれば効果あり
- 帰宅時の通勤で歩く距離を伸ばすなど、「生活に溶け込む運動」で対応できるのが理想
- 小さい子供の面倒みなくてはいけない、夜の散歩は怖い…という方は、ステッパーの導入やYouTubeのフィットネス動画でも◎
わたしは、夜に妻が子供を寝かしつけている時間に、30-40分散歩をしていました。
目標設定をして歩数を記録したり、YouTube動画をラジオがわりにして、インプットの時間にすることで自分のモチベーションを高く継続できました。
めのめmemo
たまにはコンビニで新しいスイーツを買って帰り、パートナーへの感謝を形で示すのも、大事な継続のポイントです。
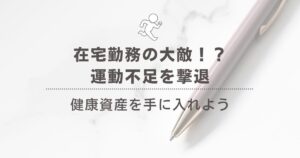
5. 完璧を手放すタスクの見直し

なぜ効く?
認知負荷理論では、「未完了タスク」は脳のワーキングメモリを占有し続け、疲労感を増幅させます。
“やらない”“任せる”を決めることでメモリが解放され、ストレスホルモン減少し、夜のリセット効率がUPします。
簡単にいえば、抱えている未解決の課題ややるべきタスクを頭に残したままだと、それだけで疲れ、睡眠による回復効果にも悪影響があるという話です。
具体的なアクション案
- 終業時に“残タスク”は捨てるか、明日に回すリストとして書き出し、デスクからすぐに見える場所に置く
- 夫婦・パートナーで「洗濯ものを畳んでしまうのは週末まとめて」「アイロンは形状記憶シャツで不要化」など、休日以外はやらないこと、そもそも家庭でやらないことを決めていく
- 家電&外部サービスに投資:乾燥機付き洗濯機・食洗機・家事代行を“時間購入”として捉える。
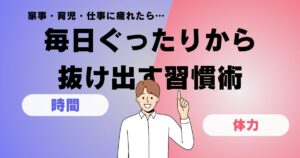
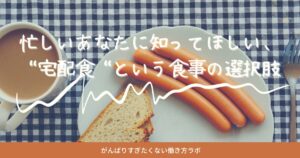
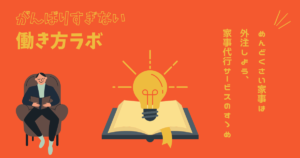
まとめ 〜30代、疲れを溜めない暮らしへ、今日からできること〜

30代は、仕事でも家庭でも責任が重くなる時期。
やりがいも楽しみもあるけれど、がんばりすぎると、心身が悲鳴を上げてしまいます。
疲れが慢性化してしまう前に、夜の「リセット習慣」を整えることが、
毎日を前向きに過ごすためのカギになります。
- 早く寝て睡眠時間をしっかりと確保する
毎日十分な睡眠時間を確保しましょう。最も基本で、最も効果的です。 - 就寝前のリラックスルーティン
スマホを手放し、ぬるめのお風呂に入る、照明を落とす、ストレッチをするなど、心身を「おやすみモード」に切り替える時間をつくりましょう。 - 消化にエネルギーを割きすぎない夕食
疲労回復に必要な栄養をしっかりと取りつつ、胃腸に負担をかけない工夫が大切です。 - 30分の運動習慣
ハードな運動は不要です。継続可能な軽度の運動習慣をつけましょう。 - 完璧を手放す、タスクの見直し
やらなくてもいいこと、誰かに頼めることは手放す勇気を。1日の終わりに「やらないことリスト」をつくるのもおすすめです。
この5つの習慣は、どれも特別なことではなく、生活に自然と組み込めるものばかり。
小さな見直しが、翌朝のスッキリ感と生活の質を大きく変えてくれます。
とれない疲れをとるために、まずは「無意識の時間」を観察してみよう
「でも、そんな余裕ないよ……」という気持ちも、すごくよくわかります。
だからこそ、まずは“ムダに疲れている時間”がどこかを見つけることから始めてみませんか?
おすすめの一歩
- 帰宅後の1時間、自分が何をしているかをざっくり書き出してみる
- 「なんとなくスマホを見ている時間」や「意味もなく起きてる時間」がないかチェックする
- その中から、5分でも10分でも“休むことに使える時間”を探してみる
何かを「増やす」のではなく、すでにある生活の中から“整える”だけでOKです。
最初は週に1回でも、1つの習慣だけでも大丈夫。
夜にちゃんとリセットできれば、朝の自分が変わり、
結果的に仕事も家庭も、そして自分の時間も、もっとラクに回るようになります。
日々溜まる疲れと向き合い、笑える毎日にしよう
「疲れすぎて何もできない」毎日から、
「ちょっと休めて、ちょっと笑える」毎日へ。
今日から、あなたらしい“夜の習慣”を、ひとつ見つけてみてください。
本記事は以下の資料を参照しています。
津川友介 著 『HEALTH RULES 病気のリスクを劇的に下げる健康習慣』 (集英社)
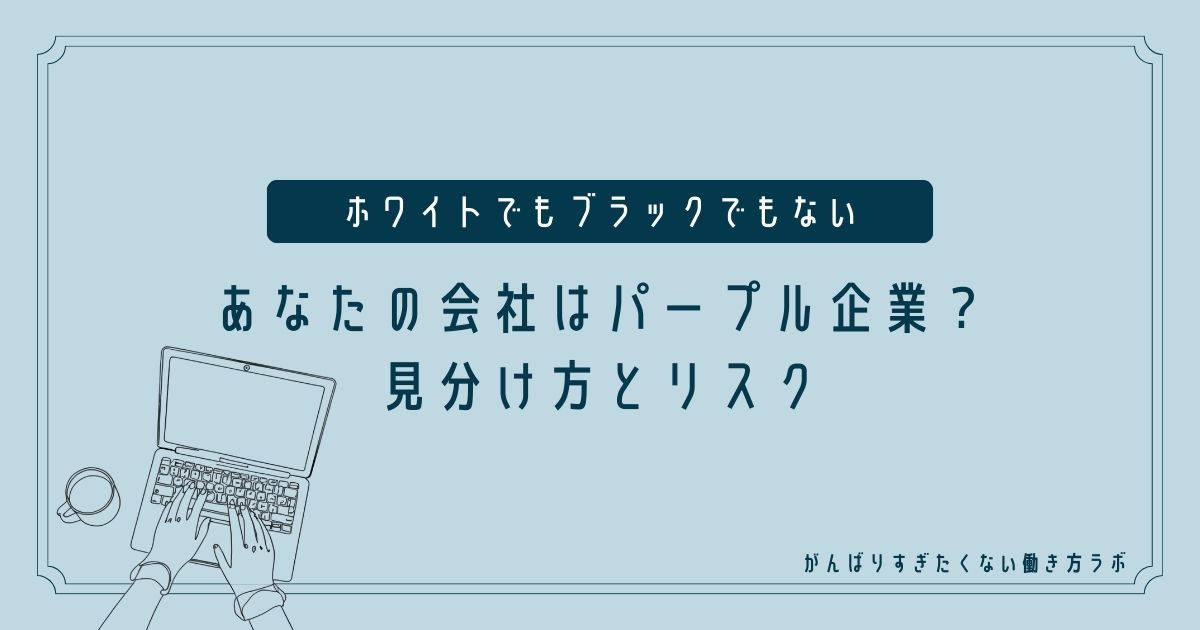
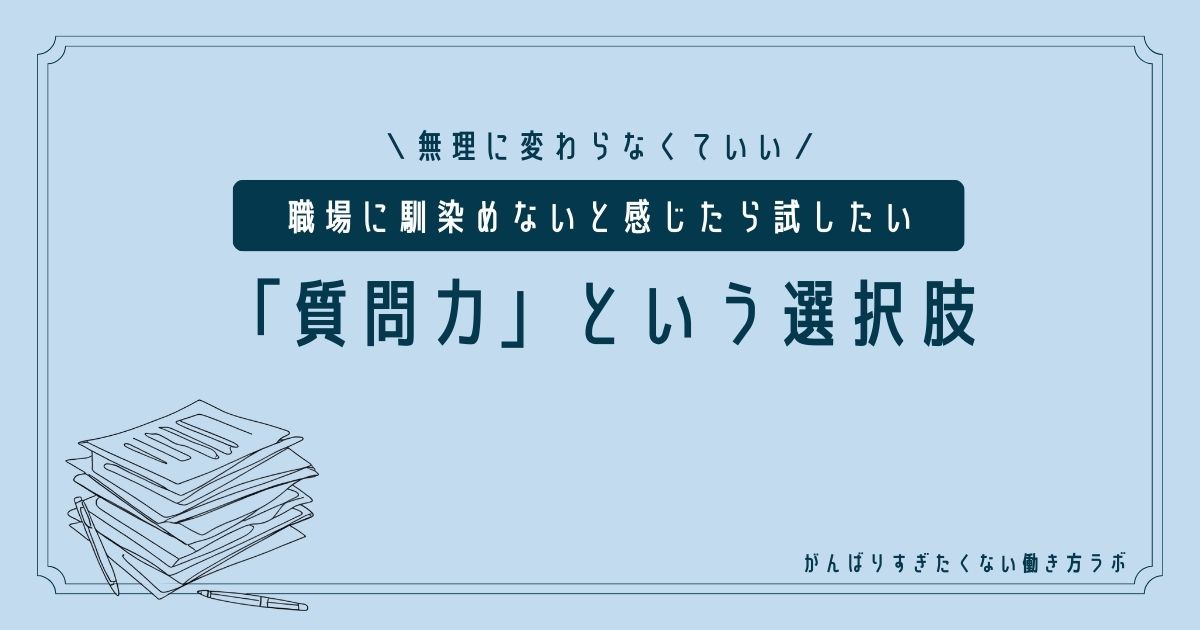
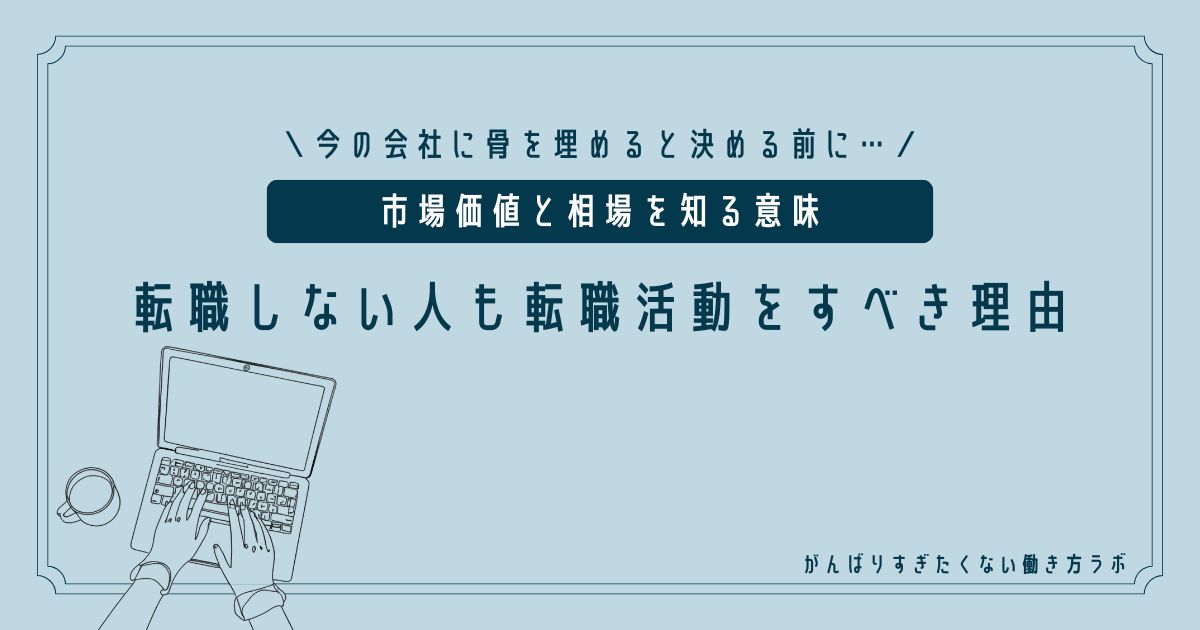
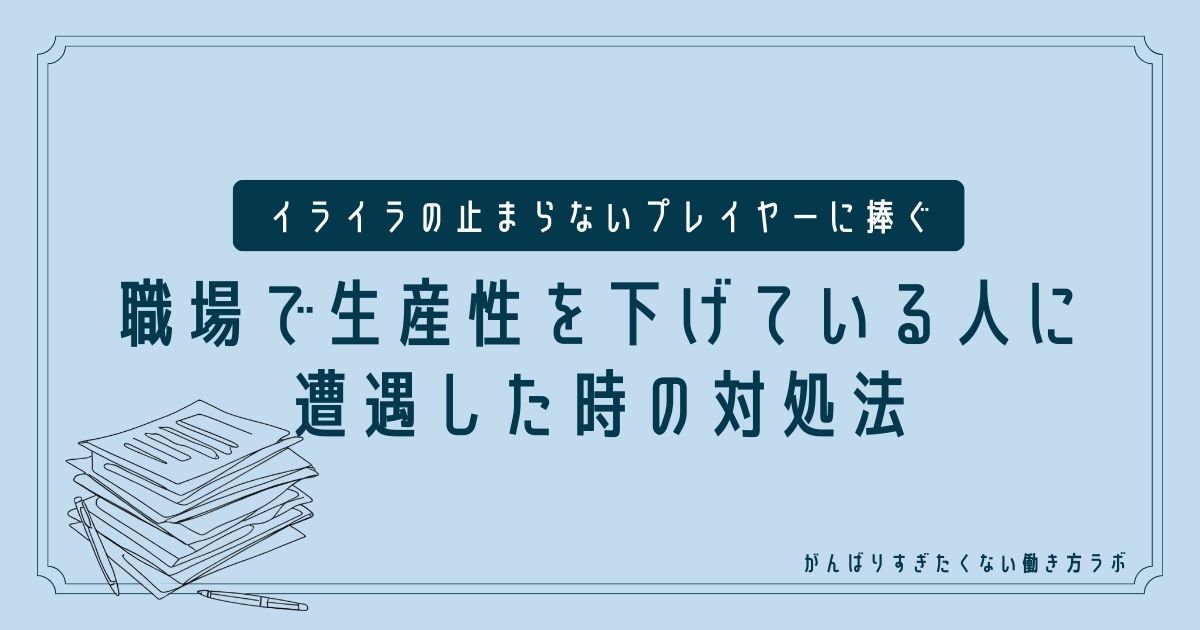
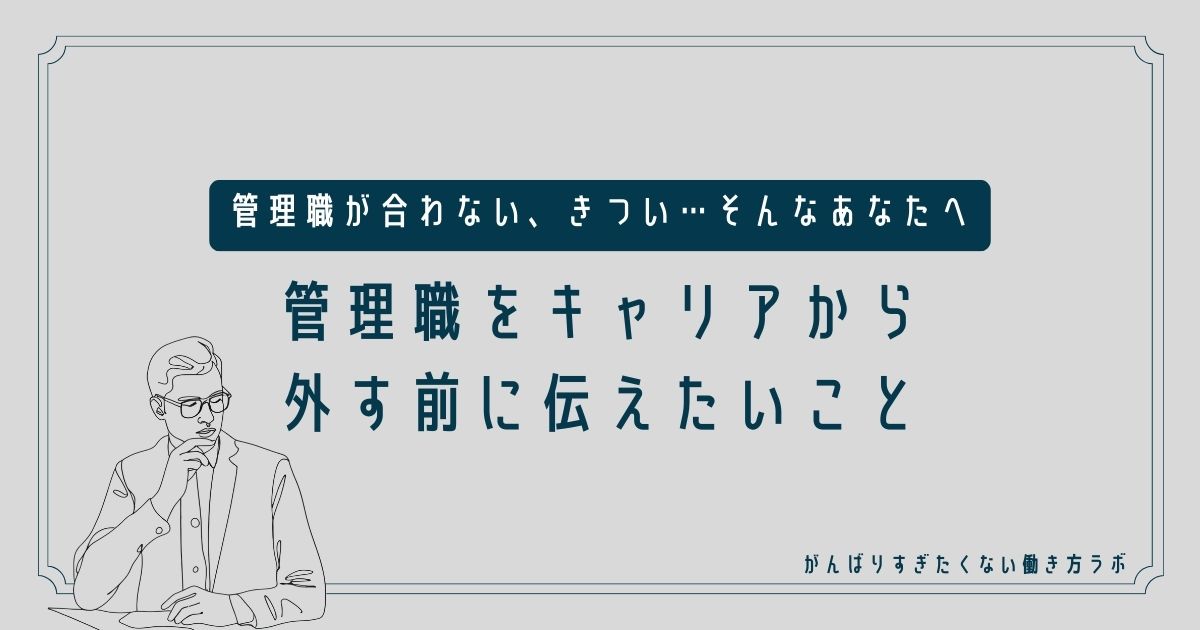
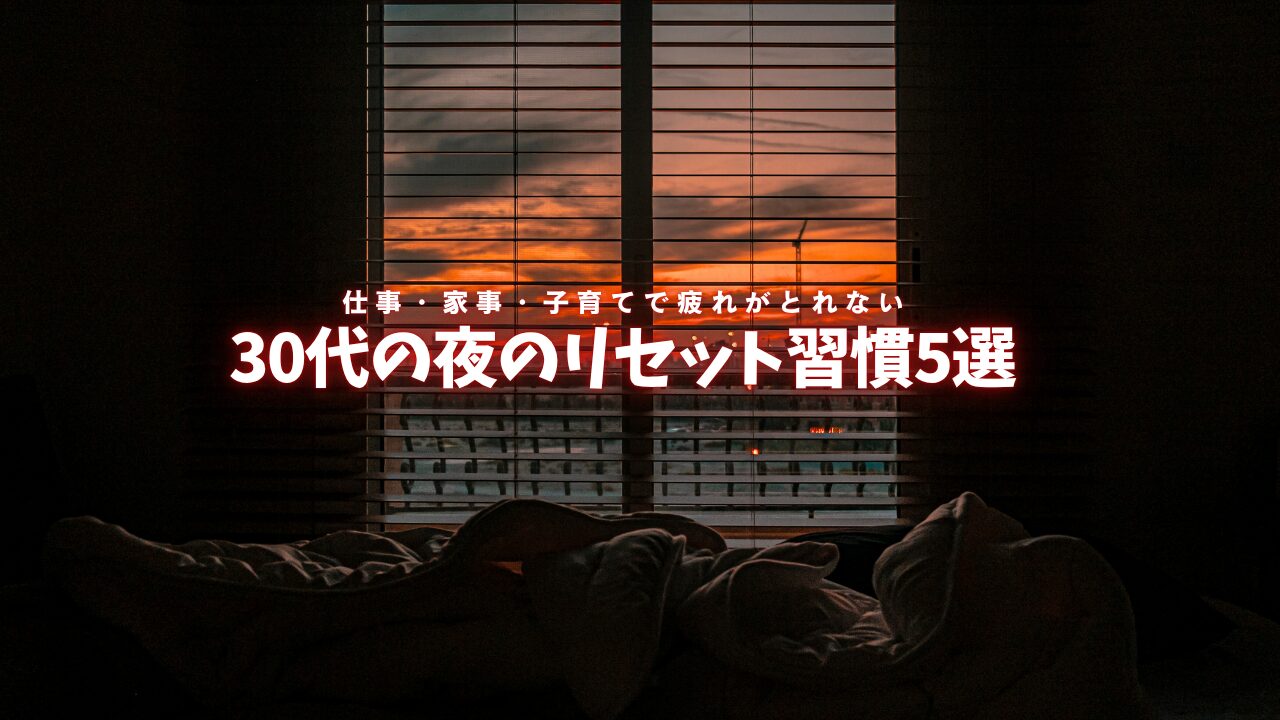
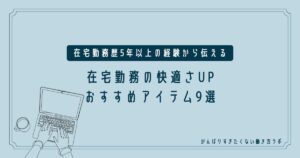

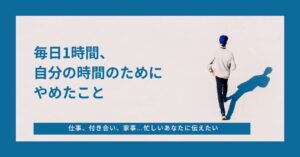

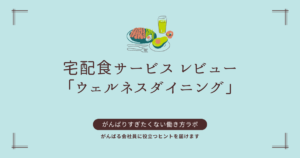

コメント