
あの先輩、どうしてあんなに仕事が早いんだろう?



同じ仕事量なのに、同期はなぜあんなに余裕があるんだろう?



上司は抱えている仕事が多いのに、どうやって新しい仕事を受けている?
忙しく働く20〜30代なら、一度はそんな疑問を持ったことがあるはずです。
でも実際に近くで見ても、経験を積んでいくことによる慣れだけでは、説明できない“速さ”があります。


私は会社員歴15年以上、現在10名以上の部下を持つ現役マネージャーとして、
数多くの「仕事が早い人」と一緒に働いてきました。
そこで共通項として見えてきたのは、才能ある人が無意識に行っている4つの習慣です。
本記事では、仕事が早い人に共通する
「走り出しが早い」「判断が早い」「周囲を頼る力」「プランBを備える」
という4つの視点を解説していきます。
この記事を読めば、
- 「仕事が早い」と評価される人の考え方と行動パターン
- 明日から取り入れられる具体的な3つのアクション
- 若手が陥りやすい罠
がわかります。
結論を先に言えば、速さ自体の本質は特別な才能ではなく、習慣と工夫で再現できる積み重ね。
今日からでも“仕事が早い人”に近づくことは十分可能です。
この記事を読んで、是非ステップアップのヒントを掴んでください。
走り出しが早い|準備の差がスピードを生む


「指示が出た瞬間にすぐ動き出す人」と「そこから準備を始める人」では、結果に大きな差が生まれます。
仕事が早い人は、指示を待たずに未来の自分の仕事をイメージして準備しています。
必要な情報を整理し、下調べを済ませているからこそ、いざ指示が出た瞬間に動けるのです。
あなたがスタートの合図がでたと認知したタイミングで、既に相手は走り出して随分先を走っているので、
ゴールまでの時間に差が出るのは自然ですよね。
ポイントは現在の状況や仕事のプロセスを意識し、“未来の仕事”を常にイメージすること。
次に来そうな依頼や会議の流れを予想し、関連情報を集めておく。
資料フォーマットを先に整える、関係者のスケジュールを把握しておくなど、下準備が「初動の速さ」に直結します。



私は、過去実行したプロジェクトは1枚のスライドに特徴を整理しています。顧客やビジネスパートナーなど、自分や組織の事例を紹介したい場合にスピーディに情報提供できるようにしています。
重要なのは、これはルール違反のフライングではなく、段取りだという点。
ビジネスにおいては、スポーツ競技のように「スタート前に動くのはズルい」と思う必要はありません。
むしろ、事前に準備しておくことで、指示を受けた瞬間に適切な質問や条件の交渉ができ、
結果としてチーム全体のスピードアップにつながります。
今日からできる一歩
- 毎朝5分、「来週以降に自分がやることになりそうな仕事」を1つ書き出す
その仕事に必要な資料や連絡先を、メモでも良いのでまとめておく - 一緒に働く上司や先輩が急に1週間不在になったときに仕事にどんな影響がでそうかを書き出す
影響を最小化するために、自分が今できそうなことを書き出してみる
書き出したもののうち、目先の仕事にも活きそうなものから取り組めないか検討してみる - 自分がスピーカーになる会議や打合せの前日に、想定問答を3つは準備する



「走り出しの速さ=未来を読む力」。
指示を待つのではなく、次の一手を描くことが“早い人”への第一歩です。
判断が早い|優先順位の迷いを捨てる


「やるべきことは分かっているのに、どれから着手すればいいか迷ってしまう」
この迷いの時間こそが、仕事のスピードを削ぐ最大の要因です。
仕事が早い人は、判断にかける時間と労力を最小限にしているのが特徴です。
その背景には、常に優先順位を明確にしている習慣があります。
重要度と緊急度を瞬時に見極め、「今やるべきか、後でいいか」を即断する。
その結果、突発的な依頼や想定外の課題が発生しても、ほとんど迷いません。



優先順位が明確な人は、仕事への交渉力も強くなります。
無茶な期限が迫られる依頼にも、対応が難しいことをロジカルに説明できます。受ける場合も、代わりに今もっている仕事の期限の調整や、巻き取ってもらうことを調整できるのです。
判断を早めるために必要なのは、複雑な理論ではありません。
「この仕事を今やらないと何が起きるか?」
「誰に影響が出るか?」
この2つの問いを自分に投げるだけで、自然と優先度は見えてきます。
さらに、あらかじめ「やらないことリスト」を持っておくのも効果的。
自分にとって成果につながらない作業を明確にしておくと、
迷いを一段と減らせます。



「判断」はとても脳のパワーを使う作業で、繰り返すことで生産性が低下していきます。「判断」にかける労力や回数を最小化することは、日々の生産性の維持にも繋がるのです。
今日からできる一歩
- 毎朝、タスクを「重要×緊急」の4象限に分けてメモする
- 週末に「やらないことリスト」を3つだけ書き出しておく
- 迷ったときは「これをやらないと何が起きるか?」を自問する



「速さは決断から生まれる」。
優先順位を即断できるシンプルな思考こそ、迷わない働き方の鍵です。
これができている人は、恒常的な残業もしていません。
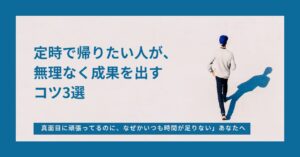
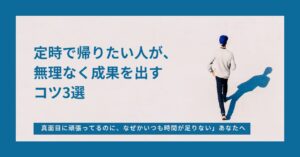
周囲の力に頼れる|70%完成で出す勇気





中途半端なものを出して、指摘を受けたくない──



完璧に仕上がってからでないと人に見せられない──
そんな気持ちが、自分の成長を遅らせているかもしれません。
仕事でも副業でも、70%の完成度で一度外に出すことで、他者の力を借りながら質を高める方が結果的に早く、
学びも深まります。
自分一人で作業していると、視点が固定されてしまいがちです。
第三者に見てもらえば、「伝わりづらい部分」や「改善の余地」に早く気づけます。



例えばブログ記事でも、構成や表現のクセは自分では気づきにくいもの。70%と言わず構成案の段階に生成AIや他の人の意見をもらうことで、早い段階から軌道修正が可能になります。
完成品を一度に出して「良し悪し」を評価されるよりも、途中段階でフィードバックを受ける方が、
修正スピードは格段に早くなります。
さらに、他者の視点は自分の引き出しを増やす学びの機会。
自分では選ばない表現や発想に触れることが、次のアウトプットの質を確実に押し上げます。
「失敗したくない」「粗が見えるのが恥ずかしい」という気持ちは誰にでもあります。
ですが、多くの場合、周囲はあなたの「完璧さ」よりも価値ある内容や成長する姿勢に注目しています。
未完成を恐れずに出し、フィードバックを謙虚かつ真摯に受け止める姿が、信頼獲得につながるのです。
今日からできる一歩
- 全体像が見える段階で一旦止めて共有する。
そもそも全体像が描けない場合は気付いた段階て、進め方を相談する。 - もらった意見は「自分への批判」ではなく「アウトプットへの改善機会」と捉える。
取捨選択しながらスピード感を持ってすぐ反映する。 - 「全体の構成が伝わるか見てほしい」など、目的やフィードバックしてほしいポイントを明確にして、
確認者や上司に依頼する。



未完成のまま出す勇気は、成長を加速させる強力な武器です。
「まず出して、周囲を巻き込んで磨き上げる」――この発想ができれば、自分一人で抱え込むよりも、ずっと軽やかに前へ進めるはずです。
プランBを常備|想定外を“当たり前”にする
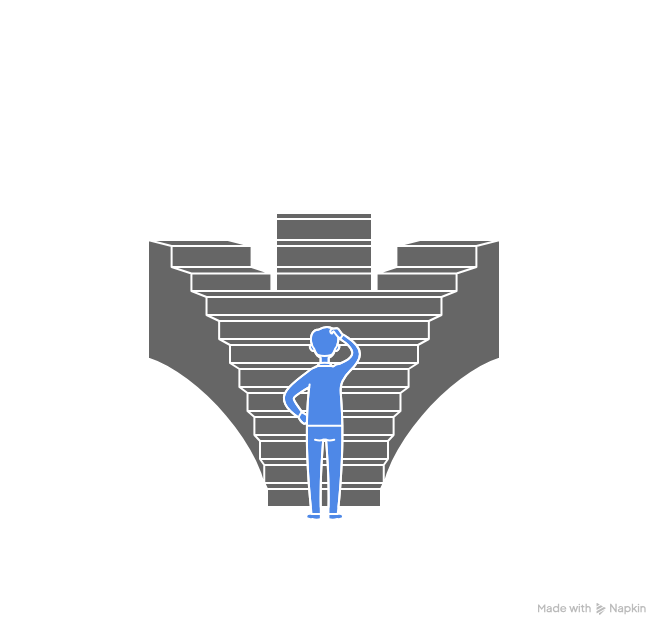
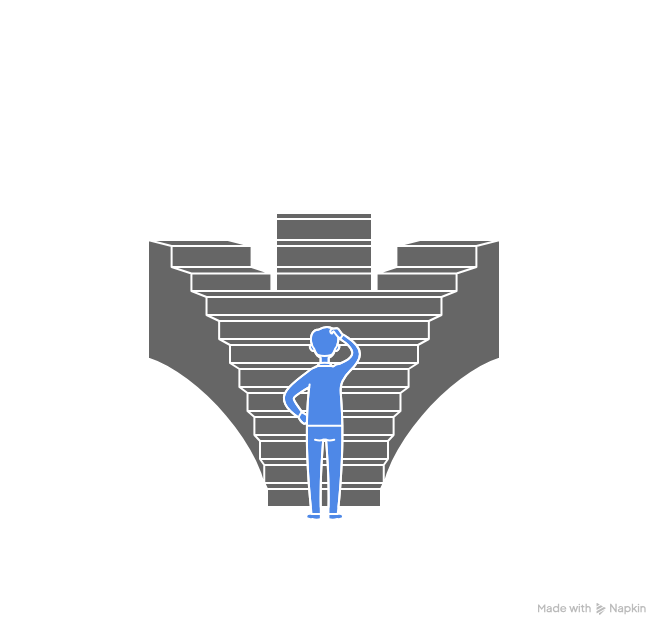
おそらく共感いただけると思うのですが、仕事では「計画どおりに進む」ことの方が稀です。
だからこそ想定外を“当たり前”と捉え、次の一手=プランBを常に描いておく人は、結果的に仕事が早くなります。
会議資料の差し替え、急な仕様変更、上司の優先順位変更…。
どんな現場にも予期せぬ事態は発生します。
「前提として想定外は起きるもの」という意識を持つだけで、心構えが変わります。
驚きや焦りで立ち止まる時間を減らせるのです。


計画はあくまで進行の目安であり、変化に適応し目的達成するための物差しです。
初期計画に固執するほど、変更に対して後手に回ります。
プランBを常に準備する人は、状況に合わせて“軌道修正”を前提に行動しています。
プランBは単なる頭の中の想像ではなく、具体的な行動レベルで準備しておくことが大切です。
- 主要メンバーが急に休んだら誰に代替を依頼するか
- 資料が完成しなければどこまでを暫定で出すか
- 納期が前倒しになった場合の優先順位はどれか
こうした「小さなもしも」を積み重ねることで、危機に直面しても即座に手が打てます。
想定外を前提に行動し、常にプランBを描くことで、仕事の早い人は変化に強くスピードも落ちないのです。
今日からできる一歩
- 1日5分のシミュレーション:業務開始前に「今日起こり得る想定外」を3つ書き出す。
- 記録を残してアップデート:起きたトラブルと対応策をメモし、次のプランBの精度を高める。
- 代替ルートを1つ用意:会議資料・外出先・移動手段など、最低1つは代案を。



「想定外=失敗」ではありません。むしろ、想定外を前提に動くことで変化に強い柔軟さを身につけられます。その柔軟さこそが、周囲から「仕事が早い」と評価される大きな理由になります。
若手が陥りやすい3つの罠
4つの習慣は「誰でも実践できる」とはいえ、
頭ではわかっていても、マインドの壁や誤解でつまずくケースは少なくありません。
ここでは、若手社員が特に陥りやすい3つの罠を紹介します。
1. 完璧主義|100%仕上げないと出せない


完璧や指摘されない成果を求めるあまり、いつまでも共有や相談ができないのは悪手です。
- 自分だけで抱え込む
- 上司やチームに共有が遅れる
- 方向修正のチャンスと時間を失う
結果的に手戻りが増え、完成までの時間が長くなります。
質も結果的に高めきれないケースの方が多いでしょう。
70%で出す=早めにフィードバックを得て、品質を上げる戦略と理解しましょう。
2. 確認不足|“走り出し”を誤解する


先回りして準備することは大切ですが、
正式なゴールや優先順位を確認せずに突っ走るのは逆効果です。
方向違いの資料を作り込んでしまえば、
むしろ修正に時間を奪われます。
走り出す前には目的や前提条件、成果物のイメージを短く共有する一手間を忘れないようにしてください。
3. 報連相の遅れ|コミュニケーション不足


仕事が早い人ほど、進捗の小まめな共有を欠かしません。
動き出してから「結果だけ伝えればいい」と思い込み、報連相を後回しにすると、
「上司や関係者がフォローできない」といったリスクが高まります。
速さ=孤独なスピード勝負ではないことを忘れないでください。



別記事では、「仕事が遅い」と言われたときに見直すべきポイントを、特徴別に整理しているので、中々改善できない方はこちらも参考にしてみてください。
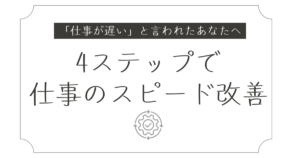
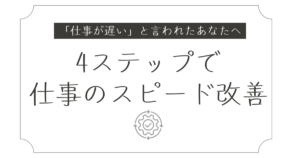
仕事の速度は再現可能なスキル


今回は仕事が早い人に共通する4つの視点を紹介しました。
- 走り出しが早い ― 指示を待たず、未来の自分の仕事をイメージして準備する
- 判断が早い ― 優先順位を即断し、迷いを最小化する
- 周囲の力に頼れる ― 70%完成で一度出し、フィードバックを活用する
- 常にプランBを描く ― 想定外を前提に行動し、柔軟に軌道修正する
仕事の速さは「手際の良さ」だけではありません。
日々の小さな準備、判断、周囲とのやり取り、そして変化への対応力、それらの継続が評価される速さを作ります。
最初から全てを実行する必要はありません。
あなたが取り組みやすいものから始め、積み重ねていくことが「仕事の速さ」の土台になっていきます。
「速さ」は特別な才能ではなく、習慣と工夫ので再現可能なスキルです。
今日からの一歩が、あなたの働き方を変えていきます。
この記事が、あなたが「仕事の早い人間」と評価されるための一歩になれば嬉しいです。
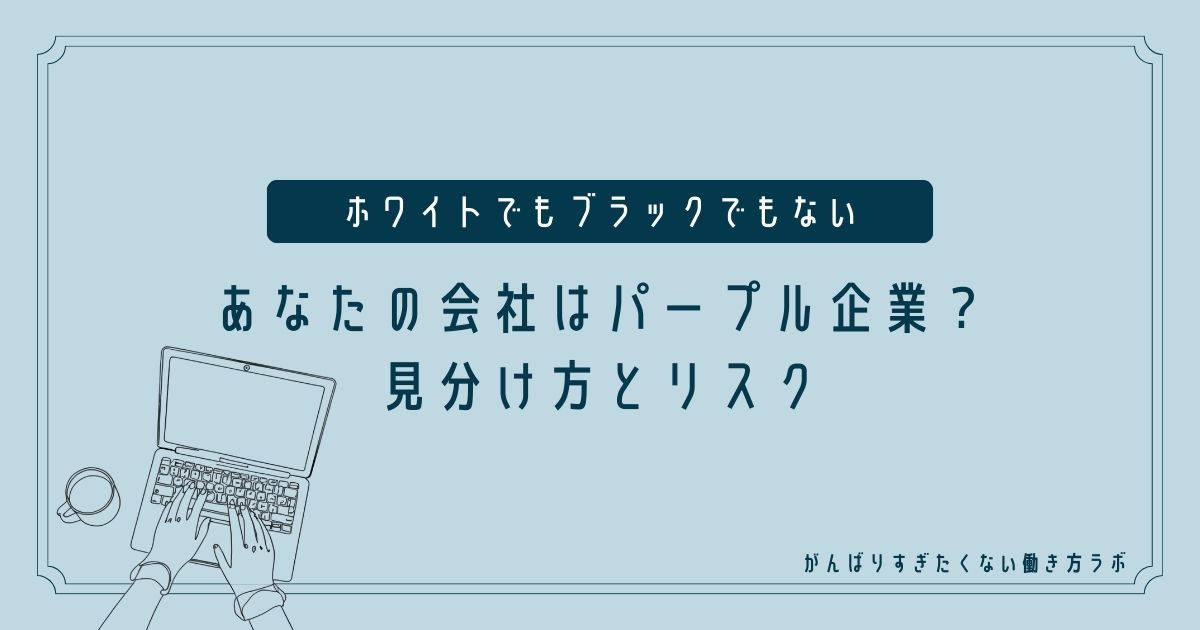
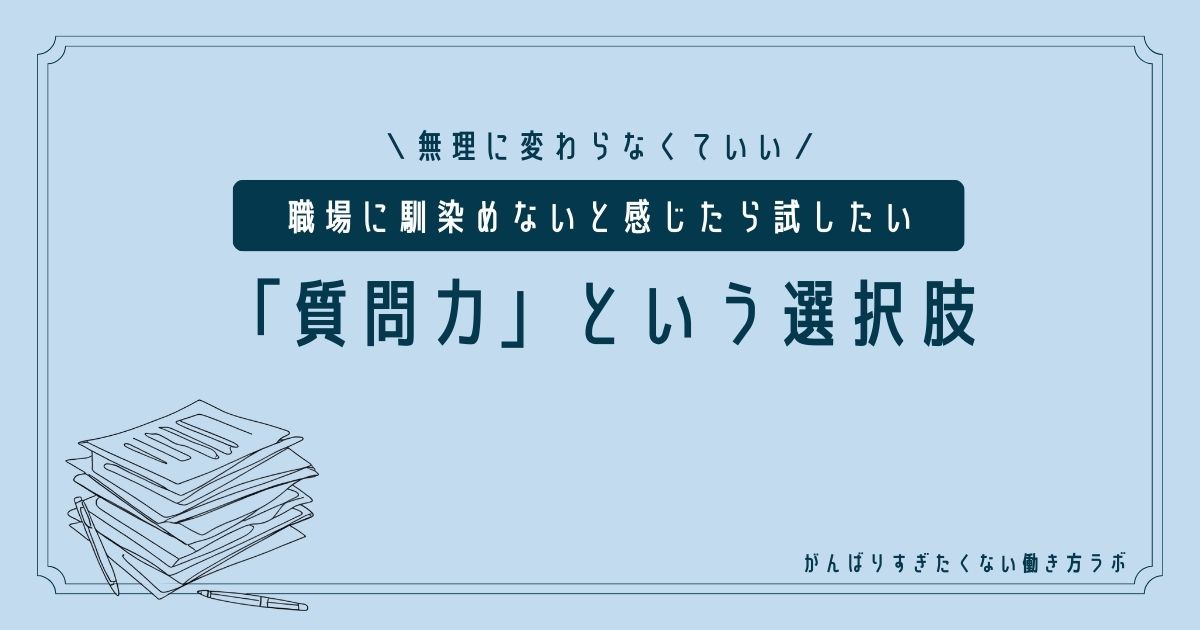
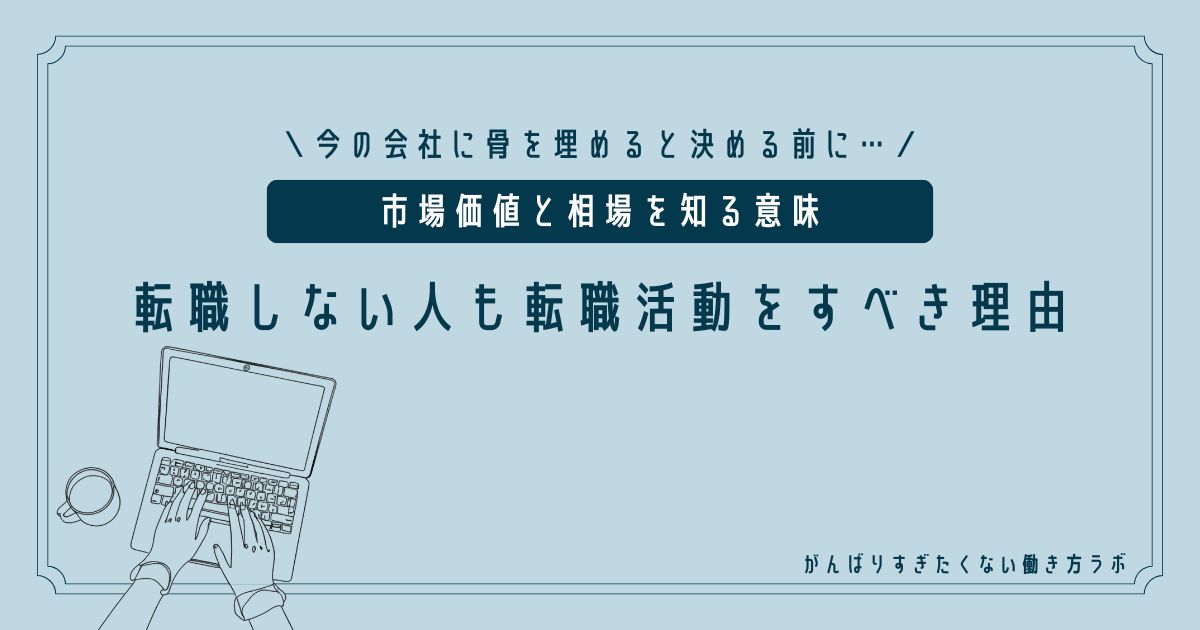
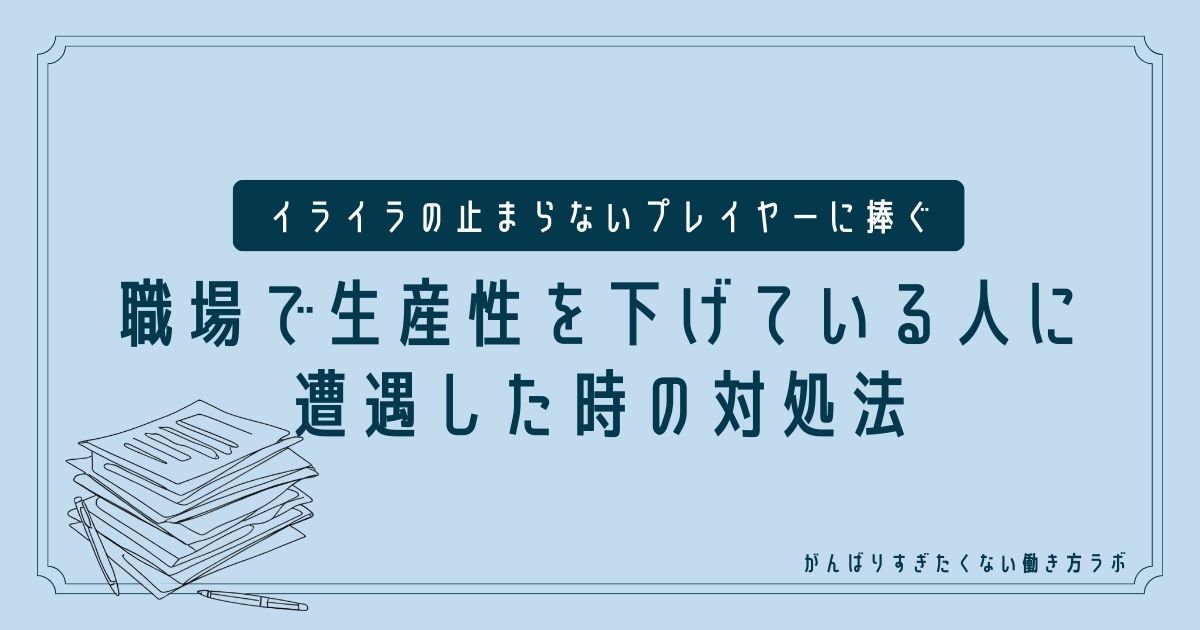
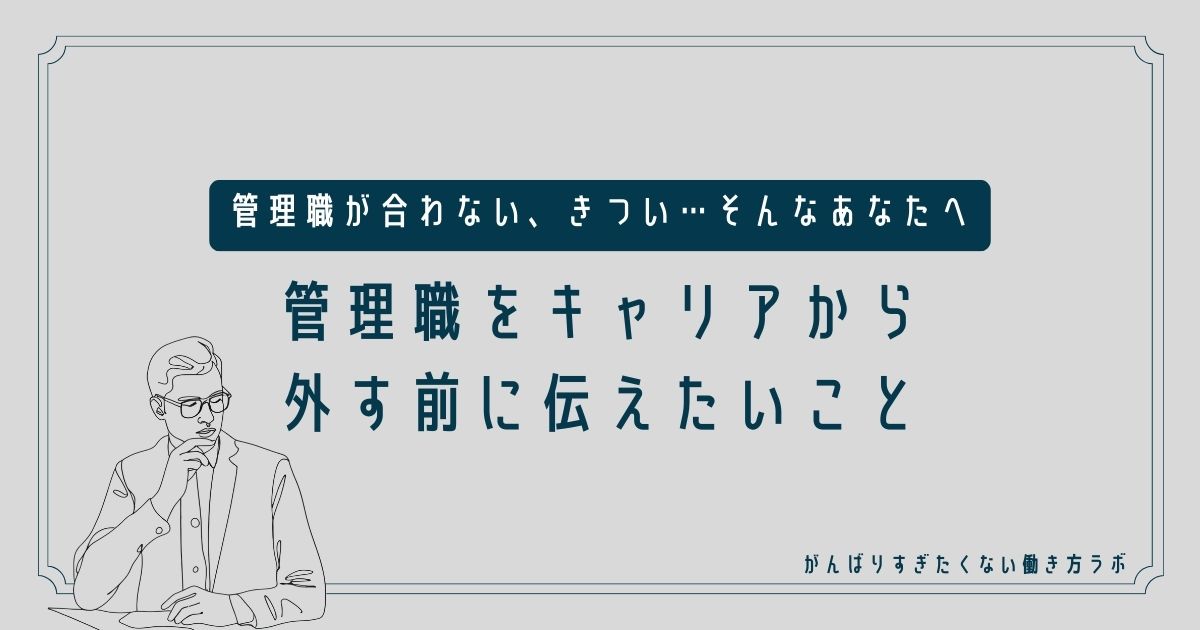
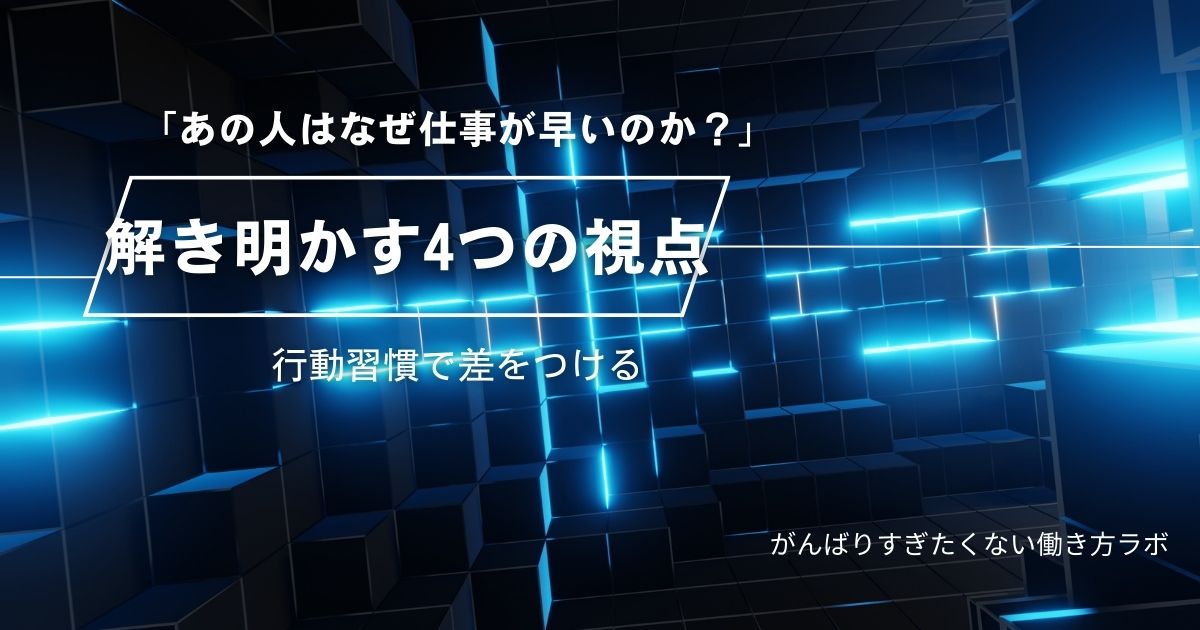
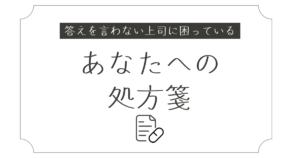
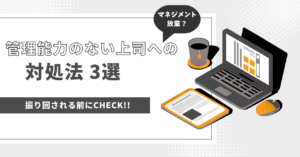
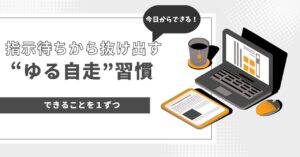
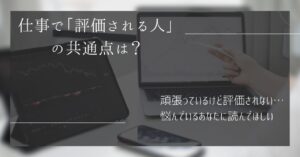
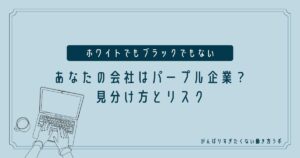
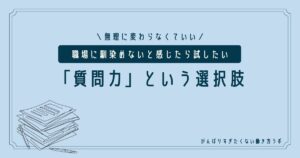
コメント