真面目に働いているのに、なぜか全然評価されない…
私のが頑張っているのに、他の人の方が評価されているのはなぜ?

そんなモヤモヤを抱えていませんか?
仕事に手を抜いているわけでもない。毎日遅くまで残業し、誰よりも真面目にタスクをこなしている。
それなのに、なぜか上司からは評価されず、周囲の“頑張っていないように見える人”ばかりが昇進していく──。
もしかするとあなたは、「努力の方向性」を間違えているのかもしれません。
この記事では、会社員歴15年以上で現役で10名の部下を持つ管理職の筆者が、
「評価されない人の特徴」と「評価される人がやっていることの違い」、さらに「社内昇進を実現するための具体的な戦略」までを徹底解説します。
努力の方向性を見直し、がんばりすぎずに評価されるキャリアへとシフトしましょう。
努力は量より質~評価される努力とは?

社内での昇進とキャリア形成は、個人の努力だけでなく、組織の評価制度が複雑に絡み合うプロセスです。
がむしゃらに頑張るだけでは、必ずしも評価につながりません。実際、働き方改革が進む今、「効率的に成果を出す人」や「周囲を巻き込める人」が高く評価される傾向にあります。
つまり、求められるのは「どれだけ頑張ったか」ではなく、「会社の評価軸にそった行動」ができているかどうか。
評価されるためには、まず努力の質=方向性を見直すことが重要です。
自身が属する組織の人事評価制度を深く理解し、評価されるべきポイントに焦点を当てて成果を出す、マイナス評価されるような行動を控える…それだけで努力の量をこれ以上増やさなくても今より評価を上げられます。
評価されない方向性

- 会社の人事評価とのズレ
→ 会社が求める人材像や職位にあった成果や行動と、自分の努力がかみ合っていない - 成果が見えづらい(可視化不足)
→ 頑張っていても、上司がその努力や成果を把握していない - 自己完結型の仕事スタイル
→ 周囲を巻き込まず、地味に仕事をこなして終わってしまう - 人間関係に消極的
→ いわゆる「報連相」が弱く、信頼関係を築けていない
わたしの会社でも、本人は頑張っているのに上司に見てくれておらず、評価されないと感じる人はいます。
つまり、正当に評価されるには、努力の方向性に加えて、“見せ方”も重要なのです。
「頑張らなくても評価される人」の共通点

一方で、あまり残業していないように見える人や、淡々と仕事をこなしているように見える人が評価される人もいます。わたしの経験上、このようなタイプいくつかの共通点があります。
会社の求める人材像にあっている
- 成果重視の会社であれば、会社の重要視している「数字」や「インパクト」を出すことに注力している
- プロセス重視の会社であれば、成果だけなく根拠や再現性をアピールしたり、新規事業へのチャレンジや、社内にノウハウ共有など、企業文化に沿ったアクションを行っている
- 評価されるポイントに集中して無駄なく働いているので、周囲からは頑張る量が少ないように見える
コミュニケーションが上手
- 報連相や巻き込み力があり、上司やチームに信頼されている
- 期待値のコントロールが得意
- 共感力や汲み取り力があり、話す相手からの印象が良い
- 成果や取り組みのアピールが上手
主体的に動いている
- 指示待ちではなく、自ら課題を見つけて提案・改善している
- 新しいチャレンジの機会があれば積極的に挑戦している
- 自分の意見を持ち、発信・表明している
自分の強みを理解し、無理してない
- 得意で勝負して“成果を出せる領域”に集中している
- 苦手を自分で補うより、苦手との付き合い方を身に付けている
- 自分のモチベーションのコントロール方法を理解し、実践している
つまり、あなたから「頑張っていないように見える人」は、努力の“見せ方”と“注ぎどころ”が上手いのです。
社内昇進のための戦略と行動

努力しても報われないと感じているなら、闇雲に働くのではなく、「戦略的に努力する」ことが重要です。ここでは、昇進を目指す上で押さえるべき戦略を6つにまとめました。
評価基準の把握と逆算思考

一番重要なのは、あなたの会社の評価制度を確認し、「次の昇進に必要なスキル・成果」を明確にすることです。
評価が公開されていなかったり、抽象的な内容しかない場合は、上司に直接確認しましょう。
どのように確認するかは、会社の文化や上司との関係性にもよりますが、わたしの経験上では定期的な評価をフィードバックする場の質疑応答、1on1がおススメです。
周囲の話を聞くと、懇親会の場で確認している方も多いので、あなたの状況に合った方法で確認してみてください。
めのめが上司に聞いたケース(評価面談)
 上司
上司以上が今期評価のフィードバックです。何か質問はありますか?



今回の評価するときに、わたしに「もっとこうあってほしい」「ここが足りてない」と思った点はありますか?



そうですね。来年度の計画はよいですが、3-5年先まで見据えて、目先のアクションも計画できるとより安心して大きな役割を任せれます。
めのめが聞かれたケース(1on1)



今日はなんのテーマで話そうか?



現在の職位で評価される方法を知りたいです



OK。評価指標は公開されているし、直属上司からフィードバックもされてると思うけど、具体的に何が分からないの?



目先何をすれば評価アップにつながるか分からなくて、具体的には…
ここまで情報整理しても具体的な取り組みがイメージしにくい場合は、先輩や過去の昇進者などより自分に近い「先行く先輩」に相談したり、話を聞いてみてください。
先輩たちの行動から自分とのギャップ分析し、何が足りないかを逆算しましょう。
アピールの習慣化


成果や努力は、「見える化」してこそ評価されます。
会社の制度で評価する仕組みに沿って、正しくアピールすることが最も重要ですが、ほとんどの会社では上司など普段一緒に働く人間の評価を重要視することが多いです。
そのため、日報・会議・普段の何気ないコミュニケーションを通じて、こまめに報告・提案・自分の考えていることを発信し、信頼と認知が得ることが重要です。
日本人には「自分をアピールするのは苦手」という意識を持つ人が少なくありません。
しかし、自分の成果や考えを上司に伝え、フィードバックを受けることは、単なる自己主張ではなく、組織との方向性をすり合わせるための建設的な行動です。
会社への貢献を高めるうえでも重要なプロセスなので、捉え方をチェンジし前向きにアクションしていきましょう。
社内ネットワーク戦略


昇進や高評価を目指すうえで、直属の上司だけでなく、他部署のリーダーや経営層とも信頼関係を築くことが非常に重要です。
なぜなら、キーパーソンとの接点が増えることで、あなたの存在や実力が認知され、機会や抜擢のチャンスが広がるからです。
また、社内ネットワークを意識的に広げていくと、業務に有益な情報が自然と集まるようになり、協力を得やすくなるなど、目に見えにくい“サポート”が増えていきます。


さらに、上司の目標達成をサポートする姿勢も、評価に直結しやすい要素のひとつです。チーム全体の成果を底上げする行動を通じて、あなた自身の影響力も高まり、職位を超えた信頼を得ることができます。
いわゆる「社内政治」は、一般的にはネガティブな印象を持たれがちですが、実際には「利害関係者との調整を通じて、仕事を円滑に進めるための戦略的行動」です。
特に縦割り構造の強い企業では、部署を横断した連携や、斜めのつながりを活かした情報共有が、組織運営の隙間を埋める重要な役割を果たします。
このような行動は、単なる調整力ではなく、「組織貢献」としてしっかり評価される要素となり得ます。
成果を生む“選択と集中”
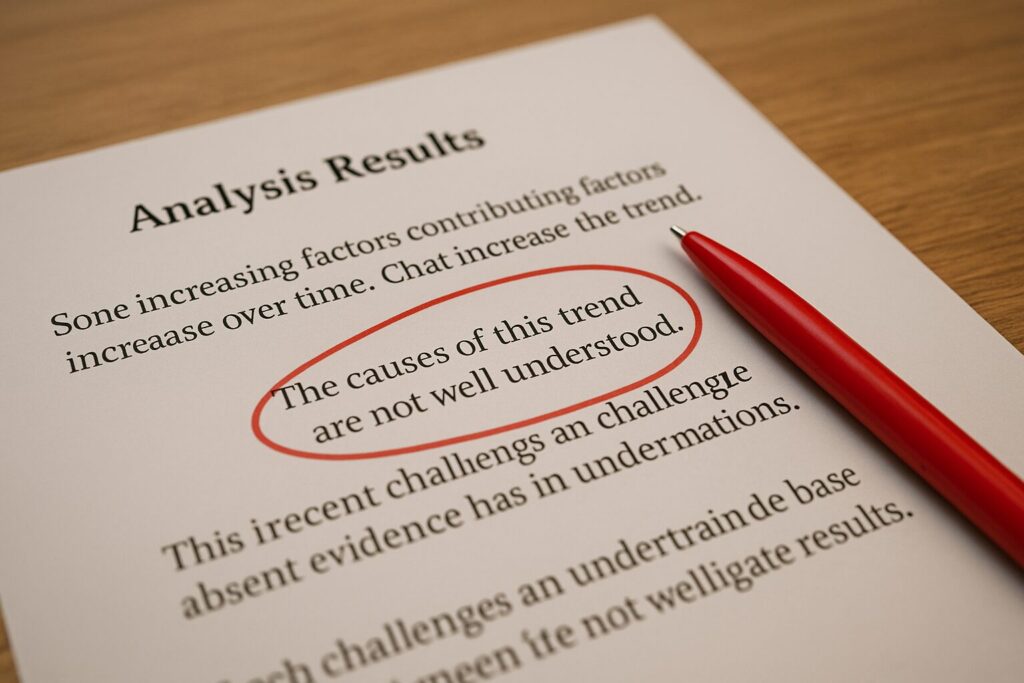
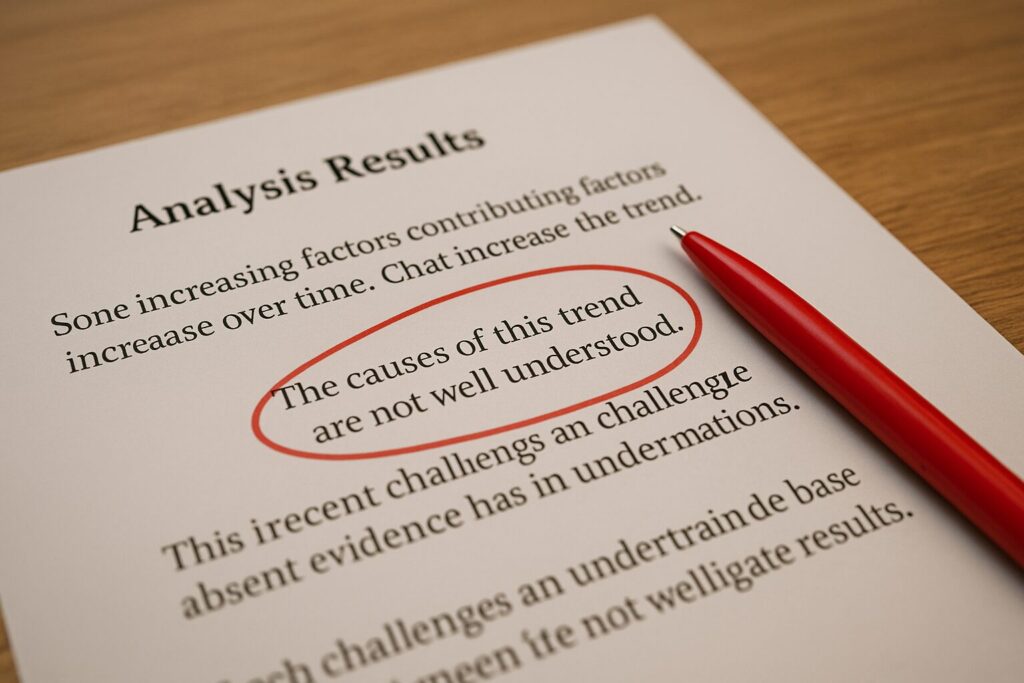
社内で評価される人に限らず、成果を出し続ける人は、例外なく自分自身を深く理解して行動に反映しています。
まずは、自分の強みと弱みを客観的に把握することが出発点です。自分は得意なことに注力し、苦手な領域は外注したり、チームで補い合うといった選択が可能になります。
「自分が成果を出しやすい分野」に集中しましょう。重要な業務や課題解決のような“評価されやすい仕事”を選ぶことも一つの戦略です。


また、自分を理解することで、モチベーションの源泉も明確になります。これにより、継続的に成果を出していく過程における努力や学習も苦になりにくくなり、キャリア形成における安定した推進力となります。
自己理解をベースに、心身の状態を整え、得意領域の重要な業務や課題解決を選択して集中する。
この地道な積み重ねこそが、確実な評価とキャリアの加速を支える土台となるのです。
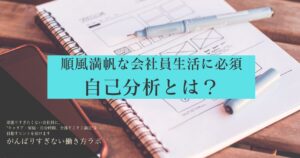
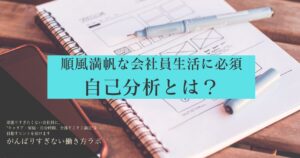


1つ上の視点で行動する


昇進を目指すなら、今の自分の評価基準だけでなく、ひとつ上の職位で求められる成果や能力を理解し、それを先取りして行動することが重要です。
そのためには、上司や先輩に話を聞いて「何が求められているのか」を具体的に把握したり、社内の評価シートや職務定義書などを分析して、上位職の期待値を見える化することが効果的です。
また、日々の業務の中でも、「上司のさらに上」への視点を意識することがポイントです。上司がどのように上層部へ報告・説明しているのかを理解し、その中でどんな情報が必要とされているのかを先回りして考えることで、あなたの行動が直接、上司の評価や成果に貢献する形になります。


具体的に非管理職の会社員で「視座が高い」と評価されそうな行動をピックアップしてみました。
- チームの課題を洗い出し、改善策を提案・実行する
- 会議ファシリテーションや後輩指導など、リーダーシップを発揮する場面を担う
- 部署間の連携や調整など、視野を広げた行動を取る
- 上司との会話で、将来戦略や事業の見通しなどの意見や考えを投げかけてくる
こうした行動を通じて、「すでに次の職位の仕事をこなしている人」として認識されれば、昇進のスピードも一気に早まります。
上司が“次に何を期待しているのか”を察知し、期待以上の成果で応える。その積み重ねが、評価と信頼の大きな差となって現れてきます。
マイナス評価を作らない
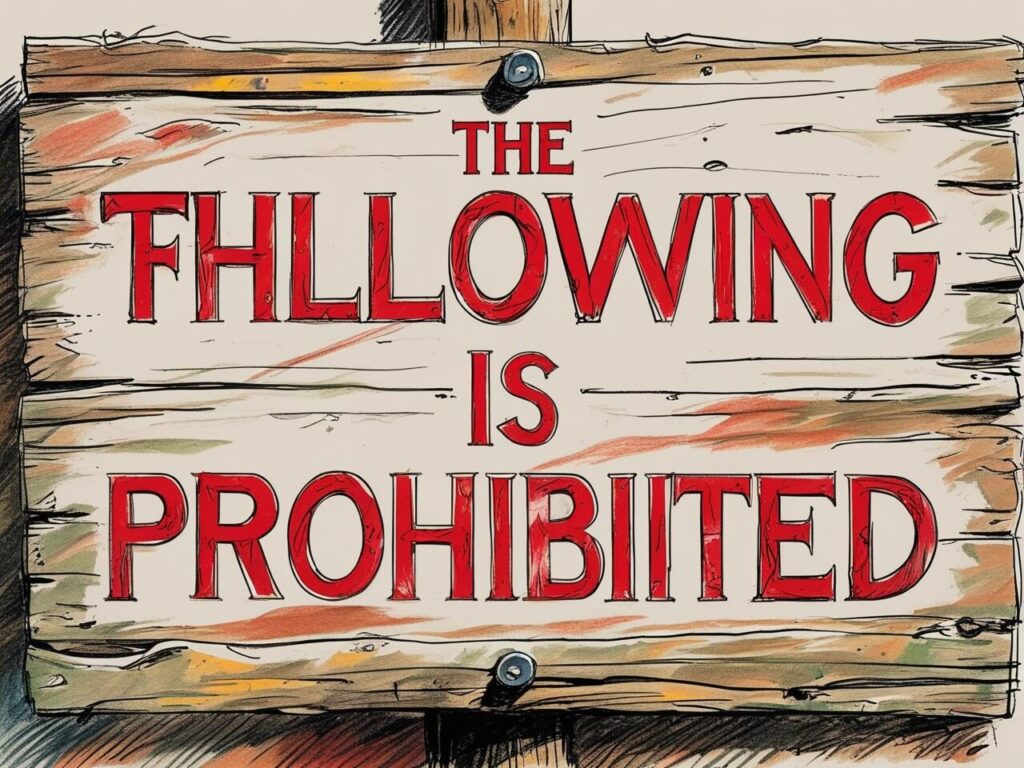
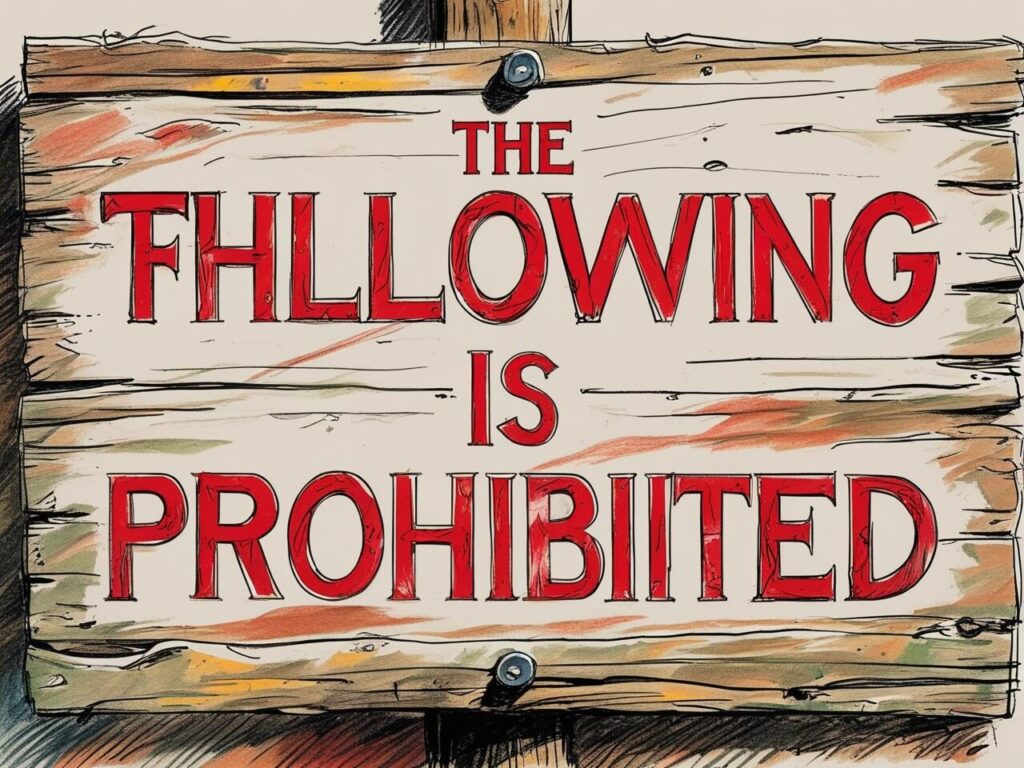
忘れがちですが、会社員の評価としては大きなマイナスを残さないことも同じくらい重要です。
特に多くの日本企業では、加点主義よりも減点主義が強く働く傾向があるため、評価されにくくなる「NG行動」を避ける意識が求められます。
たとえば、ハラスメントや不祥事などのコンプライアンス違反は言うまでもなく、
「仕事上の致命的なミス」や「軽率な発言」、「悪口・不満の漏洩」といった行為も、信頼や評価を大きく損なう要因となります。
特に同僚間では休憩中や社内チャットで、うっかり悪口や不平不満を共有してしまうことがあります。
しかし、この手の内容はいつ漏れているか分からないものです。マイナスを作りたくない人は意識的に避けましょう。


めのめMEMO
評価を考える上で、忘れてはいけないのが、評価をするのは人間であり、人間は本質的に論理ではなく感情で判断する生き物だということです。
つまり、少なくとも定量的な評価がフラットな2人に対し、上司が評価の上下をつける必要がある場合は印象が良い部下をより高い評価にします。仮に成果や能力が全く同じであってもです。
おそらく、わたしも同じ状況に置かれれば、そのような評価を下すでしょう。
会社組織の中において、評価を念頭に置くのであれば、良い人間関係を築くことは重要なのです。
逆に言えば、自分が良い人間関係を築けると感じられる会社に身を置くことは、もっと重要だと言えます。
【補足】一般的な評価制度の仕組み


制度を把握することで、「何をすれば評価されるか」が明確になり、努力の方向性がブレにくくなります。
評価されないと感じている場合、「そもそも自分は何を基準に評価されているのか?」を理解していないことが原因であることも多いです。会社によって評価制度は異なるため、会社の制度を確認したり、上司に直接確認することが重要です。
参考に、一般的に評価の判断に利用される要素を紹介します。
| 評価方法 | 具体的な評価点 |
|---|---|
| 業績評価 | 数字や目標に対する達成度(売上、KPI、利益率、成果物の納品など) 企業の業種によって評価の重みが異なる |
| 行動評価 | 日々の勤務態度、チームへの貢献度、仕事への取り組み方 評価者の主観が入るため、コミュニケーションや報連相の影響が大きい |
| コンピテンシー評価 | 将来的な活躍可能性、論理的思考、リーダーシップ、主体性など 主に将来や別の現場でも、再現性高く成果をだせそうかを能力で評価 昇進や配置転換時の参考にされやすい |
| 評価者の影響 | 評価はあくまで「人が人を見るもの」。相性や印象、信頼関係も影響を及ぼす 客観性を担保するために“複数の視点”や“評価会議”を設けている企業も増えている |
【補足】評価される主要スキルとは


昇進や高評価を得るためには、「今の成果」だけでなく、「それを未来で再現可能か」を支えるスキルセットも見られています。
ここでは、参考までにわたしの経験も踏まえて、職種・業界でも共通して求められる代表的なスキルを紹介します。
| スキル | 説明 |
|---|---|
| コミュニケーション | 上司・同僚。クライアントとの円滑なやりとり(報連相の質やスピード) 必要な情報を汲み取り、正確に伝える能力 |
| 問題解決力 | 課題の構造を分解し、根本的な解決策を提示できる能力 データ・事実・状況に基づく判断力 |
| 主体性・当事者意識 | 指示待ちではなく、提案型のスタイル 与えられた範囲内からの染み出し |
| リーダーシップ | 他人に仕事を依頼したり、チームを動かす力 個人の感情と求められている役割を切り分け、立場に沿って振る舞える力 |
| 自己管理力 | 期日や納期を守れるセルフマネジメント力 体調管理能力 ストレス下でも冷静に判断し、継続的に成長できる姿勢 |
環境を変える選択肢も視野に


努力の方向性を整えても、どうしても評価されない場合。
それは、あなたの問題ではなく「環境」のせいかもしれません。
報われない場所に居続ける必要はありません。
評価される場所、伸びやすい職場に身を置くことで、あなたの可能性はもっと広がります。
自分を責めるのではなく、“自分を活かせる場”を探す視点を持ちましょう。
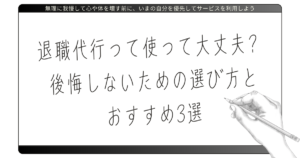
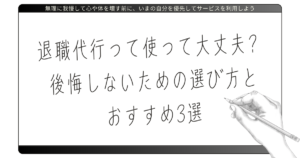
頑張る“前に”戦略を立てよう
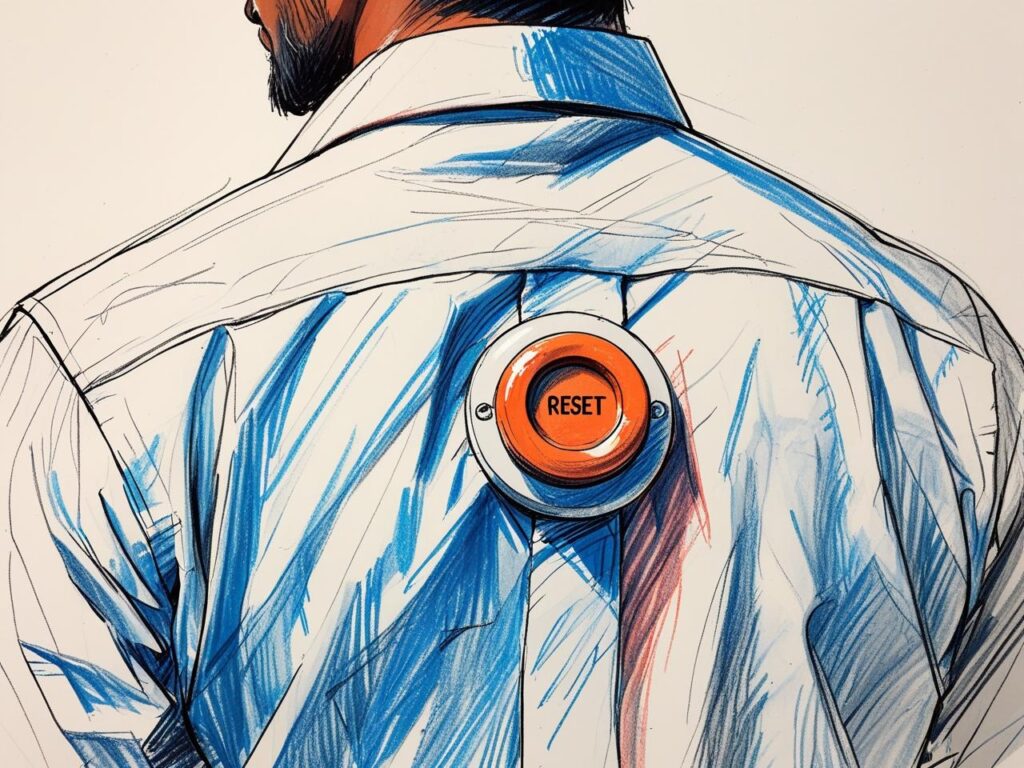
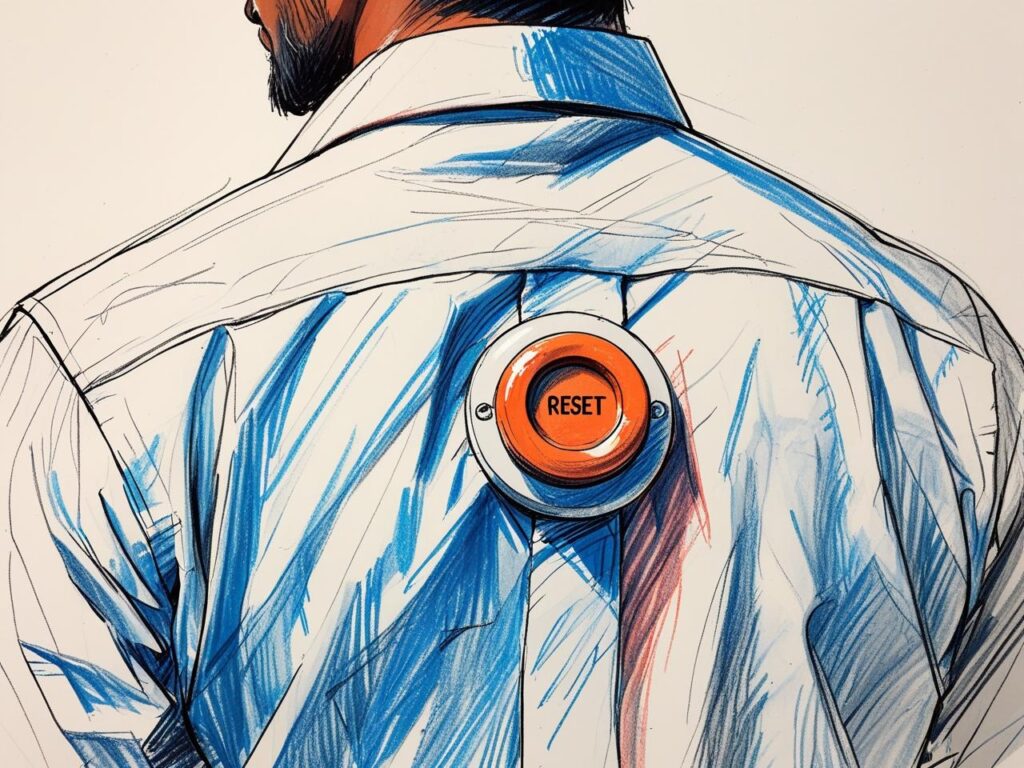
報われない努力に疲れてしまったあなたへ。
まず見直すべきは「自分の能力」ではなく、「方向性」です。
評価されている人は、運や才能ではなく、“評価されやすい行動”を選び取っています。
今回、紹介したすべての取り組みを一度に行う必要はありません。
とっつきやすいものから、まずは1つ試してみましょう。
あなたも自分の努力を少しだけ見直すことで、これ以上がんばりすぎることなく、きちんと評価されるキャリアに変えていけます。
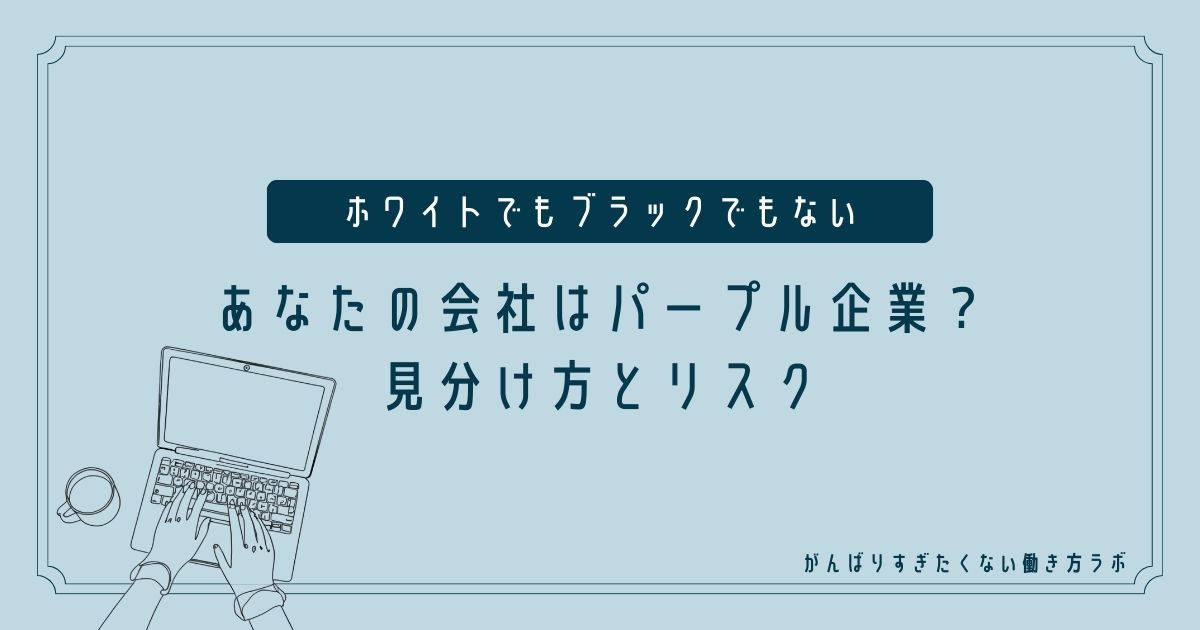
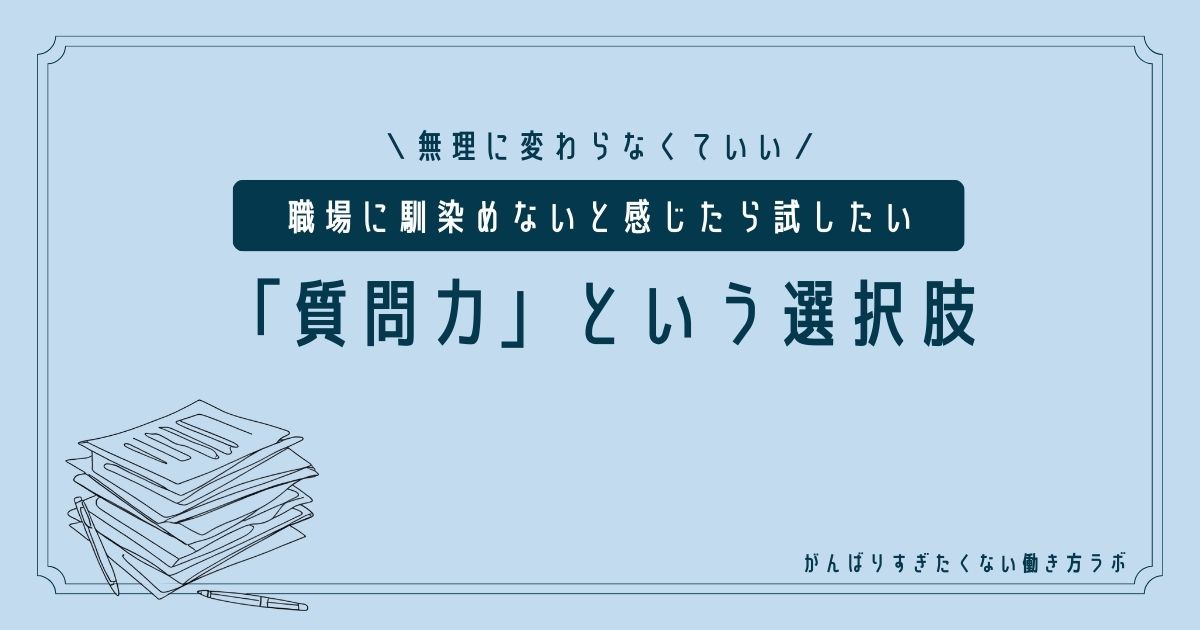
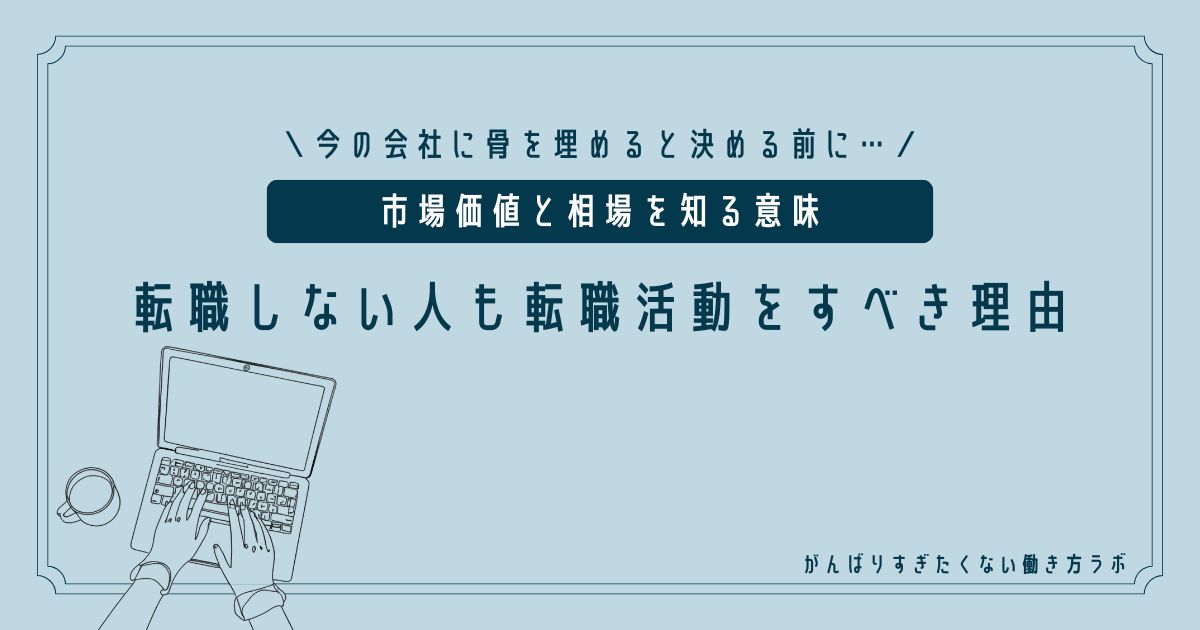
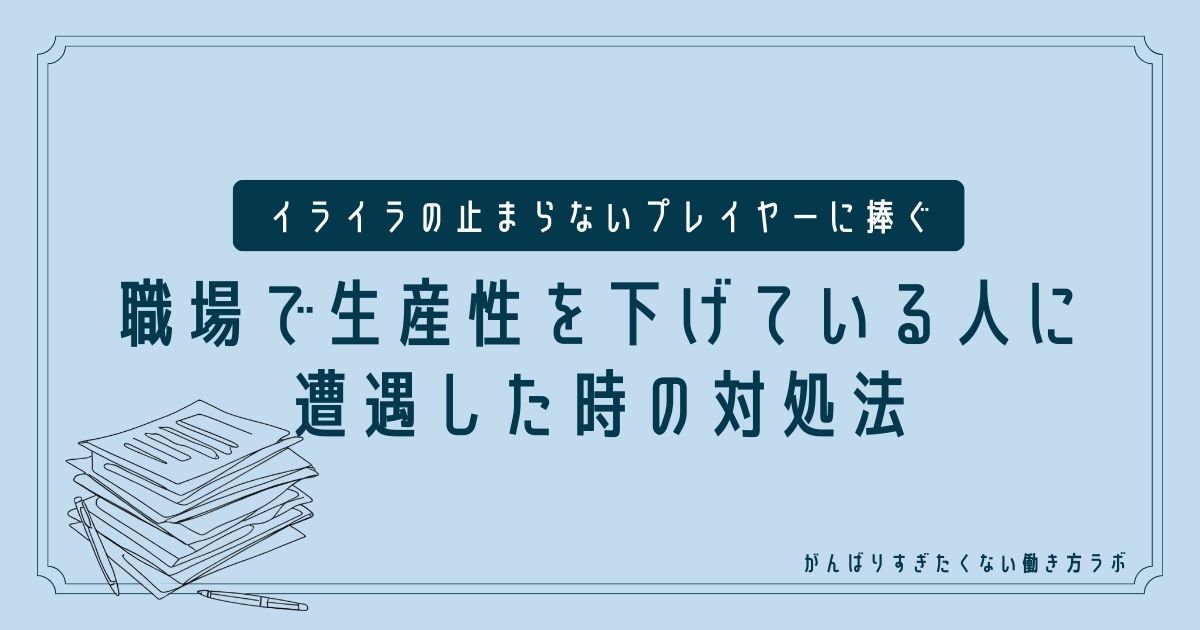
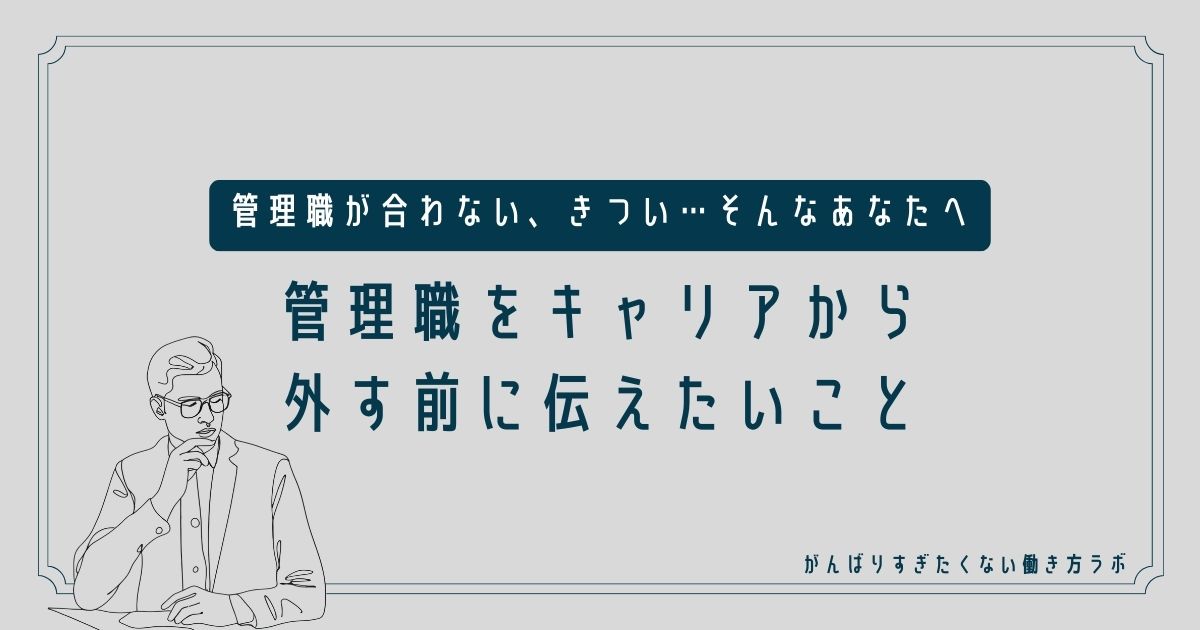
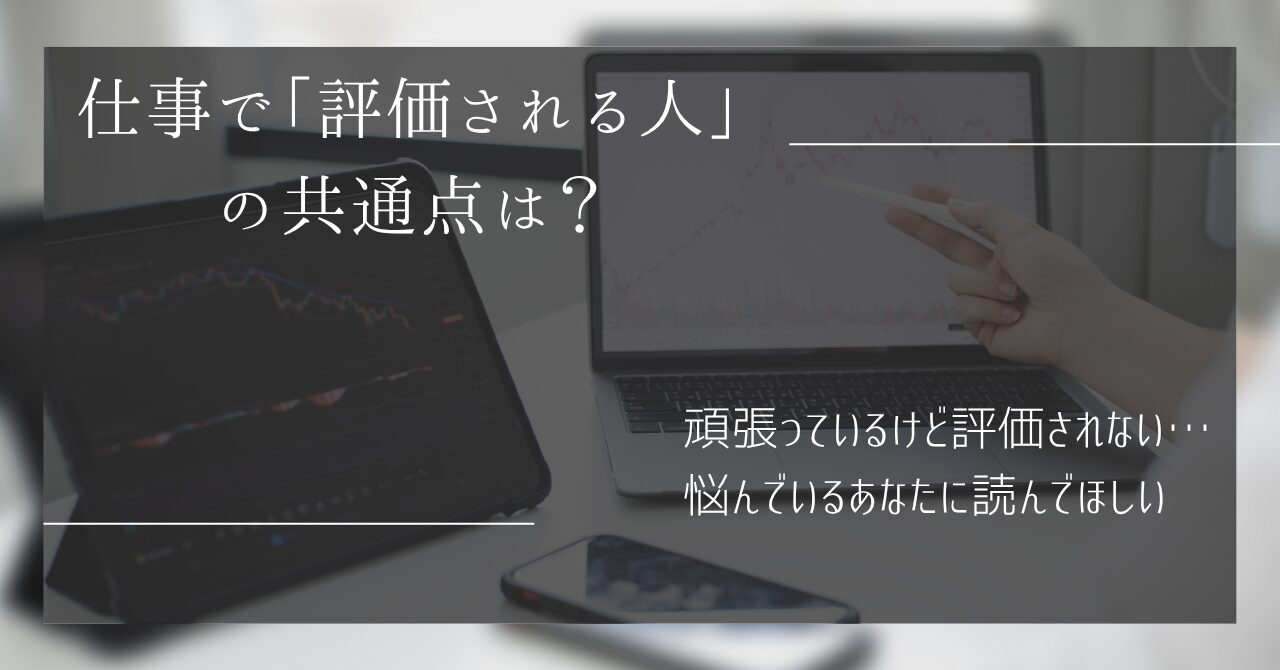
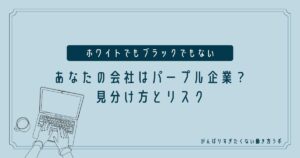
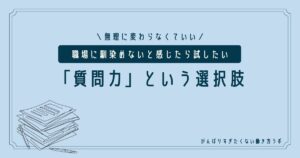
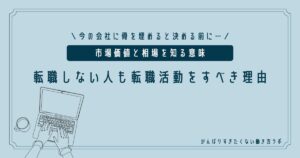
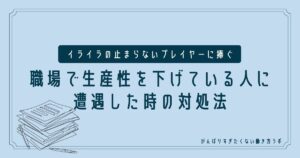
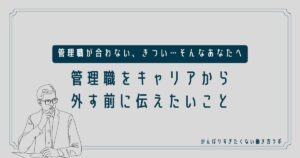
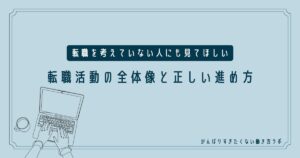
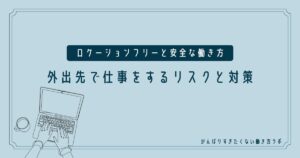
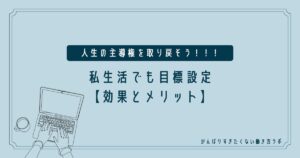
コメント