仕事をしていると、どうしても同僚や同期と自分を比べてしまうことはありませんか?

自分だけ成果が出せていない気がする



あの人はもう昇進しているのに
――そんな思いにとらわれてしまうと、焦りや不安が募り、仕事へのモチベーションまで落ちてしまいます。


実は、同僚との比較は誰にでも起こり得る自然な心理です。
しかし、その比較が続くと、あなた自身の成長や可能性を見えにくくしてしまうこともあります。
この記事では、会社員歴15年以上、現役で10名の部下を持つ筆者が、
- なぜ私たちは同僚と自分を比べてしまうのか
- 比較がもたらす悪影響とは何か
- そして、そのループから抜け出すための具体的な方法
をわかりやすく解説します。
「比較の苦しさ」から抜け出し、あなたが自分らしく前向きにキャリアを歩むためのきっかけになれば嬉しいです。
比較よりも「自分軸」に集中しよう


同僚との比較は、私たちの心を大きくすり減らす原因です。
もちろん「負けたくない」という気持ちが努力の原動力になることもあります。
しかし、常に他人を基準にしてしまうと、どれだけ頑張っても「まだ足りない」「自分は劣っている」と感じ続けてしまうのです。
本当に大切なのは、他人との比較ではなく 自分自身の成長や立てた目標を基準にすること。
昨日の自分よりも一歩前進できたか、小さな成功を積み重ねられたか――
その視点を持つことで、無理なく前向きに成長を続けることができます。
つまり、「比較する相手を同僚ではなく“過去の自分”に変えること」が、
あなたの心を守りながら着実に前進し、キャリアを築く第一歩になるのです。
同僚と比較してしまう4つの理由
人間は「比べる」ことで安心したい生き物


心理学では「社会的比較理論」と呼ばれる考え方があります。
人は自分の立ち位置を確認するために、無意識に周りの人と比べてしまうのです。
昇進スピードや成果、スキルレベルを比較することで「自分は大丈夫だろうか」と安心を得ようとします。



これ自体は人間が社会を築き、その中で上手く生きていく上で非常に重要な能力です。
SNSや職場環境が比較を加速させるから


情報化社会という言葉が叫ばれて久しいですが、
現代社会では、インターネット、SNS、スマホが発展し、個人に触れられる情報量が爆発的に増えています。
その中でもSNSでは、他人の「うまくいっている姿」ばかりが目に入ります。
なぜなら、人は日常の失敗や停滞よりも、
キラキラした成功体験やポジティブな出来事を発信しやすい傾向があるからです。
その背景には、「人から良く見られたい」という承認欲求や、「せっかく発信するなら楽しいことを共有したい」という心理が働いています。
さらに、SNSの「いいね」やコメントといった反応は、
ネガティブな内容よりもポジティブな投稿の方が得られやすいため、発信内容が成功体験に偏りやすくなるのです。
そのため、実際には誰もが苦労や悩みを抱えているのに、
SNS上では「成功している人ばかり」のように見えてしまうんですね。
職場でも、評価や成果は目立ちやすいため、どうしても「人と比べる土壌」ができやすいのです。
承認欲求が強く働くから


「もっと認められたい」「評価されたい」という気持ちは自然なものです。
しかし、その承認欲求が強すぎると、
つい周囲と比べて「自分は劣っているのでは」と焦りや不安につながることや、
自分の努力や成果が正当に評価されていないという思い込みに至ってしまいます。
特に、完璧主義の人や責任感の強い人、評価を気にしやすいタイプの人は、この状況に陥りやすい傾向があります。
常に「他人からどう見られているか」を意識しやすいため、
比較が自分のモチベーションではなく不安の種になってしまうのです。
目標設定が曖昧だから
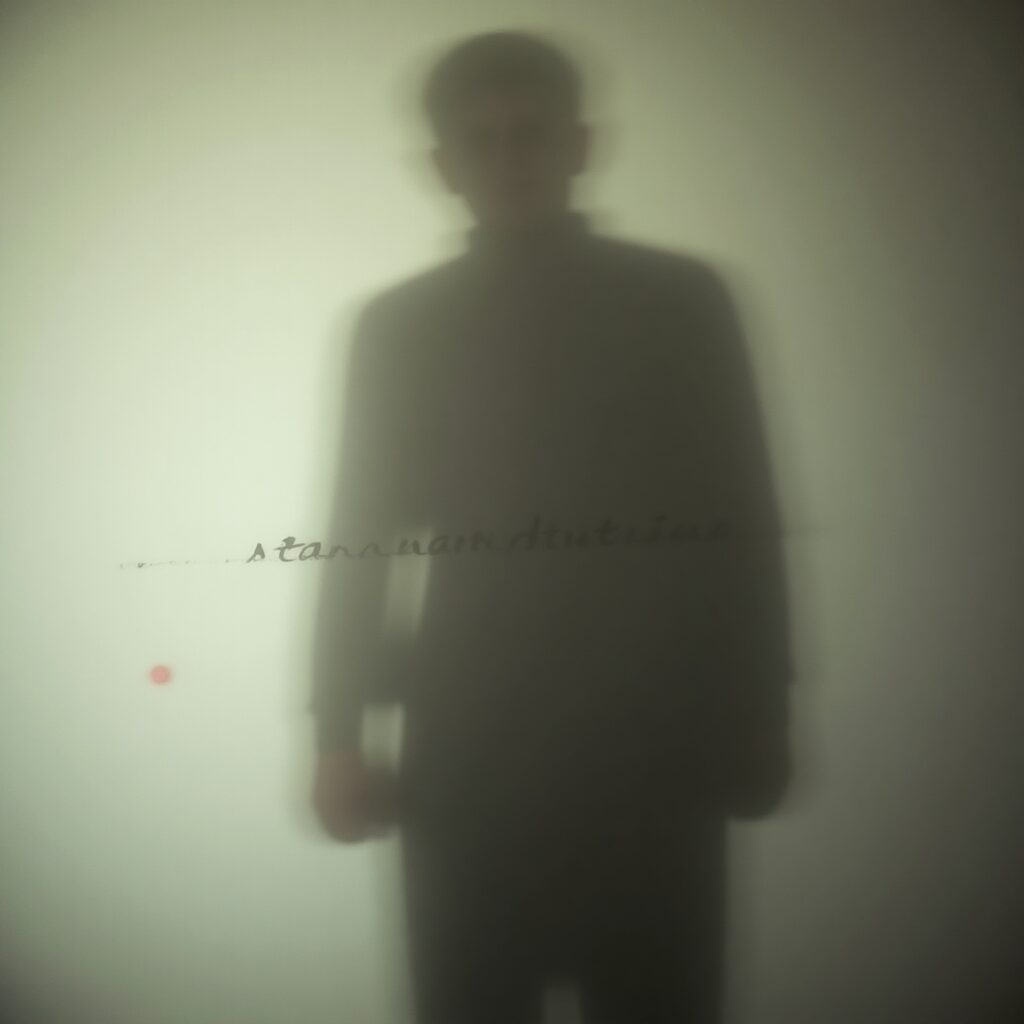
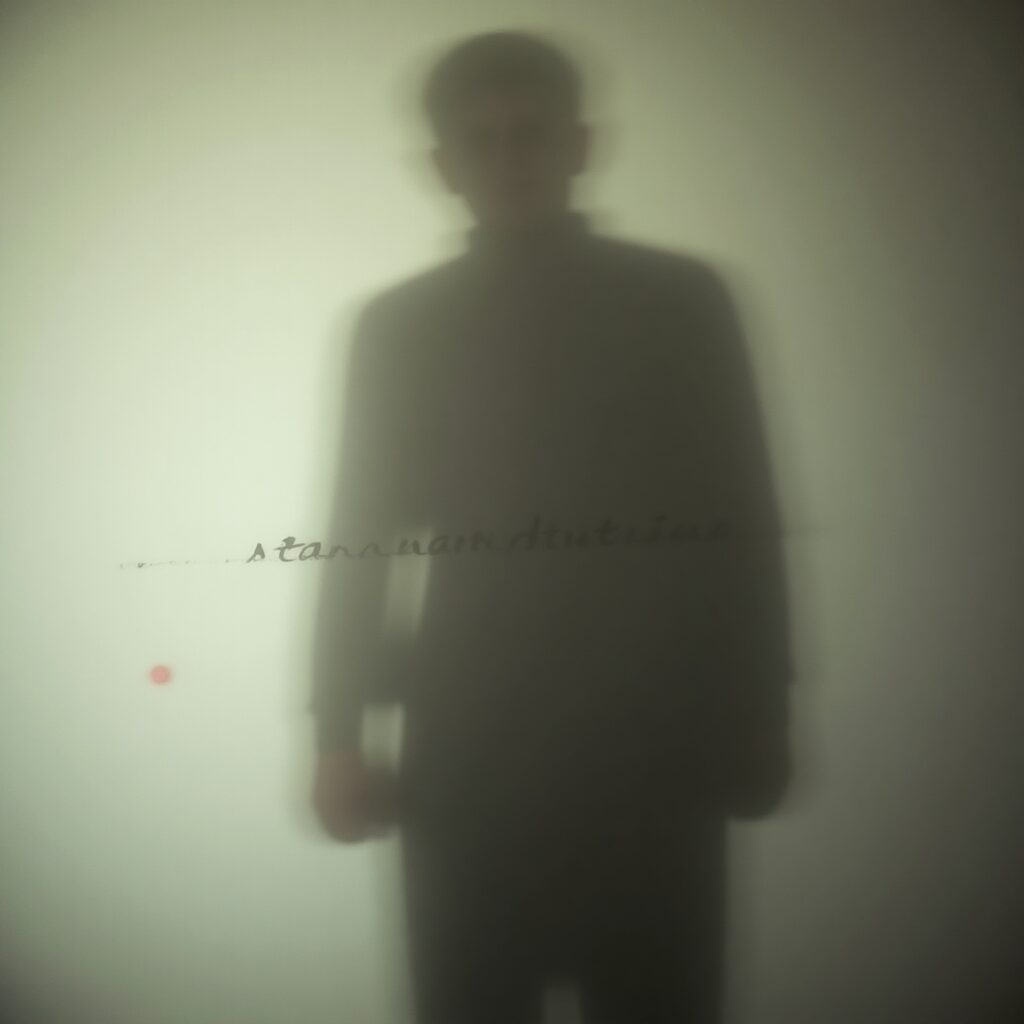
自分がどんな基準で成長を測るのかが明確でないと、
どうしても「他人」という分かりやすい物差しに頼ってしまいます。
「自分は今どこを目指しているのか」「どんなスキルを身につけたいのか」が曖昧なままだと、
同僚の成果やスピードが気になりやすく、比較のループに陥ってしまうのです。
同僚との比較がもたらす悪影響
同僚との比較は、一時的にモチベーションを高めることもありますが、長期的には心身に悪影響を及ぼすことが少なくありません。
ここでは代表的な悪影響を3つ取り上げます。
自己肯定感の低下


比較を続けると、自分の努力や成長に目を向けるよりも、他人の成果ばかりが気になるようになります。
例えば「同じ時期に入社した同僚がもう昇進したのに、自分はまだ…」という考えに支配されてしまうのです。
そうなると、自分が積み重ねてきた経験や達成を過小評価しがちになり、「自分は劣っている」という思い込みが強まります。
これは本来の能力や実績とは関係なく、自己肯定感をじわじわと削り取ってしまう原因となります。
不健全な競争意識


本来、仕事における競争はチーム全体の成果や顧客への価値提供につながる建設的なものであるべきです。
しかし、同僚との比較が強くなると、ゴールが「チームの成功」ではなく「自分が同僚より優位に立つこと」にすり替わってしまいます。
たとえば、同僚の失敗を内心で喜んでしまったり、協力すべき場面でわざと情報を出し惜しみするなど、不健全な行動が生まれることもあります。
このような空気は職場の人間関係を悪化させ、信頼関係を壊す要因となり、結果的にチーム全体のパフォーマンス低下につながりかねません。
精神的ストレスの増加
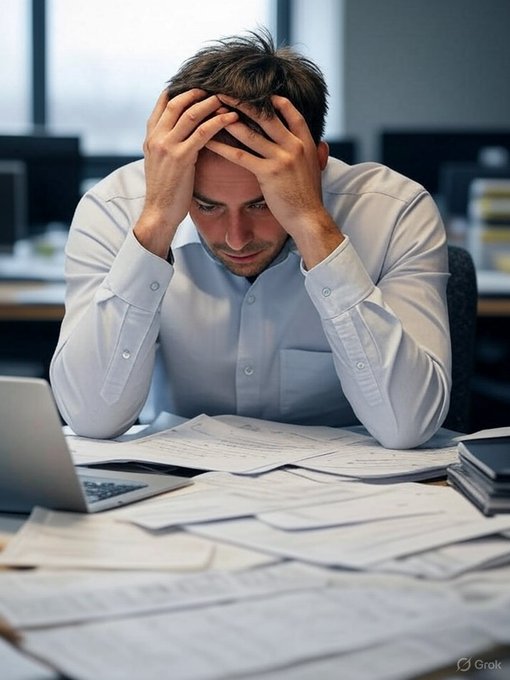
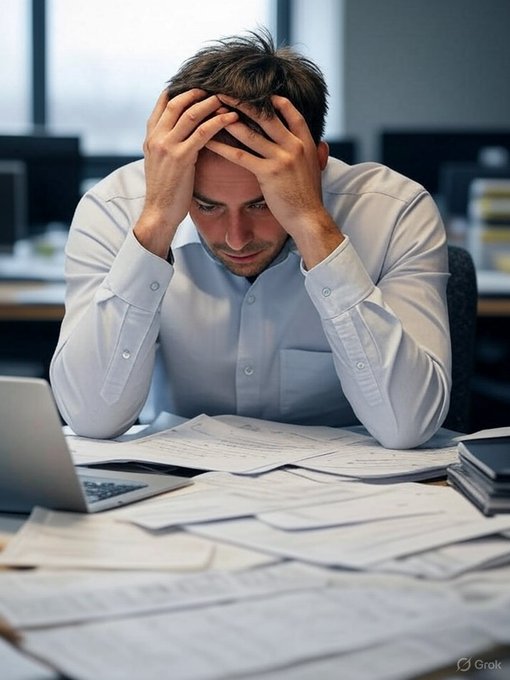
常に「周囲に比べて自分はどうか」と意識し続ける状態は、大きな精神的負担となります。
成果を出しても「もっと上がいる」と満足できず、安心する間もなく次の比較対象を探してしまうからです。
このような終わりのない比較ゲームは、慢性的な焦燥感や不安感を生み、ひどい場合には心身の不調につながることもあります。
仕事中だけでなく、プライベートの時間まで「同僚のSNS投稿が気になる」といった形で気持ちを休められず、生活全般に悪影響を及ぼすことさえあります
このように、同僚との比較は「自己肯定感を削ぐ」「協力より競争を助長する」「ストレスを積み重ねる」という悪循環を生み出します。
一見モチベーションにつながるように見えても、長期的にはむしろ心身を消耗させ、キャリア形成や人間関係に深刻なダメージを与えるリスクが高いのです。
比較をやめて「自分軸」に戻る方法


同僚との比較は、気づかないうちに私たちの心を疲れさせます。
特にSNSや職場での評価は「誰かと比べる土壌」をつくりやすく、放っておくと自己肯定感を下げたり、不安や焦りを生んでしまいます。
こうした悪循環から抜け出すためには、
「他人基準」ではなく「自分基準」で物事を見る視点 を取り戻すことが不可欠です。
ここでは、今日からできる具体的な工夫を、実際のシーンを交えながら紹介します。
自分の小さな成長に目を向ける


比較をやめる最初のステップは、他人ではなく「過去の自分」と比べることです。
たとえば、1か月前の自分と比べて「新しい仕事を習得できた」「業務を少し早くこなせるようになった」といった小さな成長を記録してみましょう。
毎日の成果をメモや日記に残すだけでも、「自分なりに進歩している」という実感が積み重なり、他人と比べる必要性が薄れていきます。



私の組織では、新人に日報として成果やできたことを書かせるようにしています。謙虚でできたことを取り上げるのが苦手なタイプには、上司がサポートし、自分の小さな成長に気付くことを、習慣化しています。
曖昧な目標を具体的な目標へ
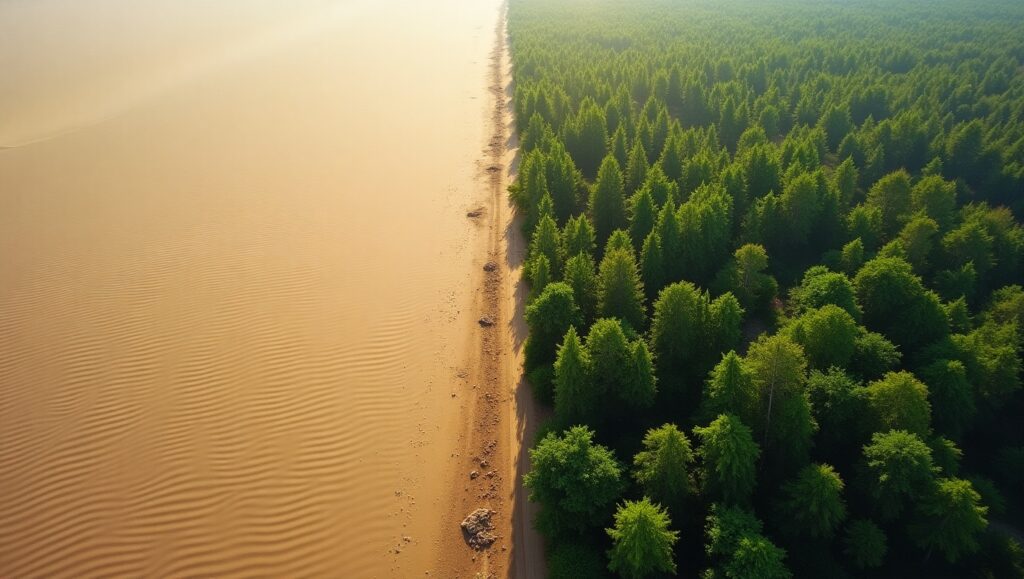
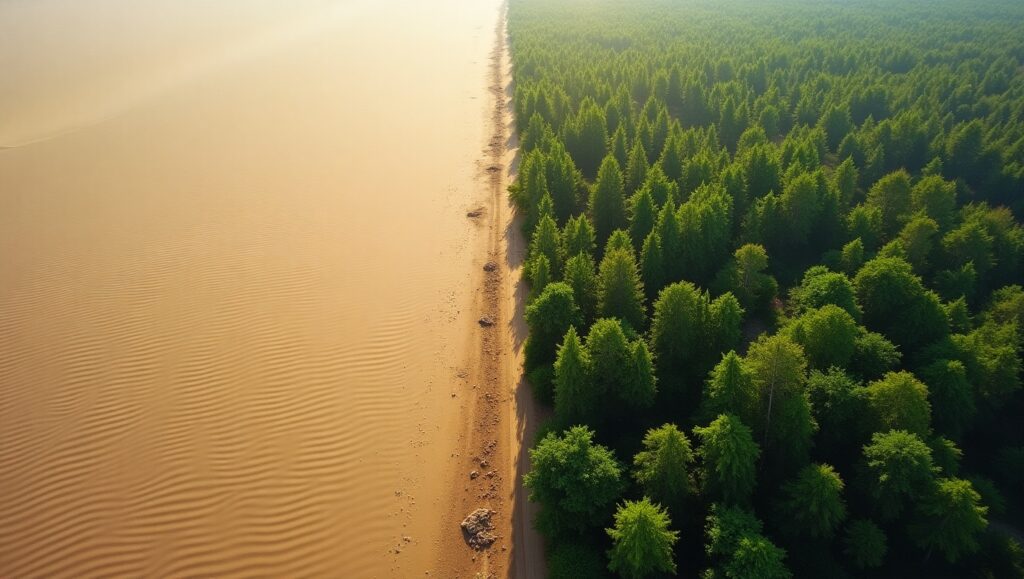
比較に陥りやすい人の特徴として「目標が曖昧である」ことが挙げられます。
ゴールがはっきりしていないと、どうしても周囲の人の動きを基準にしてしまうからです。
そこで「半年後に資格試験に合格する」「来月は残業を10時間減らす」といった、自分でコントロールできる具体的な目標を立てましょう。
こうした目標は他人の動向に左右されず、常に「自分軸」を保ちながら進めることができます。
SNSの情報摂取を意識的に制御する


SNSは人の「キラキラした瞬間」や「成功体験」が強調されやすく、偏った情報に触れることで比較意識が増幅されます。
これを防ぐには「SNS断ち」や「利用時間の制限」が効果的です。
たとえば、朝の通勤中はSNSを開かず読書にあてる、夜は寝る前30分はスマホを見ないといった小さな習慣を導入してみましょう。
これにより、他人の成功ストーリーではなく、自分の現実や日常に意識を戻すことができます。



私も定期的にSNS断ちを行っています。やってみれば以外と弊害はありませんよ。
必要になればまた再開すればよいのです。
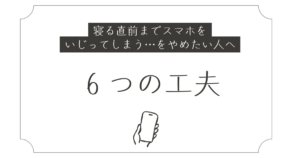
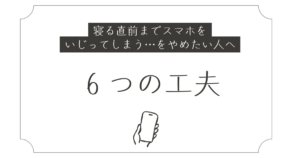
自分の価値観を言葉にして整理する


他人と比較してしまう背景には、「自分が本当に大切にしたいこと」が曖昧なままになっていることがあります。
自分にとっての幸せや達成感は何なのかを、言葉にして書き出してみましょう。
たとえば「家族との時間を大事にする」「健康を損なわずに働きたい」といった自分の価値観を明確にすれば、他人がどう評価されていても「自分はこれでいい」と納得感を持ちやすくなります。



育休から戻った部下はキャリアの遅れを気にしていましたが、
キャリア相談で「自分にとって大事なこと」をノートに書きだし、自分の価値観に気付いたことで、前向きに働けるになりました。
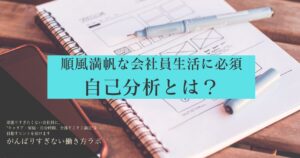
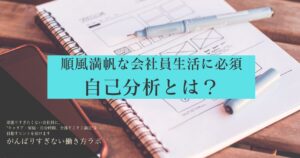
感謝の習慣を取り入れる


比較の意識は「自分に足りないもの」にばかり目を向けさせます。
これを逆転させるのが「感謝の習慣」です。
1日の終わりに「今日ありがたかったことを3つ書く」といったシンプルな実践で構いません。
小さな出来事への感謝を積み重ねることで、足りないものではなく「すでに持っているもの」に気付けるようになり、比較への執着が自然と弱まっていきます。


5つの方法まとめ


比較のクセから抜け出すためのカギは「他人ではなく、自分を基準にすること」です。
- 小さな成長に注目する
- 具体的な目標を立てる
- SNSの使い方を工夫する
- 自分の価値観を整理する
- 感謝を習慣化する
これらを実践すれば、承認欲求に振り回されず、自分のペースで安心して歩んでいけるようになります。今日からできる一歩を積み重ね、自分らしい「自分軸」を取り戻していきましょう。
比べなくても、あなたは前に進める
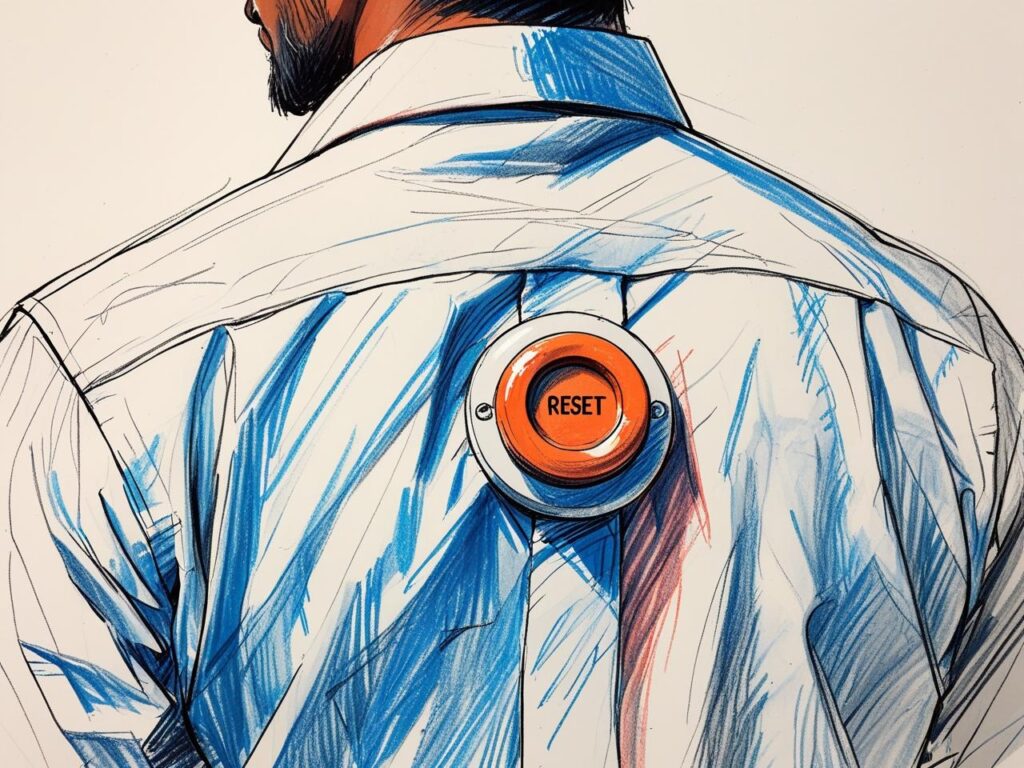
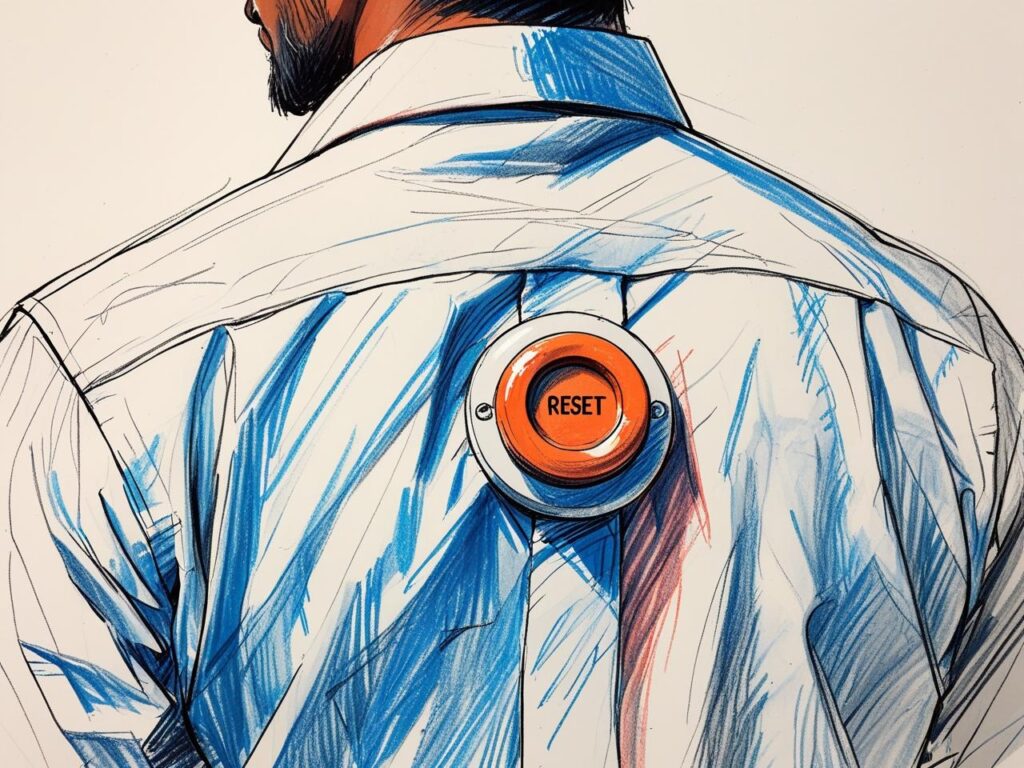
同僚との比較は、誰もが経験するごく自然なことです。
けれども、その比較にとらわれ続けると、自分の良さや成長の実感を見失い、苦しさばかりが大きくなってしまいます。
大切なのは、比較のクセに気づき、少しずつ「自分軸」に戻っていくこと。
昨日の自分より少しでも前に進めたなら、それは確かな成長です。
あなたには、他人と比べなくても前進できる力があります。
小さな一歩を積み重ねることで、自分らしいキャリアと、心の安定を両立させることができるのです。
どうか今日から、「自分の歩み」に優しく目を向けてあげてください。
この記事が、あなたが自分らしく前向きにキャリアを歩むためのきっかけになれば嬉しいです。
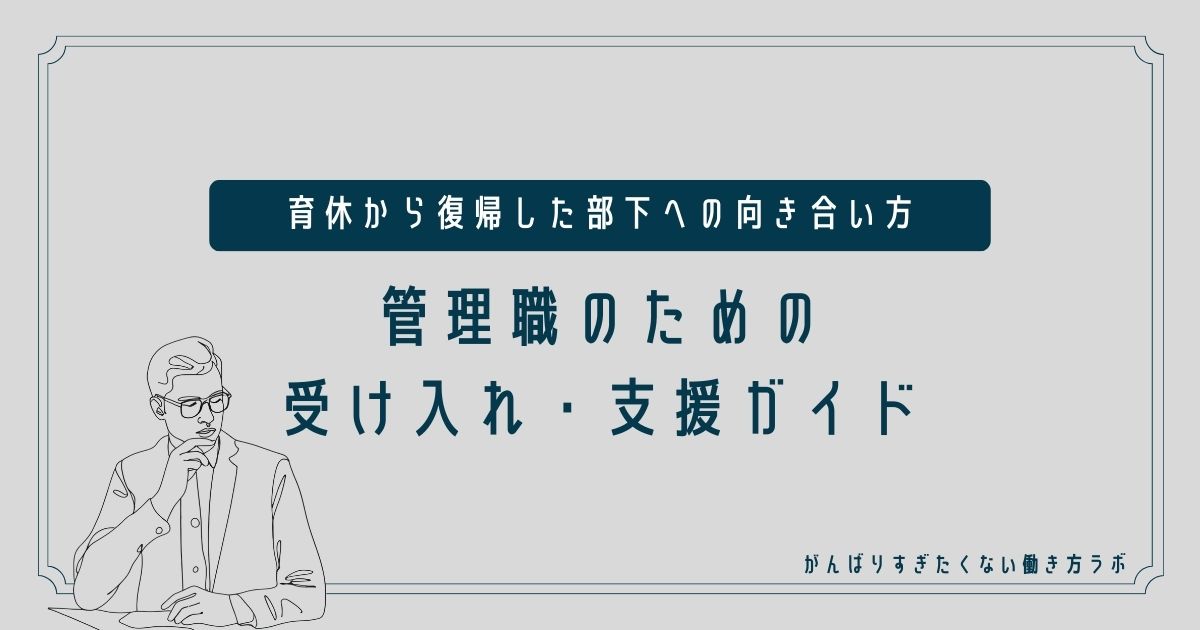
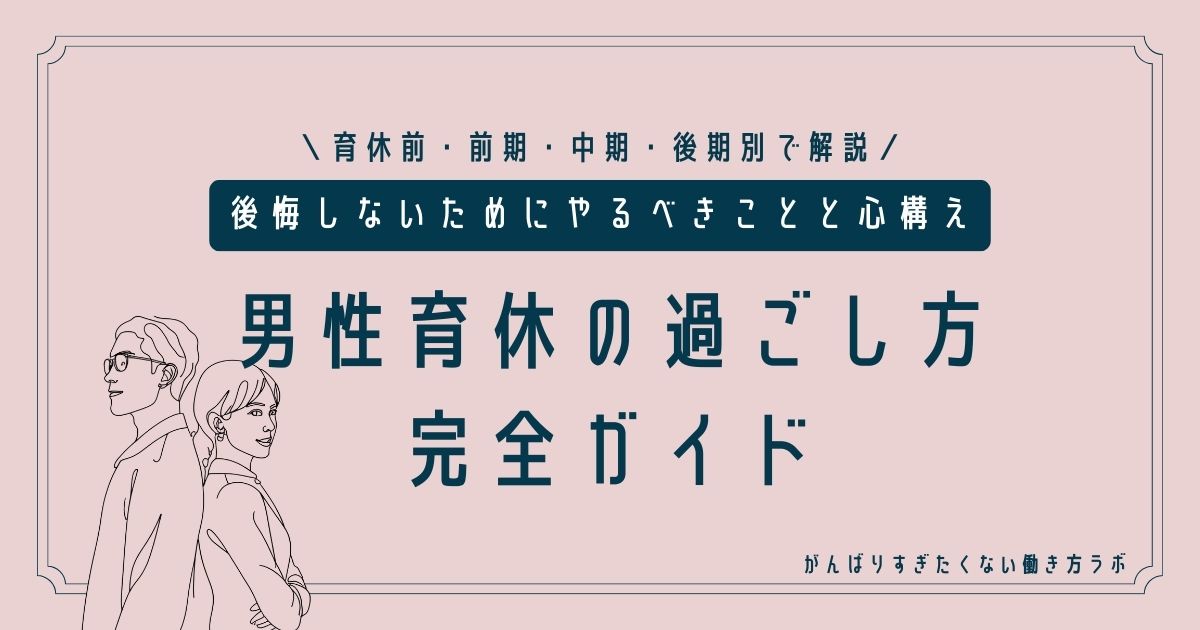
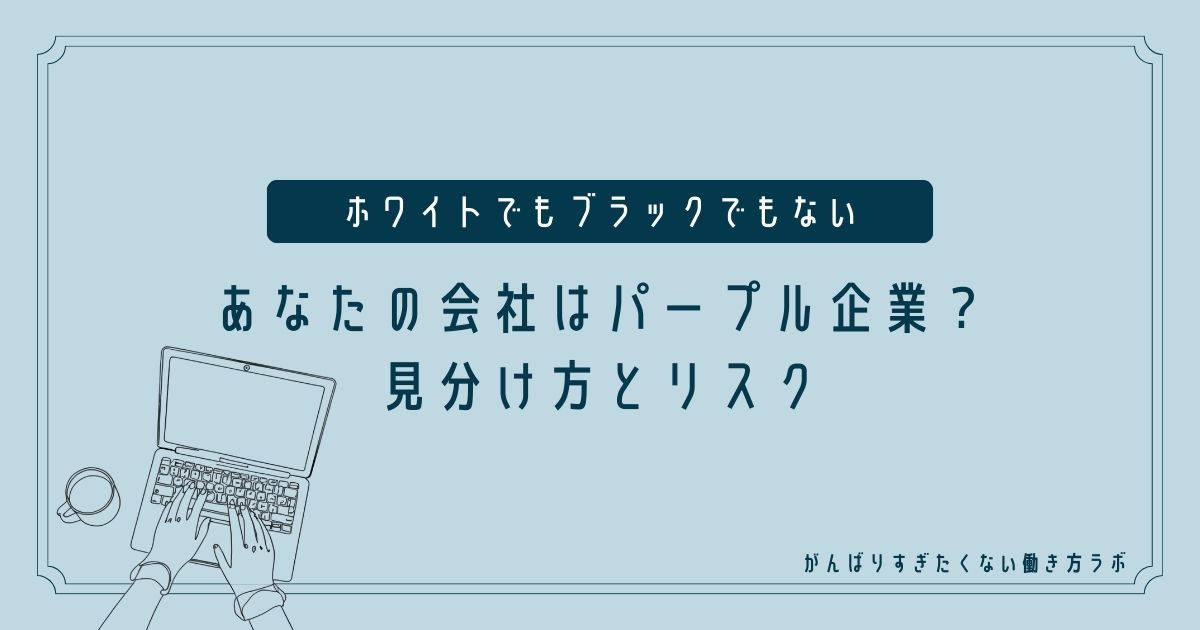
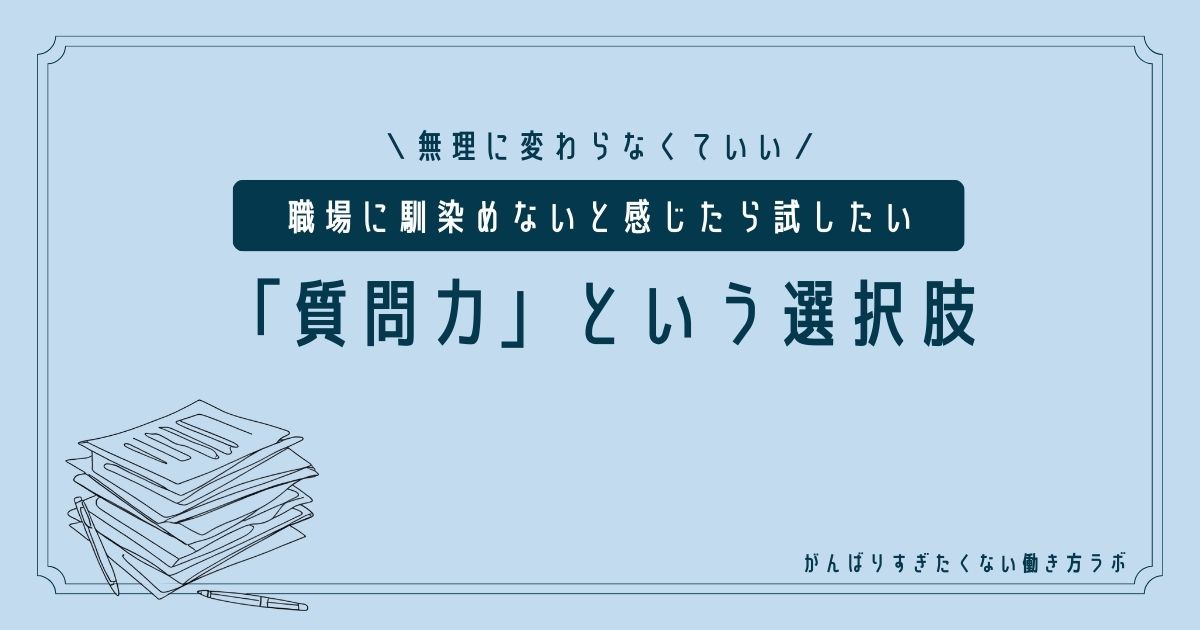
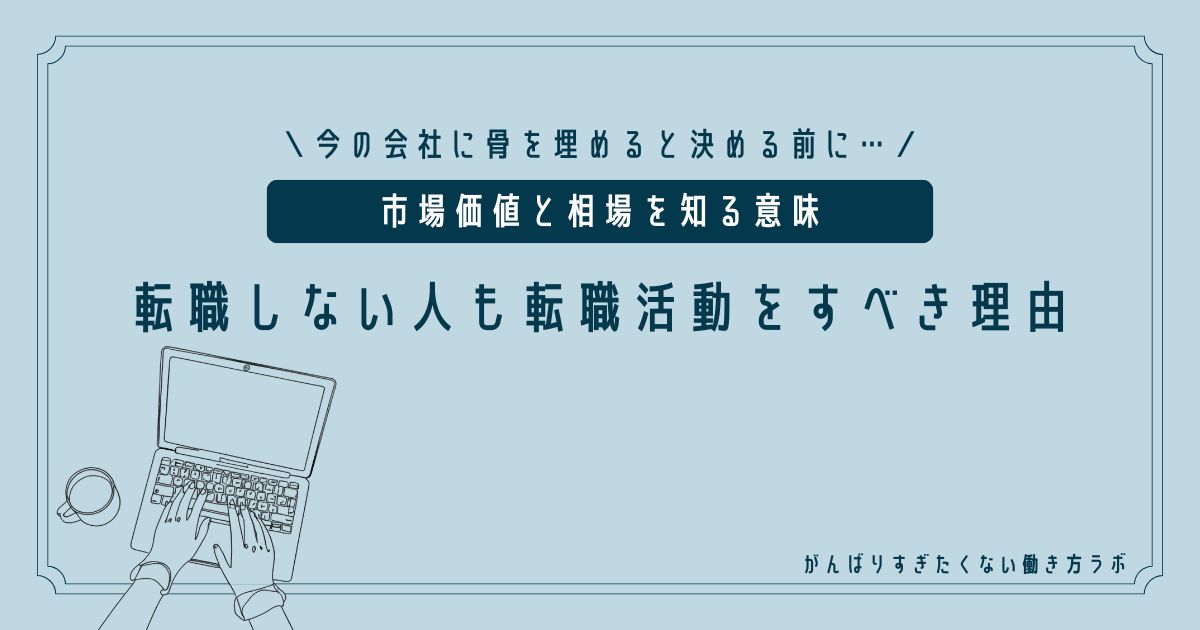
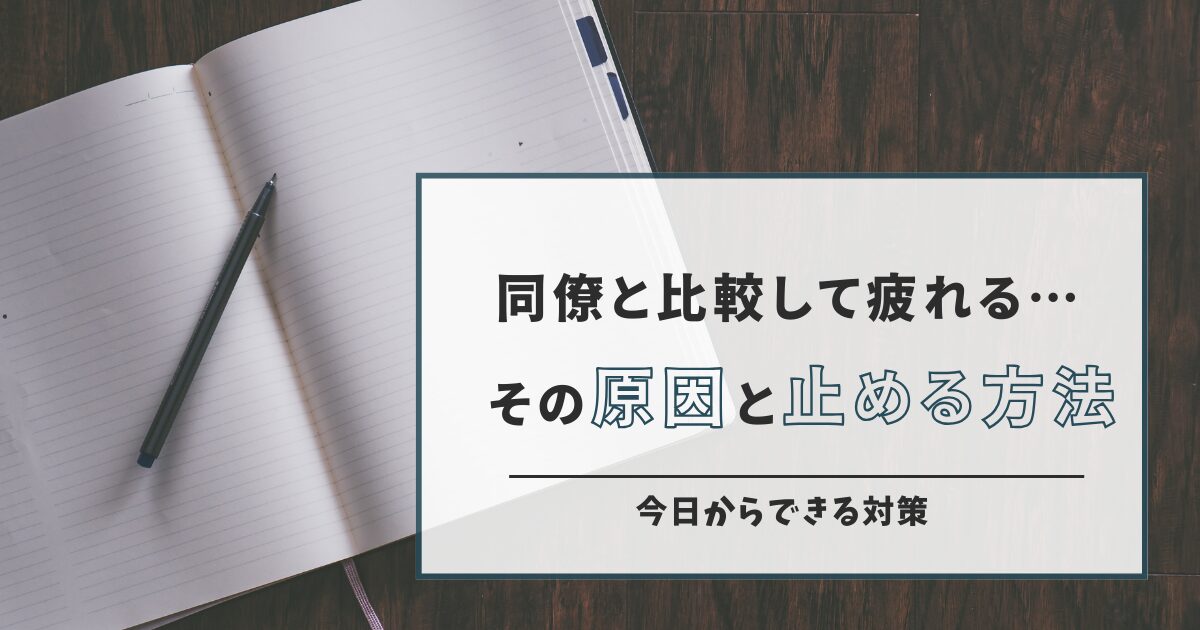

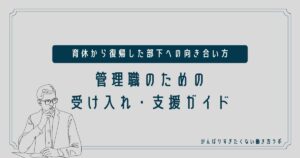
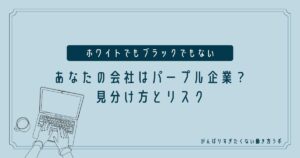
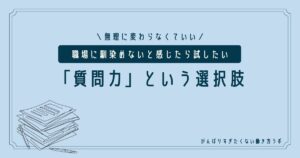
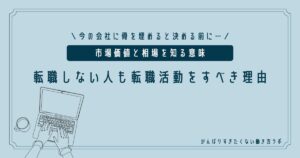
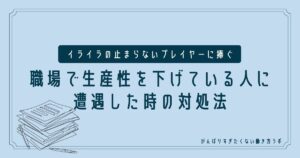
コメント