
ママ友はみんなパートを始めたらしい。



片働き、子供の学費が不安。かと言って共働きの毎日は大変そう……
共働きが“当たり前”に聞こえる今、片働き(夫婦どちらかだけ専業)のわが家は 「このままでよいのか?」 と焦ることがあります。
でも実際には、片働きにも共働きにも一長一短があり、どちらが“正解”という話ではありません。
この記事では 、片働き歴10年の筆者が「うちは片働きでよい」と納得できるに至った考えを、「片働きのメリット」を中心にしてまとめています。
読み終わった後には、あなたも「うちは片働きを活かしてこう暮らそう」「やっぱり共働きを検討しよう」と
一歩が踏み出せ、納得感をもって日々の生活が送れるようになるはずです。
そもそも「”片働き”ってなんだろう?」…という方はこちら
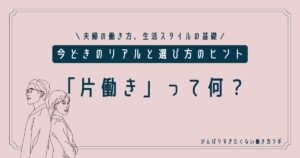
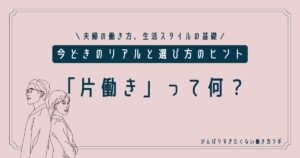
「片働き」でよいかはあなたとあなたの家族にしか分からない


片働きか共働きかに“正解”はありません。
大切なのは “自分たちの価値観” × “ライフステージ” × “家計数字” を突き合わせ、 家族が納得して選ぶ ことだけです。
「周りがどうか」ではなく、「わが家が何を大切にしたいか」で決める――これが片働きでも後悔しない最大のコツです。
では、あなたが何を大切にしたいかを明確にしていくために、まずは共働きと比較した片働きのメリット・デメリットを説明します。
3つの視点からみる片働きのメリット・デメリット
家計


メリット
- 配偶者控除・社会保険の扶養制度による節税効果
片働き世帯では、年収が一定以下であれば配偶者控除や配偶者特別控除が使え、所得税・住民税が年間数万円単位で軽減されます。
また、健康保険や年金も扶養に入れば主婦・主夫は保険料の自己負担がゼロに。 - 在宅中心の生活で支出が抑えられる
共働きではランチ代・外食・通勤費・保育料など、“働くために必要な出費”が発生します。片働きだとこうしたコストを抑えられ、実質的な可処分所得はむしろ高くなるケースもあります。
デメリット
- 収入源がひとつ=リスク集中
働いている方が病気や失職になると、即、家計が危機に直結します。また、収入アップの手段が限られやすく、インフレや教育費の増加に対応しにくい面も。 - 長期的な資産形成に限界が出やすい
老後資金の準備や住宅購入、子どもの進学費用など、ライフイベントにかかる資金が大きい現代では、ダブルインカムの家庭より貯蓄ペースが遅れがちになる傾向があります。
まとめ
片働きのメリットも上げましたが、やはり家計という点では共働きのほうが総合的に優位性があります。特に将来に備えた資産形成では不利になりがちです。
昨今日本でもインフレが進んでおり、インフレでは節約による貯蓄の効果が相対的に弱いため、稼ぎの大きい方が対応しやすいです。税制面でのメリットも、女性の社会進出を推し進める影響で今後はどちらかというと改悪の方向性に進むことが推測されます。
よって、片働き世帯では固定費の圧縮・無理のない範囲での資産運用など、堅実な家計戦略が不可欠です。
家族時間・育児


メリット
- 育児や家事にじっくり向き合える
保育園や学童に頼らず、親が子どもの生活を主導できる。接点を多く持てるので、急な発熱や学校行事にも対応しやすく、子どもとの信頼関係や安心感が育ちやすい環境です。 - 家庭内のゆとりが生まれやすい
仕事で日銭を稼ぐことと、育児を含む家庭の仕事、そちらに主体を置くかの役割が自明なので、分担がしやすく、家全体に「余裕」や「温度差のない会話」が生まれやすい傾向があります。
デメリット
- パートナーへの家事育児依存が進みやすい
家庭にいるほうが「やって当たり前」になりやすく、役割の偏りや不満が蓄積することも。 - 子どもが外との接点を持ちづらいケースも
親主導で日中を過ごす分、保育園や学童などでの多様な人間関係に触れる機会が減ることもあり、社会性や自立心の形成に注意が必要です。
まとめ
家族時間・育児という点では片働きにはっきりと優位性があります。
工夫によって作ることのできる時間的な余裕や子供と過ごす時間が明らかに多いです。そのため、接点の持ちにくさというデメリットも、公園に出かけたり片働き同士のネットワークを構築するなど、積極的に動けば補うことができます。
パートナーへの家事育児依存が進みやすいという点は確かにデメリットですが、この問題は共働きでも発生し得ます。片働きにせよ、共働きにせよ定期的な夫婦の対話を行い、家事育児の負担が寄り過ぎていないかは確認しましょう。
メンタル・生活満足度
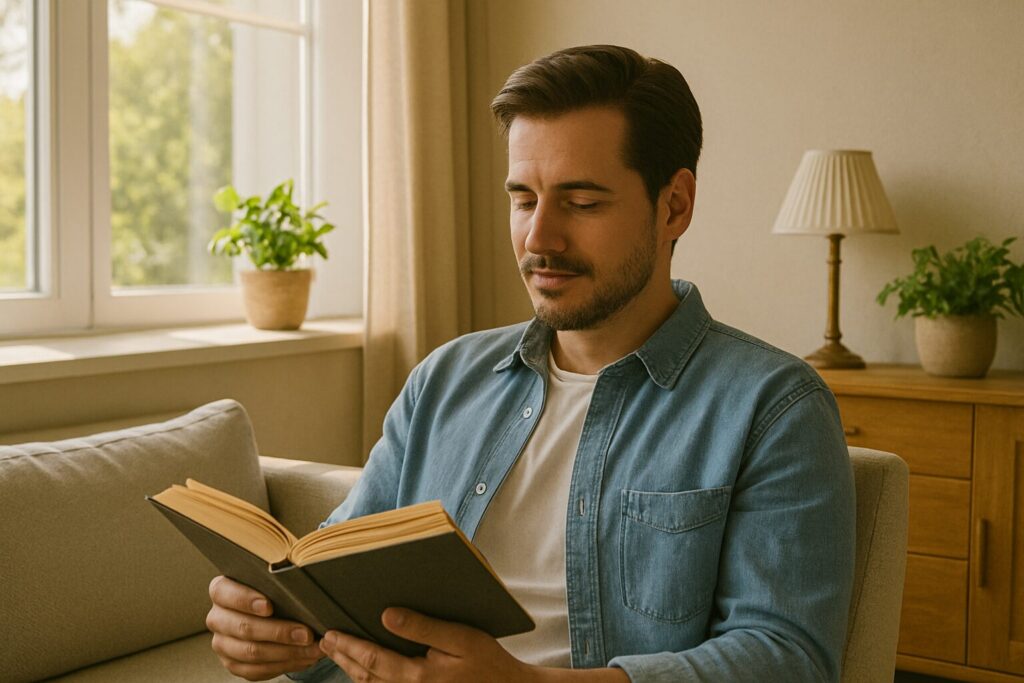
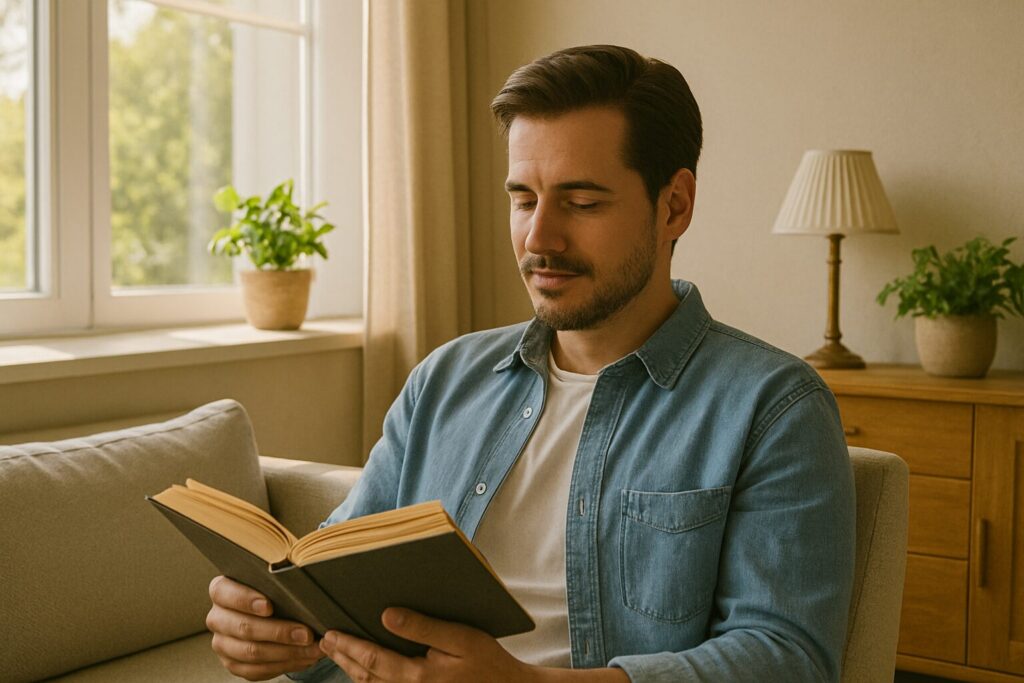
メリット
- 時間的・精神的な余裕が生まれやすい
「仕事・家事・育児をすべて同時進行」というプレッシャーが軽減され、ストレスや心の疲労感が少ない状態を保ちやすいです。 - 生活の“質”に集中できる
時短料理ではなく丁寧なごはん作り、季節の行事の準備、部屋を整える時間……暮らしを味わう時間が生まれるのも片働きならでは。
デメリット
- 社会とのつながりが希薄になりがち
主婦・主夫は、日中に大人との会話が少ない・社会的な役割が見えづらいことで、承認欲求が満たされにくくなることも。 - 「自分だけ取り残されている」感覚が生まれることも
主婦・主夫は、キャリアを積む友人やSNSの情報に触れ、「自分はこのままでいいのか…」という漠然とした不安や焦りを感じる場面も。
まとめ
メンタル・生活満足度という点では、一律の判断は難しいです。
片働きをしている側は、ある程度仕事に集中して打ち込めることで、やはり精神的な余裕を作りやすいです。
一方で、主婦・主夫側は時間的に“ゆとり”はあるのですが、「閉じた世界」になりやすいという落とし穴もあり、社会との乖離で苦しむケースも存在します。
メンタル・生活満足度という点では、夫婦の価値観や人生観によって良し悪しが変わると言えます。
我が家が片働きに腹落ちした理由


次は我が家がこのメリット・デメリットを踏まえて、どのように腹落ちしたかを説明していきます。
家計
幸いわたしの収入が安定しており、一馬力でもなんとか資産形成をできる状況でした。
一応誤解がないように補足しておくと、びっくりするほど収入が多いというわけでありません。夫婦の価値観的に浪費を良しとする家庭ではなかったので、日々の節約で黒字家計とし、計画的な貯蓄・投資が安定的に行えるビジョンが描けたことが大きかったです。
家族時間・育児
これは本当に片働きでよかったと思っています。子供は体調を崩しがちなので、妻が柔軟に対応してくれることで、わたしは安心して仕事に打ち込めています。
我が家には娘が2人いるのですが、次女はわたしが在宅勤務している環境で育った影響か、明らかに懐いてくれています。長女とも今は二人で仲良くお出かけもできますが、3歳ぐらいまでは休日にわたしが外に連れていくと途中で泣いたものです。
勿論、接し方や向き合い方でも変わると思います。それでもこの経験は、わたしが育児において過ごす時間や接点の多さが重要であると実感したきっかけです。
「忙しい忙しい」と言っていた妻も、今では娘たちが小学生になり、一緒に過ごす時間が減っていくことを実感して、就学前の時間が貴重だったと漏らしています。
メンタル・生活満足度
我が家では、最終的に「メンタル・生活満足度」を夫婦の価値観に照らし合わせて判断することになりました。
主婦である妻はリアルでの日々の交流は子供の関係者が多く、その筆頭がママ友です。
主婦のママ友は必然と主婦であることが多いのですが、子供の年齢が上がるにつれて職場復帰したり、パートなどで働く方が増えていきます。



みんなパートを始めてる…私も働いた方がいいのかな



働きたくなった?それともやりたいことがあるの?



そうじゃないけど…塾とか今後お金がもっとかかるでしょ



でも保育料・外食代でむしろ赤字かも
保育料や働く日は外食や中食前提で差額を算出、働ける時間と周辺のパートの時給からざっくり計算してみると、実質の手残りは月1万円程度だと判明しました。
これを踏まえて話し合い、現時点では「家庭を整えるフェーズ」とし、家事や家族との時間を優先してもらうことで二人で合意しました。今では、働く意味を見直したようで落ち着いて家事をしています。
わたしも妻が社会で働くことに価値を見出していたり、シンプルにやりたいことが見つかるなら応援します。しかし、世間体を意識して働くことや、費用を考えると利益の少ない時間売りの仕事を金銭目的で行うのには、あまり前向きではありません。
今後、妻が「やりたい仕事」が見つかったときは、わたしが在宅勤務日を増やして全力でサポートする方向で話をしています。
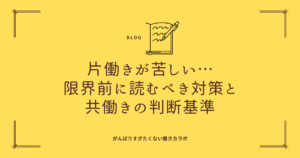
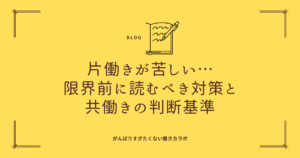
片働きのデメリットへの対処法


片働きの暮らしには、安心感やゆとりといった魅力がある一方で、「お金」「キャリア」「社会との接点」といった面で不安や葛藤がつきものです。ここでは、私自身の試行錯誤も交えながら、片働きならではの悩みとその対処法をいくつかご紹介します。
将来の不安には「情報と計画」で備える


「収入が一馬力だと将来が不安…」というのは、多くの片働き家庭が抱える共通の悩みだと思います。わが家でも、将来の教育費や老後資金について不安を感じたことが何度もありました。
その対策として実践しているのが、“数字ベースで考える習慣”です。毎月の支出を見える化し、年間のライフイベントや支出も早めにシミュレーション。将来必要なお金を「なんとなくの不安」ではなく、「具体的な数値」に落とし込むことで、対策が打てるようになります。何より可視化することで、今使ってよい金額や、貯まっていく資産が実感できるので安心してお金を使えるようになりました。
また、NISAなどの資産運用にもチャレンジしています。投資は事前の勉強が必須ですが、時間を味方につけて無理なく長期的な備えができるので、将来的な経済状況に不安のある方は是非検討してみてください。
孤立感には「ゆるやかなつながり」を


家庭中心の生活はとても大切な時間ですが、ふとしたときに「自分って社会から取り残されている…?」と感じる瞬間もあると思います。働いているわたしでも、家庭と仕事の往復で世間とギャップを感じることがありました。
そんな時に役立つのが、“ゆるくつながれる場所”の存在です。オンラインコミュニティなどで、子どもが寝たあとや家事の合間に、掲示板をのぞいたり、誰かの投稿に反応したりするだけでも、「自分は社会とつながっている」と思える安心感があります。
また、無理のない範囲で単発の学びや副業にトライすることもおすすめです。家庭や本業以外に自分の「役割」や「成長の実感」があると、メンタルが安定しやすくなりますし、収入の柱が一本であることのリスクヘッジにもなります。
家事育児の偏りには「言語化」と「共有」


片働きになると、「家にいる方が家事育児をすべき」という暗黙の前提ができやすくなります。
そんなときに我が家で心がけているのは、「我慢する前に、ちゃんと伝えること」。感情的になる前に、どんなときに大変だったか、どうしてほしいかを丁寧に伝えるようにしました。逆に、パートナーの大変さにも耳を傾けることで、お互いの立場が理解しやすくなりました。
また、タスクや予定はなるべく「見える化」して一緒に管理するようにしたことで、自然と家庭内の「チーム感」が生まれました。
特に育児が大変な時期などは、家事の外注化もおススメの選択肢です。
宅配食や家事代行サービスは、以下の記事でも整理しているので気になる方は確認してみてください。
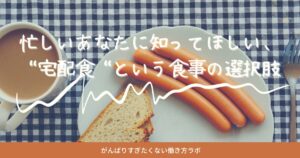
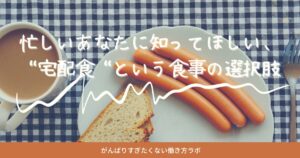
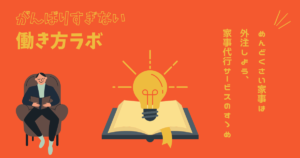
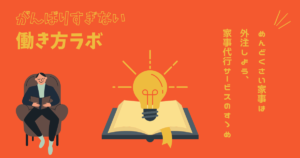
家計を見直し、パートナーと片働き/共働きについて対話しよう


片働きを考える上で抑えるポイントまとめ
- 片働きは“不利”ではなく“特徴が違う”だけ。共働きが合う家、片働きが合う家は本当にバラバラ。
- 重要なのは「何にお金と時間を割くと幸せか、ストレスが、少ないのか」を夫婦で共有し、選択に納得して協力し合うこと。
- 片働きの強み(時間・精神的ゆとり)で家族を満たし、弱み(経済・キャリアリスク)は数字と仕組みで対策――それだけで、周囲の声に振り回されない“わが家モデル”が完成します。
片働きでよいか悩むあなたが今日からできる3ステップ
固定費一覧・年間イベント費・自由時間帯を書き出す
見栄で払っている高額習い事/外食/ブランド支出/車をチェック
家計・価値観・将来不安をテーブルに乗せて「わが家プラン」を言語化
1つでも手を付ければ、片働きの“納得度”は一気に上がります!
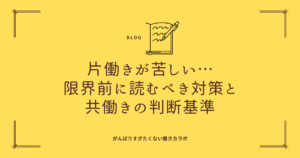
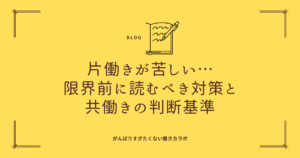
「うちはうち、よそはよそ」でいい


片働きは、ただの「経済的な選択」ではなく、家族の価値観やライフスタイルに深くかかわるテーマです。
完璧を目指さなくても、少しずつ工夫や対話を重ねることで、不安を軽くし、心地よい形に近づけていけるものだと感じています。
いま片働きを選んでいる方も、これから考えている方も、必要以上に「べき論」に縛られず、自分たちに合ったバランスを探していける…この記事が、その手助けになれば嬉しいです。
あなたの家庭の主役は、あなたとパートナーです。
世間のテンプレより、自分たちの価値観を信じてみませんか?
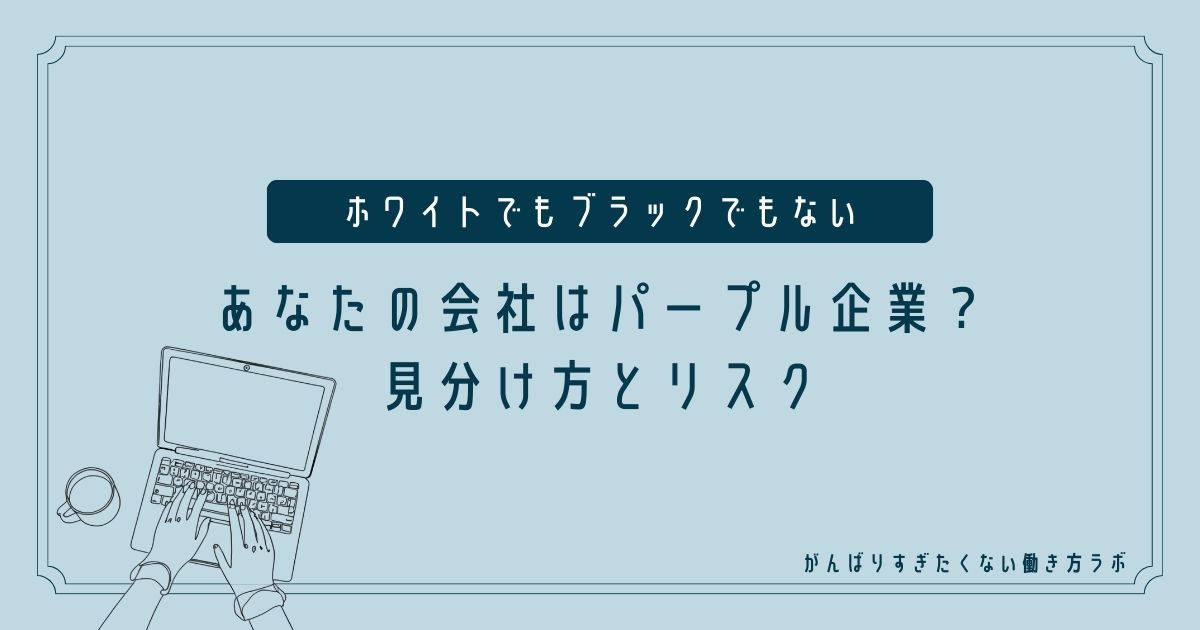
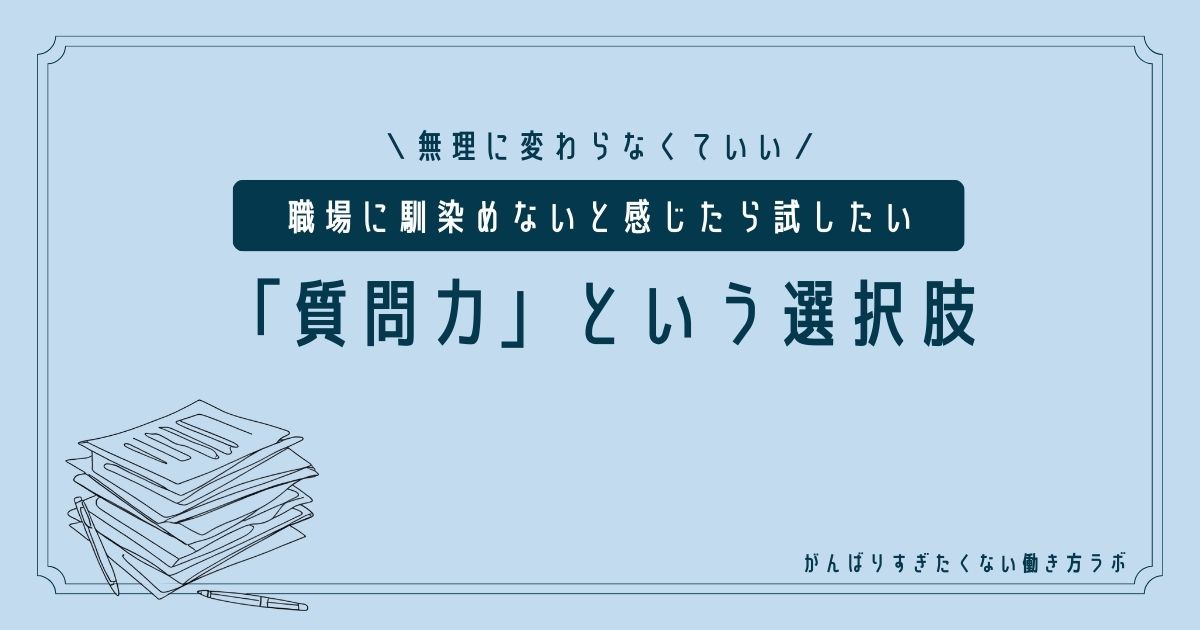
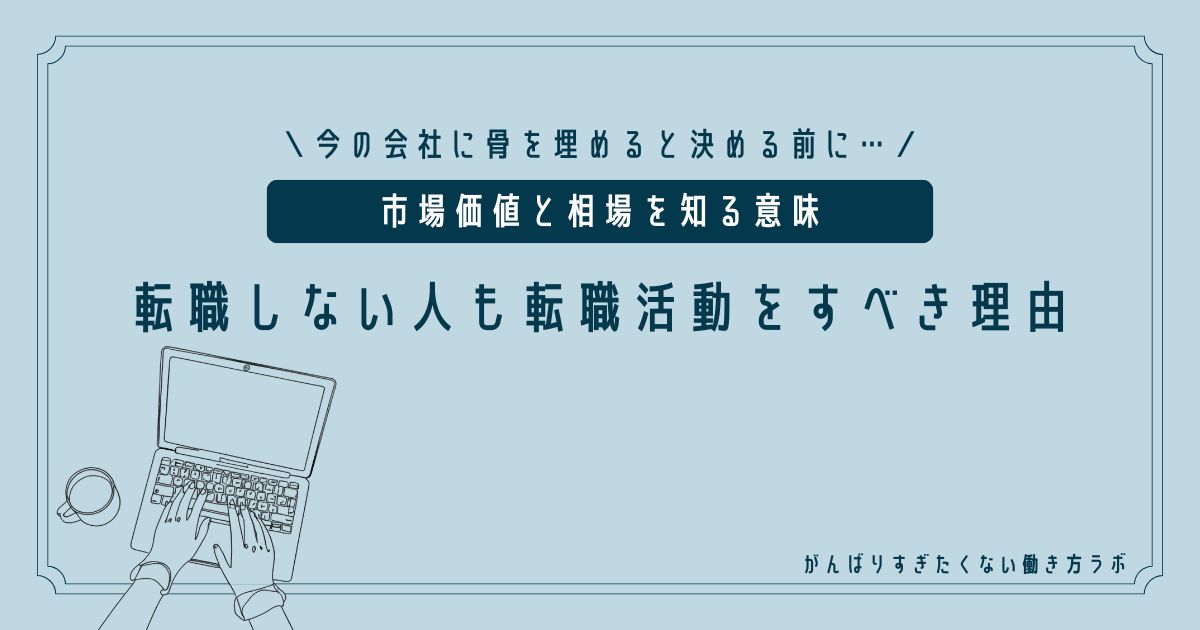
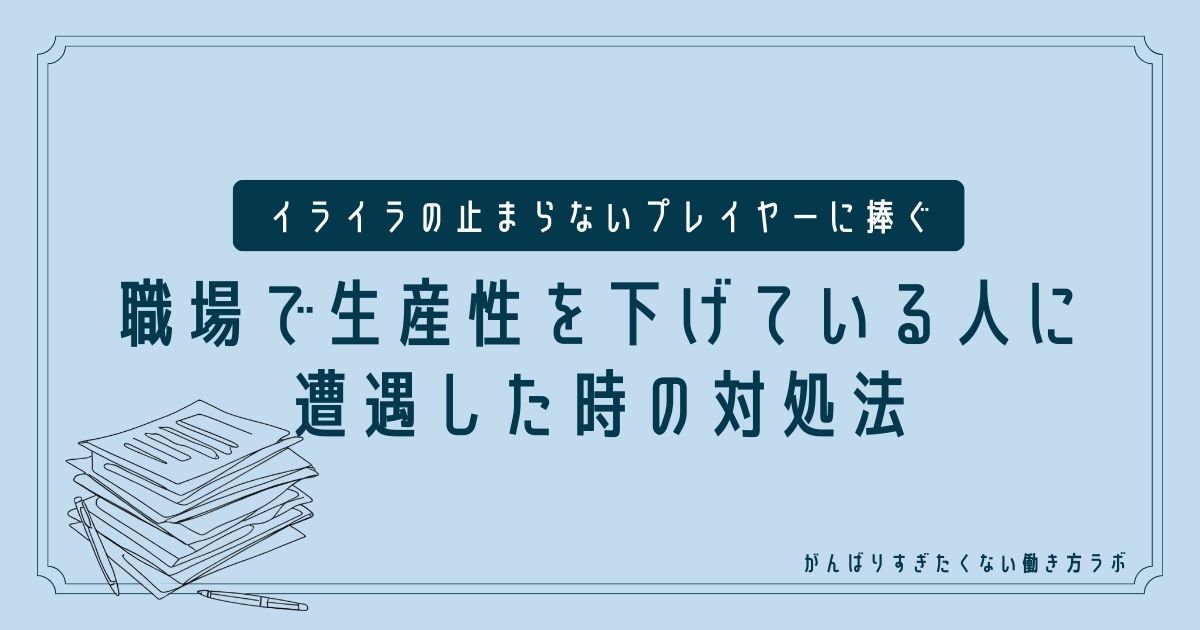
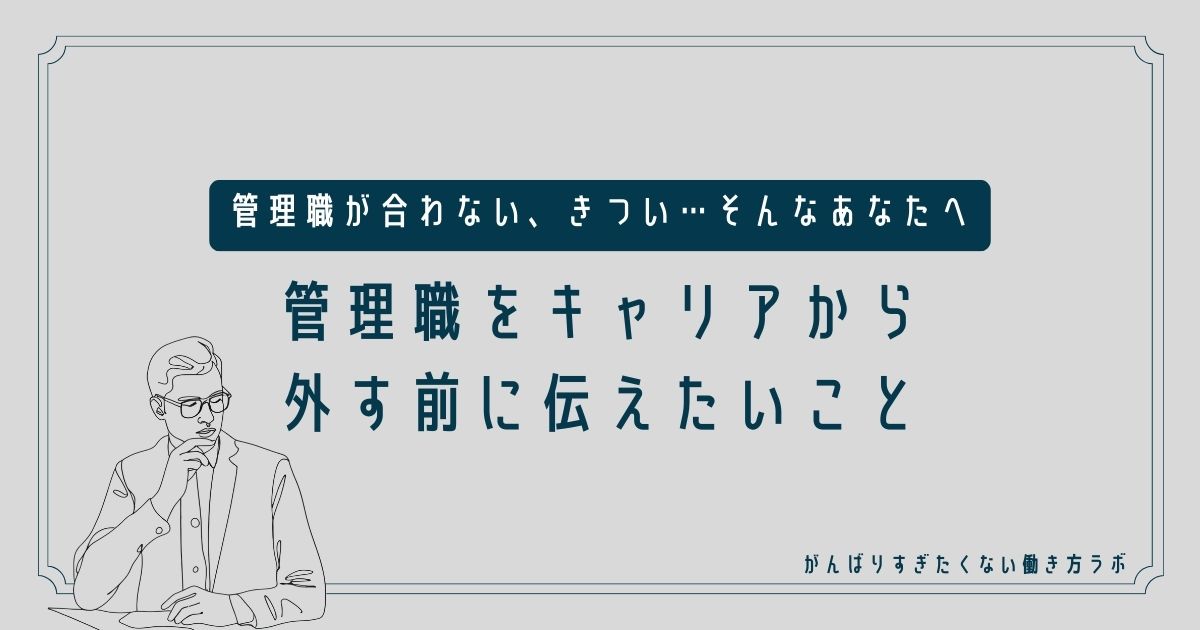
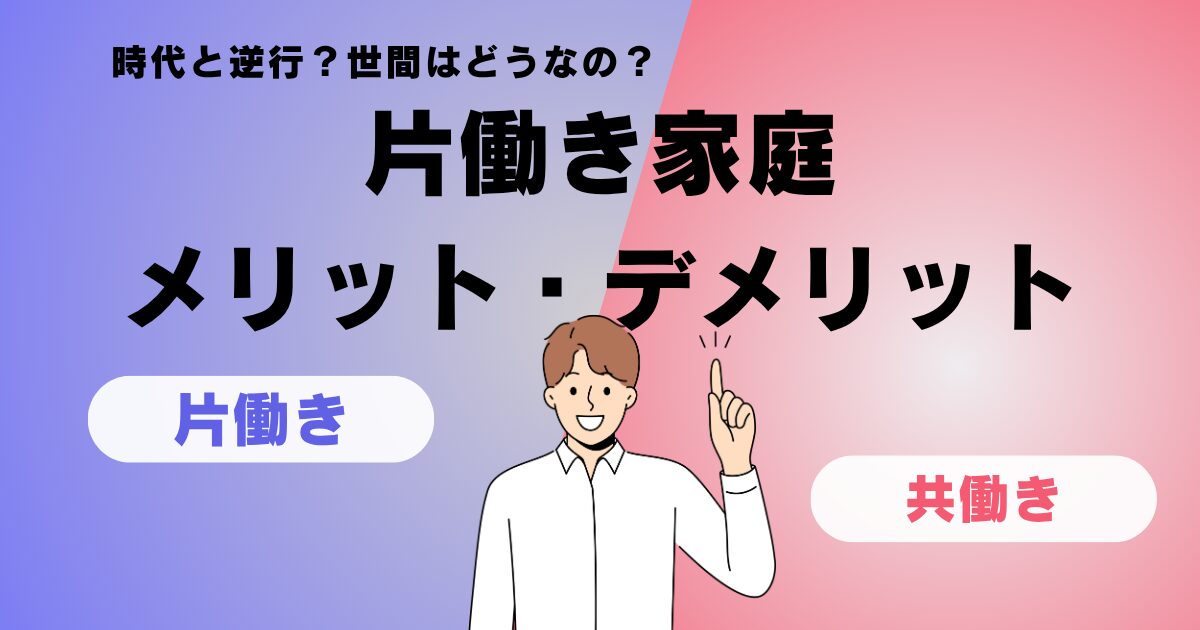
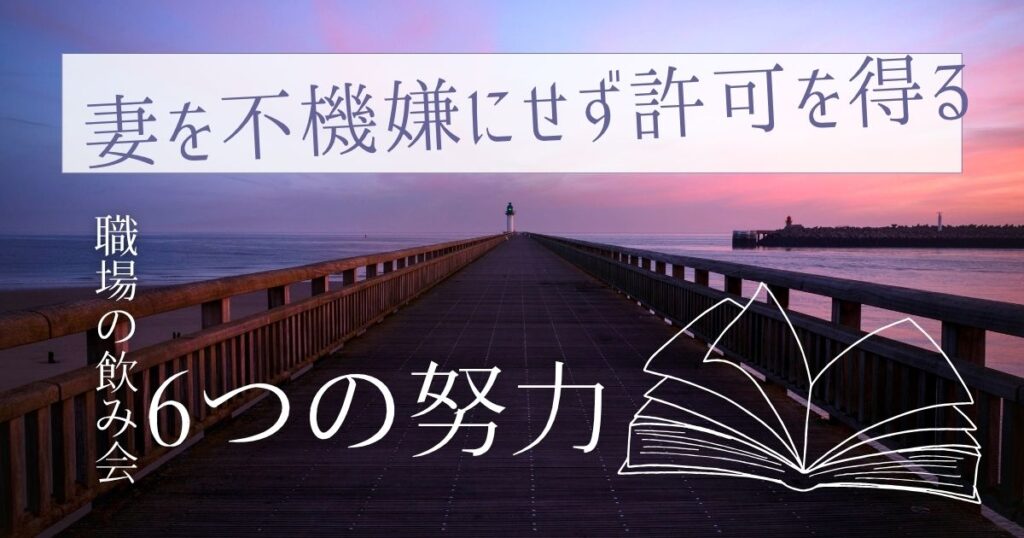
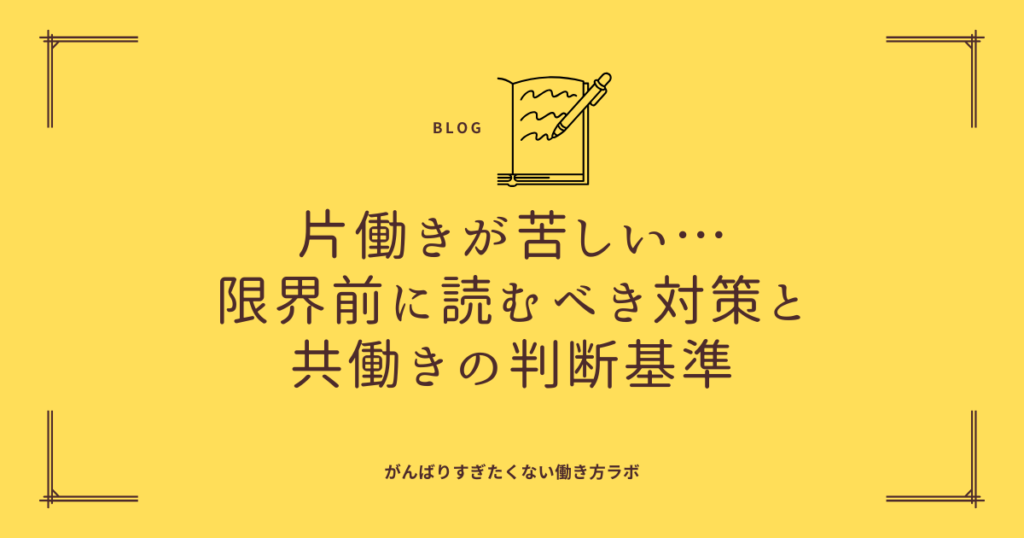
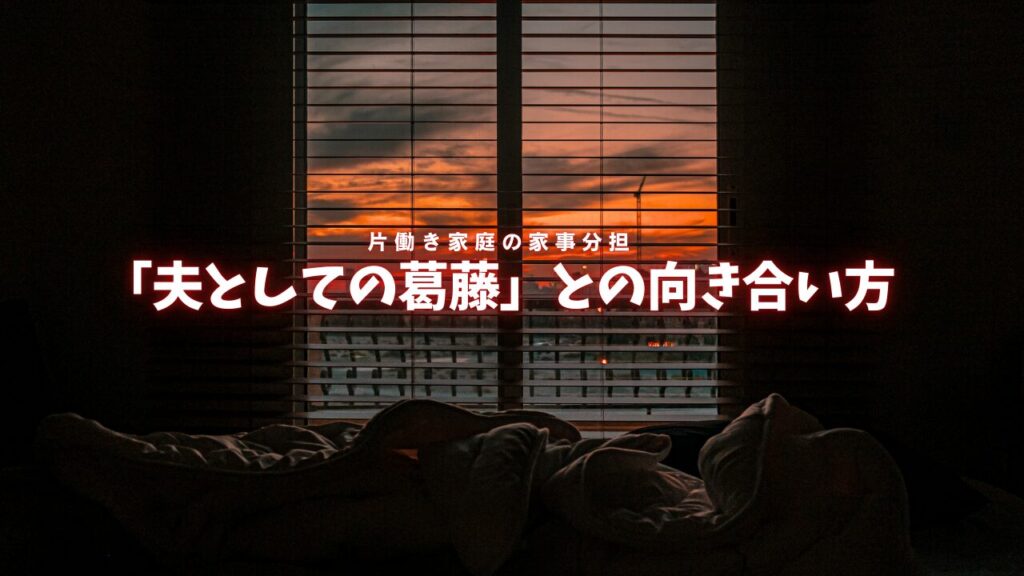
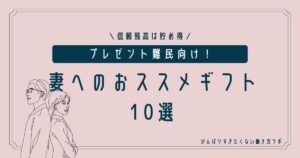
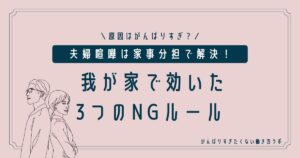
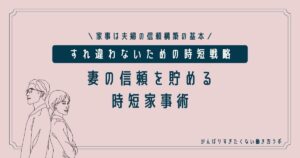

コメント