片働き家庭で家事や育児をしていると、

自分なりに頑張っているのに、パートナーからはもっとやってほしいと言われる



周りの家庭と比べられてつらい
と、モヤモヤしてしまうことはありませんか?


実際、私自身も



仕事面はともかく、家事や育児については足りないと感じられているのでは?
と不安に思うことがあります。
あなたのこのモヤモヤの正体は、単なる家事の量や頻度ではありません。
「頑張っている自分を認めてもらいたい」という気持ちにあります。
そして同じように感じている夫は決して少なくありません。
この記事では、片働き歴10年以上の筆者が、
片働き家庭における家事分担の現状と夫が抱える葛藤を整理しながら、
パートナーとの関係を建設的に進めるための具体的な方法を紹介します。
読み終えるころには、
「自分だけじゃない」と肩の荷が下り、家庭での役割に納得感を持つヒントが見えてくるはずです。
そもそも「”片働き”ってなんだろう?」…という方はこちら
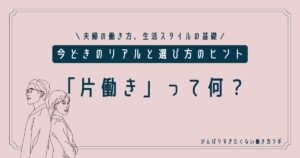
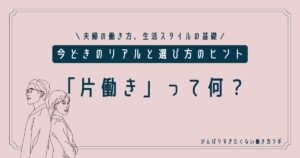
モヤモヤの正体:「もっと認めてもらいたい」
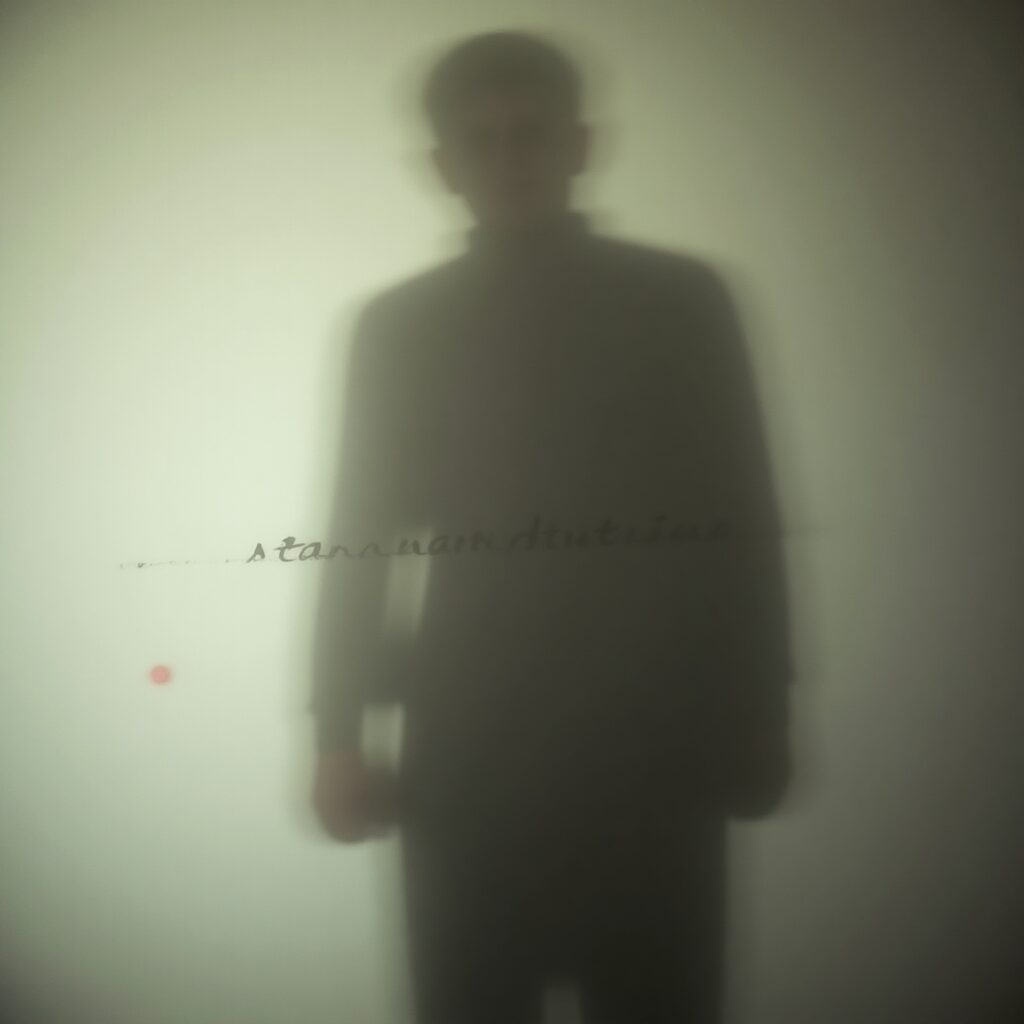
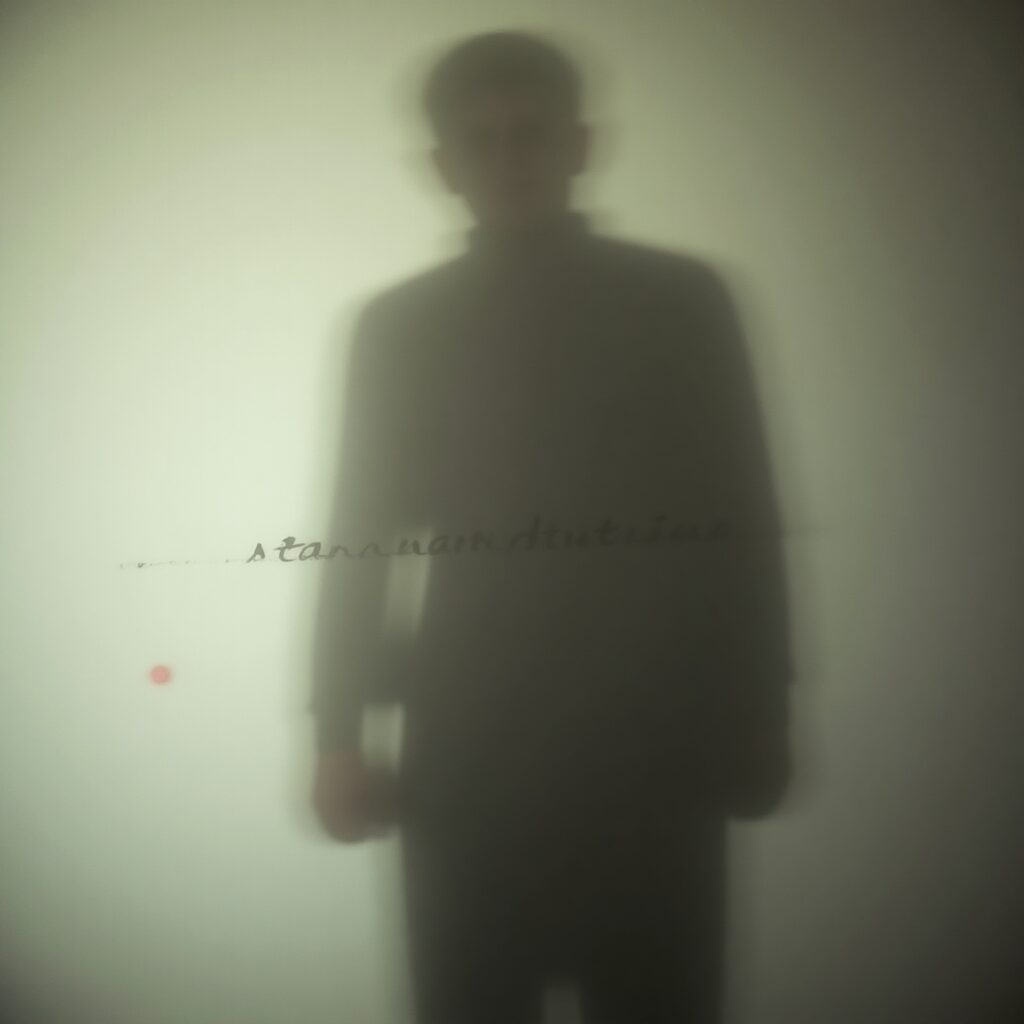
夫としては、仕事と家庭の両方を背負いながら日々努力しているつもり。
にもかかわらず、その努力が十分に伝わらないと「自分は評価されていないのでは」とモヤモヤしてしまうのです。
この気持ちの正体は「相手にもっと認めてもらいたい」という自然な欲求です。
決して自分だけが抱えているものではありません。
多くの人が同じように「頑張っていることをパートナーに伝えたい」「努力を見てほしい」と感じています。
たとえば、あなたが仕事で疲れて帰宅しても洗濯物を畳み、子どもをお風呂に入れたとします。
しかし翌日パートナーからは「もっと主体的にやってほしい」と言われる。
さらに周囲の家庭と比較した話を持ち出されると、「自分の努力は評価されていないのか」と感じてしまいます。
実際の家事量というよりも、この「認めてもらえていない感覚」こそが、心をすり減らす最大の要因なのです。
承認欲求は弱さの表れではなく、誰もが持つ健全な感情です。
むしろ「頑張っているのに伝わらない」というモヤモヤを自覚し、向き合うことが、
夫婦関係を前に進める第一歩となるのです。
家事分担に関する現状と統計データ


ここで客観的な視点から、日本における家事・育児分担の現状を分析してみます。
- 片働き世帯の家事分担
調査では「女性9割、男性1割」という回答が最多で、妻が家事の大半を担うケースが半数近くを占めています。 - 共働き世帯との比較
共働き世帯でも「女性7割、男性3割」と偏りはありますが、片働き世帯のほうが夫の家事参加がさらに低い傾向にあります。 - 夫の家事・育児時間
他の先進国と比べても、日本の男性の家事・育児時間は依然として低水準。加えて、「労働時間が長いからできない」という理由がよく挙げられますが、近年の調査では必ずしも労働時間と家事・育児参加時間の相関は明確ではないことも示されています。 - 妻の不満
国立社会保障・人口問題研究所の調査では、夫の家事参加について「不満足」と答えた妻は42.6%に上っています。
このように、構造的に「夫は家事参加が少ない」「妻はその負担に不満を持ちやすい」という状況が存在しています。
つまり、夫が「もっと認めてもらいたい」と思いやすく、妻が「もっと分担してほしい」と感じやすいのは、
社会的背景やそれに伴う周囲の環境からの声を踏まえるのは自然なことなのです。


パートナーの心理を理解する


ここまで、夫側が感じるモヤモヤの正体や、社会的背景について整理してきました。
次に大切なのは、パートナー側の心理に目を向けることです。
これは「自分が悪い」という話ではなく、パートナーがどんな気持ちで日々を過ごしているか、
なぜあなたが葛藤するようなことを言うのかを知るための視点です。
一般的に専業主婦/主夫からよく聞かれる声には、こんなものがあります。
- 「1日中子どもと一緒で、大人と会話する時間がほとんどない」
- 「終わりのない家事をやっても、感謝されることは少ない」
- 「社会から取り残されているように感じる」
- 「夫は“手伝っている”つもりでも、私からすると“お願いしないと動いてくれない”のがつらい」
- 「夫は手伝ってくれるけど、決まったことしかしてくれない。」



どの声も、わたし自身も妻から言われた経験があります
こうした声の背景にあるのは、「共感を求めている」という心理です。
仕事と異なり、家事や育児は成果が数字や形で見えにくく、しかも「やって当たり前」とされやすいもの。
ママ友やパパ友に代表される同じ立場の人間は周りにいるかも知れませんが、言ってみれば職場が別なので、本当の意味で一緒に働いているのはあなただけなのです。
だからこそ「頑張りをちゃんと見ているよ」「一緒にやっているよ」と伝わるだけで、大きな安心感につながります。


つまり「もっと手伝ってほしい」「主体性が足りない」といった言葉は、単なる不満や攻撃ではなく、
「私の気持ちに寄り添ってほしい」「共感してほしい」という心の声なのです。
ここを理解できれば、「責められている」と感じていたやりとりも、
「一緒に家庭を担っていると感じたい」という信頼のサインとして前向きに解釈できるはずです。
妻の心理を理解することは、自分の努力を否定することではなく、
「どうすればその努力が相手に伝わるか」を知ることにつながります。
そしてそれは、結果的に夫の頑張りを正しく認めてもらうことにも結びつくのです。



プレゼントもよいですが、普段やらない片付けやちょっとした掃除をする方が喜ばれるケースも多いです。
パートナーが毎日掃除する箇所ではなく、汚れや散らかりが目立ったら都度行うような場所がオススメ。
我が家だと納戸や洗面台などです。
片働き家庭の夫が抱える葛藤


相手の心理を理解した上で、改めて自分自身に目を向けると、あなた自身の葛藤が浮かび上がってきます。
表面的には「仕事を頑張っている自分」と「もっと家事や育児に関わってほしいと願う妻」という構図に見えるかもしれません。
ですがその裏には、夫自身もまた、さまざまな心理的負担を抱えているのです。
1. 罪悪感と孤独感
家事や育児に参加したい気持ちはあっても、仕事との両立が難しかったり、思うように動けなかったりする。
その結果、「自分は十分にやれていないのでは」と罪悪感を抱くことがあります。
さらに、責任感が強いほど仕事面や今後の収入面では弱音を吐けず、「自分だけが頑張っている」と孤立してしまうケースも少なくありません。
2. 「名もなき家事」への認識不足
料理や掃除など“目立つ家事”はやっているつもりでも、オムツ替え後の片付けや、
買い置きの補充などの細かい作業は気づきにくく、中々うまくやるのは難しいです。
そのため「主体性がない」と言われ、努力が伝わらずにモヤモヤが募ることがあります。



「何か買ってくるものがあったら、言って」ではなく、
「ティッシュのストックなくなりそうだけど買ってきた方がよい?」
からの「他になにかある?」にするだけで、
相手からの見え方が変わります。
3. 社会的な期待と現実のギャップ


「父親になったからこそ、しっかり働いて稼がないといけない」というプレッシャーが根強く残っています。
社会や職場の価値観も後押しし、家事・育児よりも仕事を優先してしまうことも少なくありません。
その結果、家庭での役割とのバランスが崩れ、夫婦のすれ違いを生む要因になります。
4. 妻の孤独感が自分の負担になる
妻が「ワンオペ状態」になれば、当然その不満は夫に向けられます。
夫としては「責められている」と感じがちですが、実際には妻自身の孤独感や不安感が背景にあることも多いのです。
その感情の矛先が自分に集中すると、心理的に強いプレッシャーとなります。
このように、片働き家庭の夫は「もっと認めてほしい」という気持ちと同時に、
「十分できていないかもしれない」という葛藤を抱えやすい立場にあります。
つまり、夫婦それぞれが孤独感や不安感を抱え、すれ違ってしまうのが実情です。
だからこそ大切なのは、互いの心理を理解し合い、
少しずつ「一緒にやっている」という安心感を積み重ねることなのです。
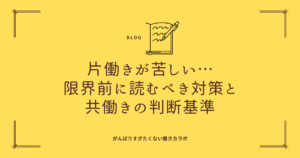
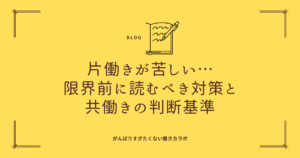
解決へのアプローチ


ここまで見てきたように、片働き家庭の家事分担には夫・妻双方の心理が絡み合い、すれ違いが生じやすくなります。では、そのモヤモヤを解消し、前向きな家庭関係を築くにはどうしたらよいのでしょうか。
実践的な工夫をもとに、建設的な解決策を紹介します。
1. 家事の「見える化」から始める
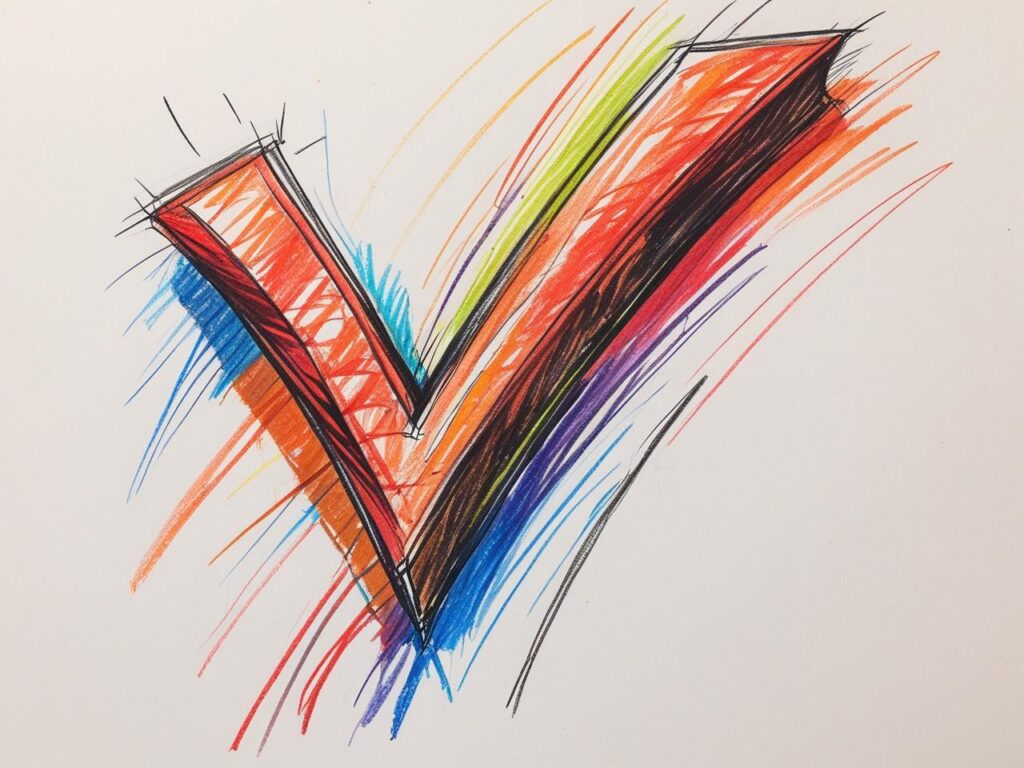
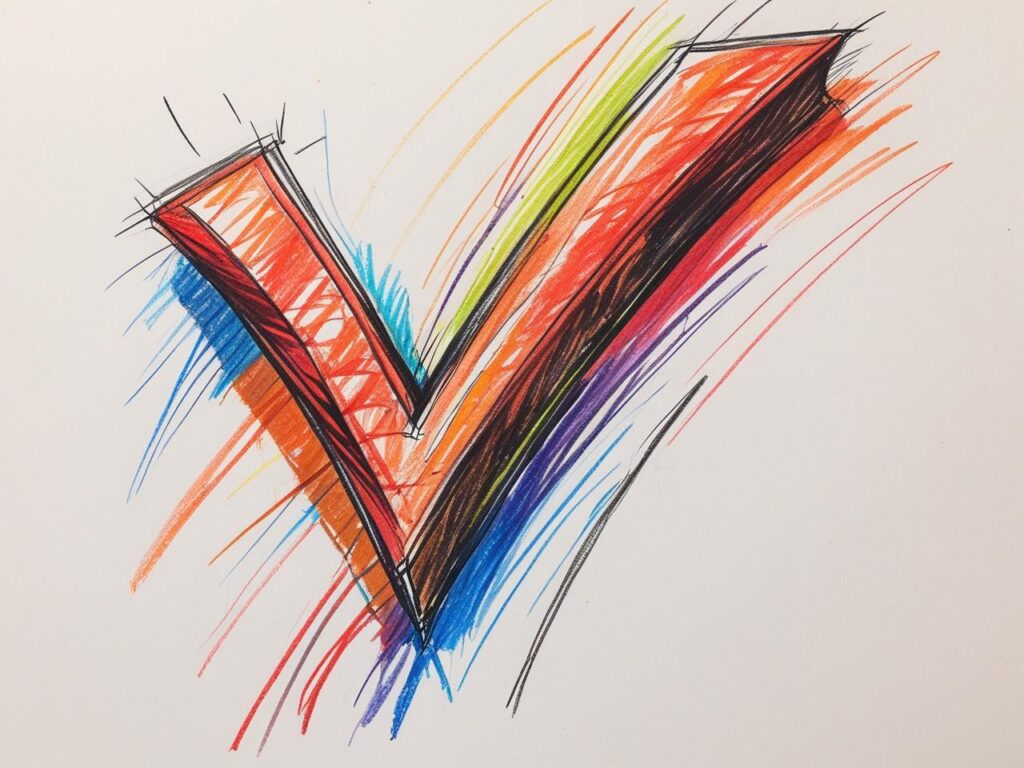
まず有効なのは、家庭内のすべての家事をリストアップすることです。
洗濯や料理といった大きなタスクだけでなく、「名もなき家事」と呼ばれる細かい作業も含めて可視化することで、
夫婦の認識ギャップが解消されます。
ポイントは「誰がどれくらいやっているか」を事実として共有すること。
責め合うためではなく、現状をお互いに客観的に確認する作業です。



いきなりパートナーと一緒に進めていくのにハードルを、感じる場合は、まずはひとりでやってみましょう。
リストアップしてみるだけでモヤモヤが晴れることもありますよ。
2. 定期的な話し合いと柔軟な見直し


一度分担を決めたからといって終わりではありません。
仕事の繁忙期や子どもの成長段階によって、家庭の状況は変化します。
月に一度でも「家族会議」のような場を設け、お互いの負担や気持ちを共有することが大切です。
このとき意識したいのは「言い方」と「聞き方」。
相手を責めるのではなく「私はこう感じている」と伝える“Iメッセージ(アイメッセージ)”を使うと、
建設的な対話につながります。



「Iメッセージ」は心理学の言葉ですが、ビジネスでも利用シーンが多いので意識的に使えると強いです
3. 得意やライフスタイルを活かす役割分担


「完璧に50:50に分ける」必要はありません。
料理が好きな人が料理を、整理整頓が得意な人が片付けを、というように得意や性格に応じた分担が納得感を生みます。
また「早く帰れる方が夕食を担当する」「朝早く出る方がゴミ出しをする」など、
生活リズムをベースに役割を決めるのも効果的です。
4. 感謝と承認の習慣をつくる


家事や育児は「やって当たり前」とされやすいもの。
だからこそ「ありがとう」「助かったよ」と言葉にするだけで、お互いの満足感が大きく変わります。
心理学の観点でも、相手の努力を認めることが、次の行動意欲を高めることが示されています。



直接的な感謝の言葉がどうしても気恥ずかしい場合は、やってもらったことを「具体的に褒める」ことをしてみましょう。
5. 外部サービスを味方につける
どうしても解決が難しい場合には、外部のサポートを利用する選択肢もあります。
家事代行サービスや時短家電の導入は、夫婦の関係を守るための「投資」と考えることができます。
頑張りだけで解決しようとせず、無理を減らすことも建設的な方法です。



全てを外注しなくて大丈夫です。
月一でプロに掃除してもらうと日々の掃除の負担はグッと減りますし、冷凍庫にちょっとリッチな宅配食を備えておくだけでお互い忙しいときの選択肢に備えられますよ。
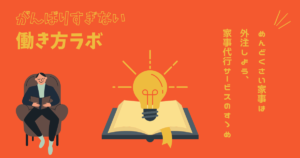
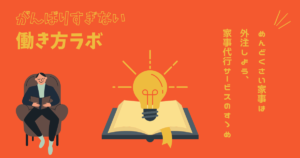
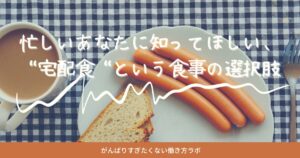
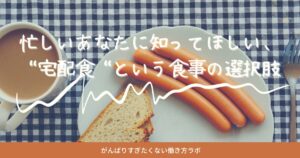
このように、家事分担を「競争」ではなく「協力」に変える工夫はたくさんあります。
大切なのは、完璧を目指すことではなく、「一緒に進めている」という実感をお互いが持てることです。
その積み重ねが、夫婦の信頼と安心感を育てていくのです。
互いを認め合える家庭に


片働き家庭における家事分担のモヤモヤは、夫だけ、妻だけ、に閉じた問題ではありません。
社会的な期待、働き方の違い、そして「認めてもらいたい」「共感してほしい」という気持ちのすれ違いが、
複雑に絡み合っています。
仕事を頑張って、家事育児もしているのに十分に評価されない…
日常の小さな負担に共感し、分かち合ってほしい…
その両方の思いに共通しているのは――「お互いを理解し、認め合いたい」という心からの欲求です。
モヤモヤを乗り越えるための第一歩は、自分自身の気持ちを言語化すること。
何に不満を感じ、何を認めてもらいたいのかを整理することで、冷静に状況を見つめ直せます。
その上で、夫婦で家事の「見える化」を行い、定期的な対話の場を持つことが大切です。
大事なのは、完璧な分担や理想像を追い求めることではありません。
小さな工夫や「ありがとう」の一言が、信頼と安心を積み重ねていきます。
ときには外部の力を借りたり、家庭でやらないことを決めても構いません。
家庭を守ることは「一緒に取り組むプロジェクト」なのです。


あなたのモヤモヤは、決してあなただけのものではありません。
多くの家庭で同じような葛藤が起きている「当たり前」であり、自分を責める必要はありません。
むしろその葛藤を「より良い関係を築くきっかけ」として捉えてほしいです。
最終的に大切なのは、夫婦が協力しながら柔軟に役割を調整し、家族全体で支え合う姿勢です。
小さな一歩の積み重ねが、やがて大きな安心感と円満な家庭をつくっていきます。
この記事が、モヤモヤ解消だけでなく、
あなた自身が納得して仕事や家事に取り組めるきっかけになれば嬉しいです。
本記事は以下の資料を参照しています。
『「家事・育児の分担割合」実態調査』 (エン・ジャパン)
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2024/35802.html『男女共同参画白書 令和2年版 コラム1「男性の家事・育児参画の現状」』 (男女共同参画局)
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/html/column/clm_01.html『社会生活基本調査に見る、家事・育児の時間差』 (WingArc DATA INSIGHT)
https://data.wingarc.com/balancing-household-work-30491『世界と比較した日本の「無償労働時間」』 (All About)
https://allabout.co.jp/gm/gc/487324/『第15回 出生動向基本調査(夫婦調査)』 (国立社会保障・人口問題研究所)
https://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou15/NFS15_reportALL.pdf
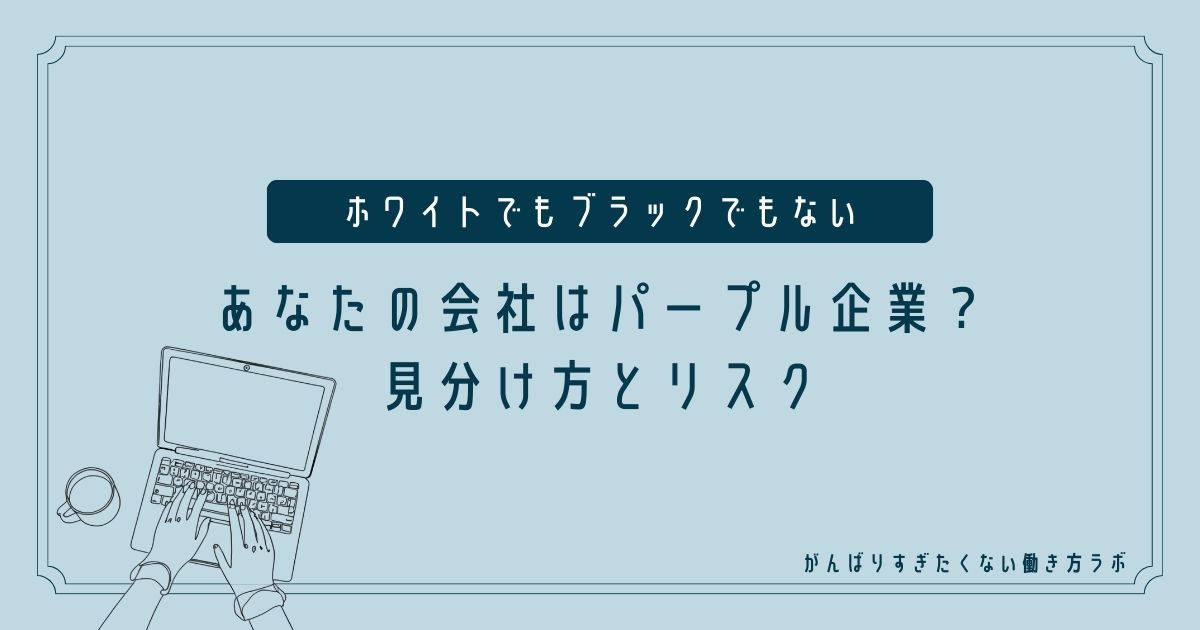
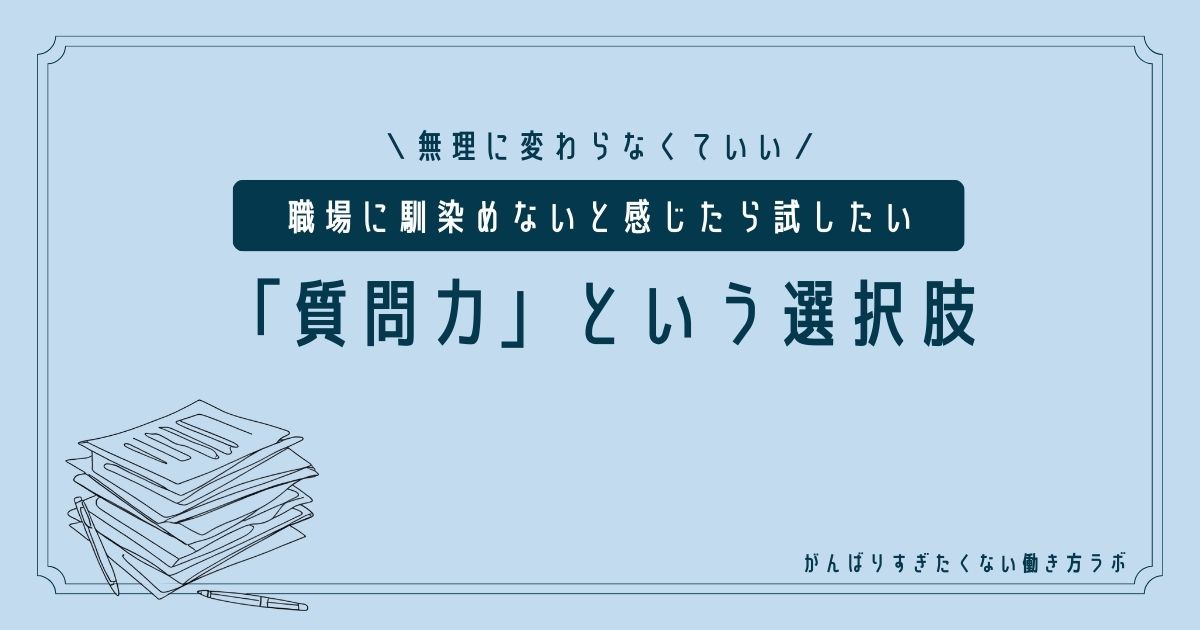
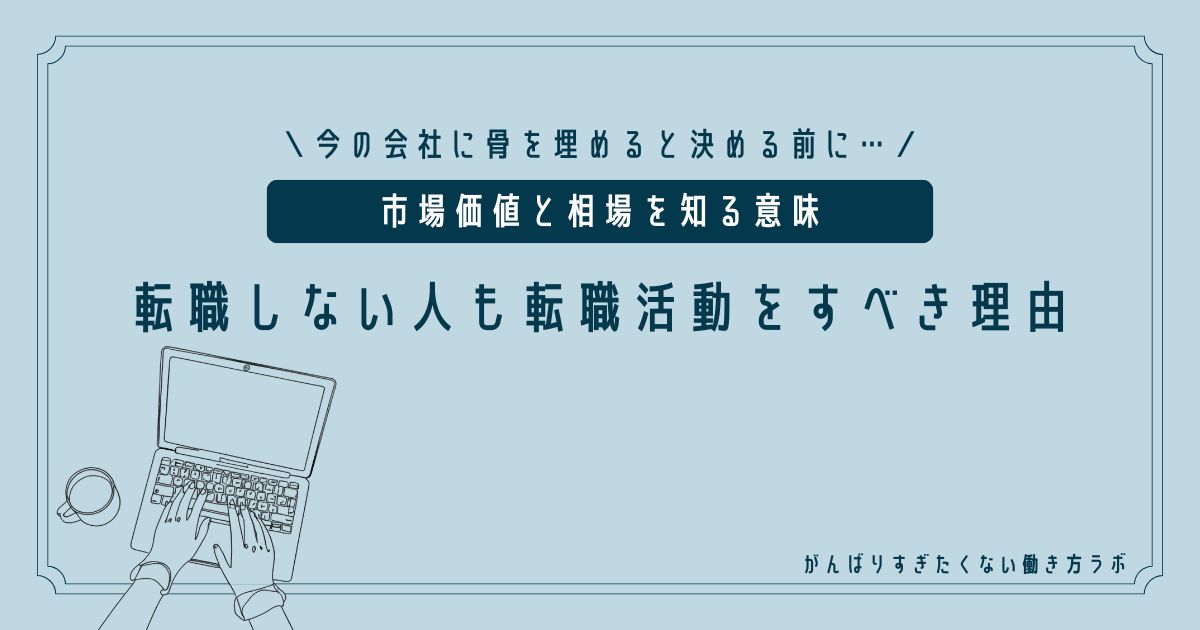
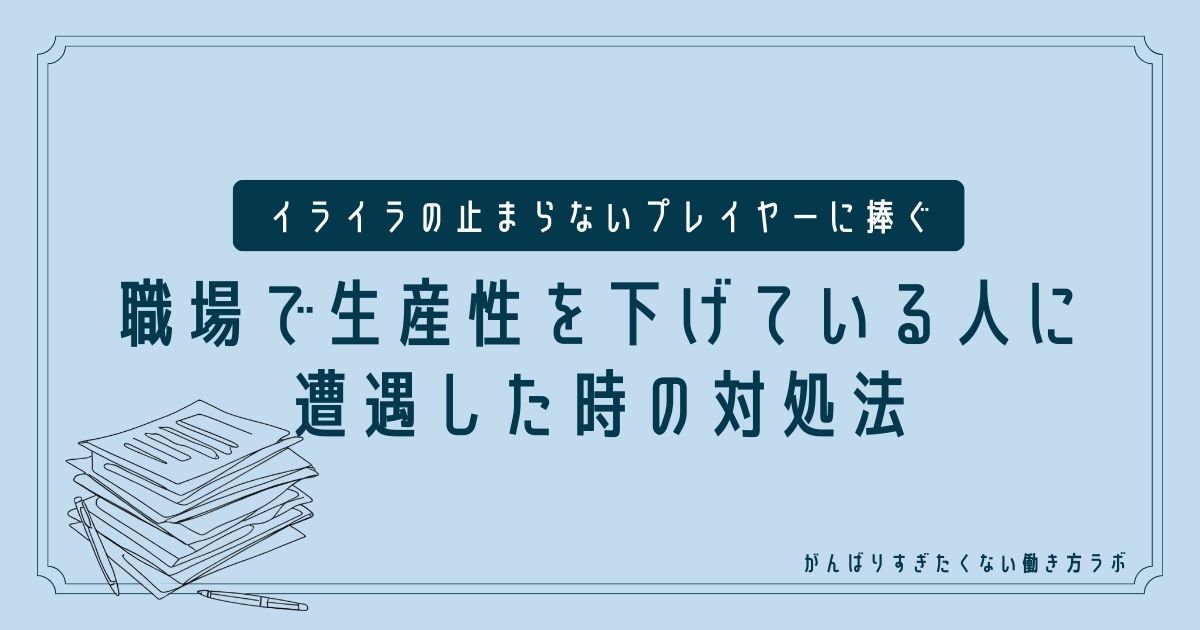
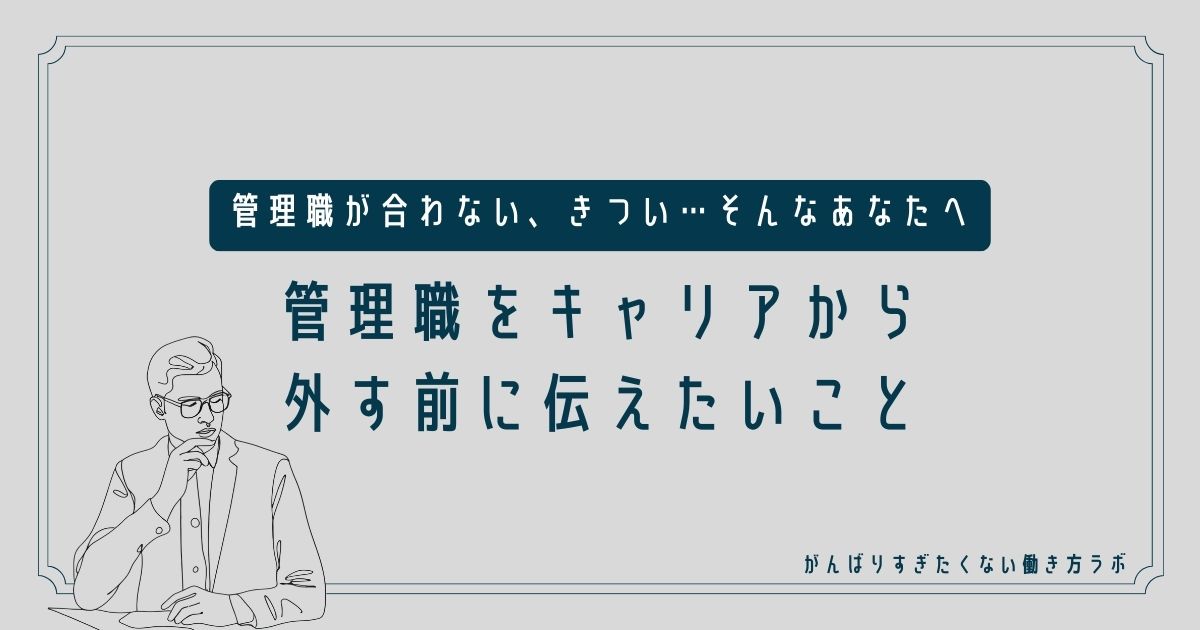
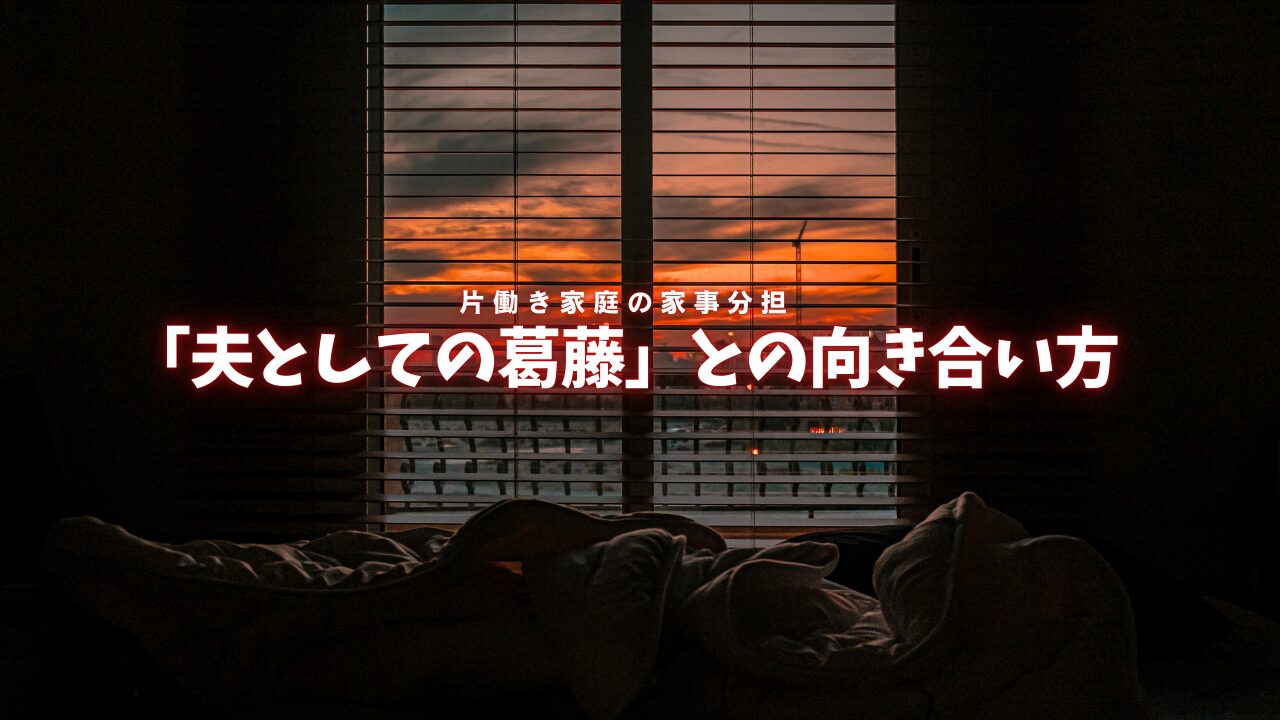
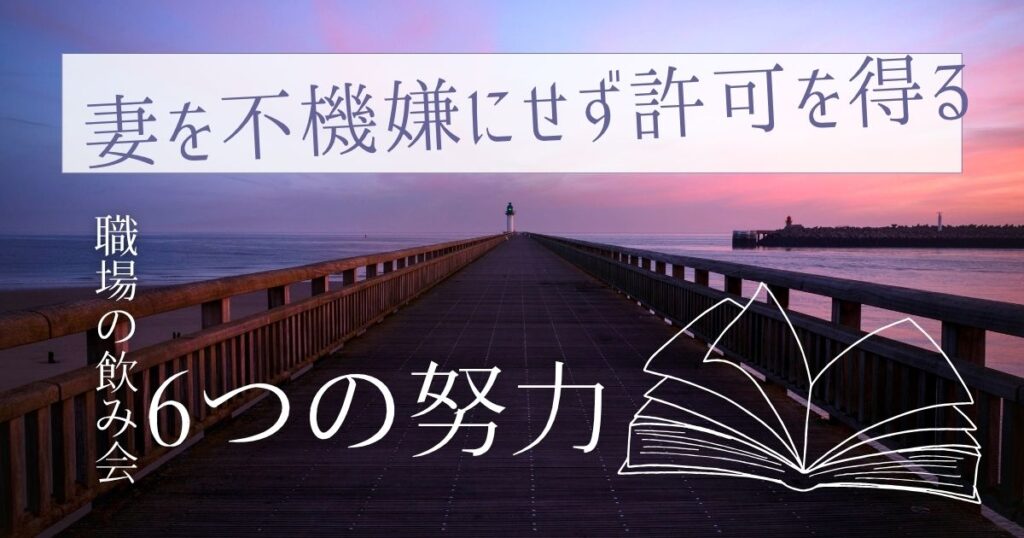
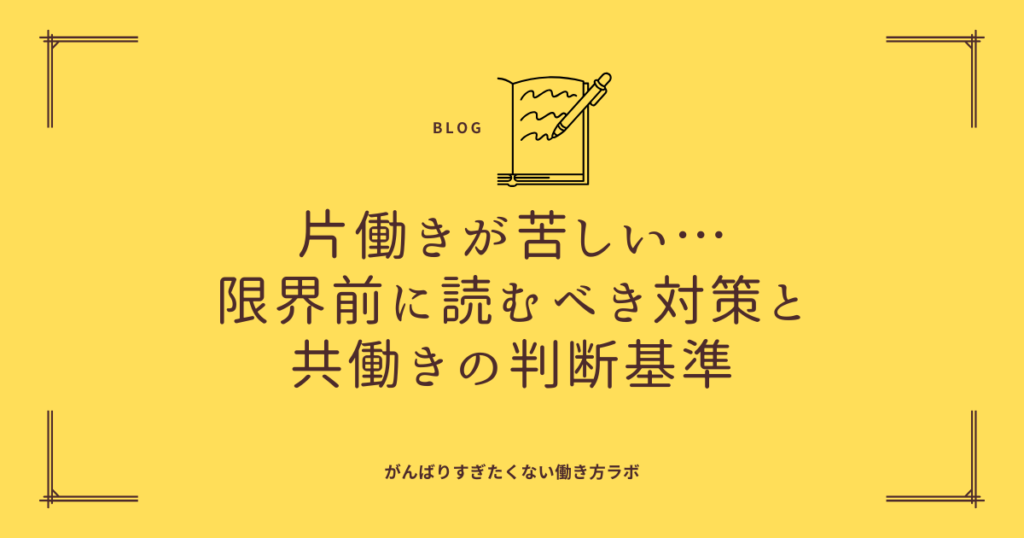
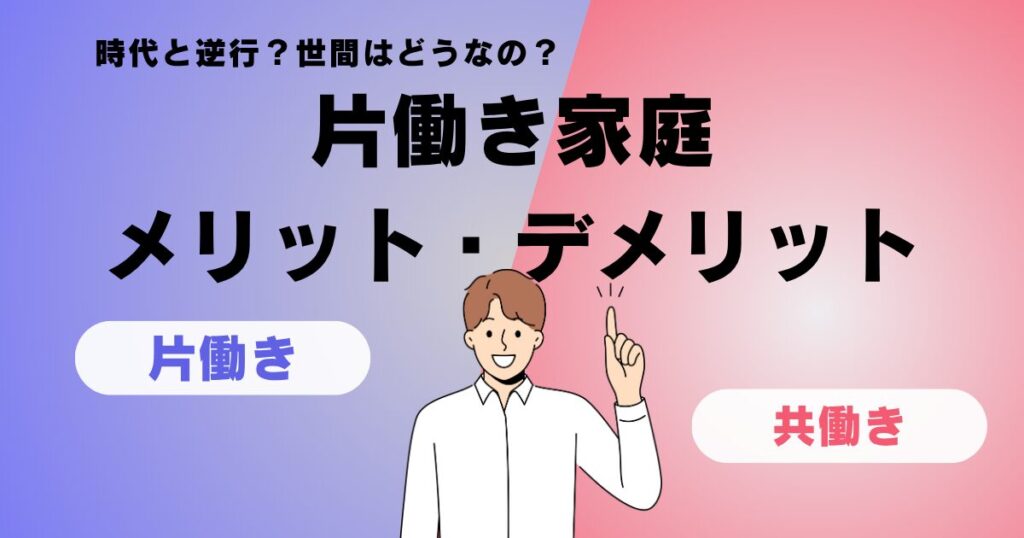


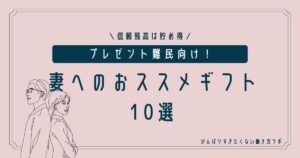
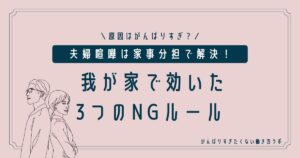
コメント