仕事では数字や事実を整理して話すのは得意なのに、
いざ自分の気持ちを伝えようとすると言葉に詰まってしまう──
そんな経験はありませんか?

なんとなくモヤモヤするけれど、うまく説明できない…



言葉にできないせいで、相手に誤解される



感情を抑え込んでしまい、ストレスだけが残る
感情を言語化するのが苦手だと、職場でのコミュニケーションに小さなズレが積み重なり、
関係づくりや仕事の進め方に影響が出ることもあります。
何よりそれらの積み重ねがストレスとなり、あなたの精神をすり減らしていきます。


ですが安心してください。
感情の言葉にする力は、特別な才能ではなく「トレーニングで磨けるスキル」です。
この記事では、幼い頃から読書感想文が大の苦手で社会人時代までそれを引きずりながらも、
職場でのコミュニケーション方法で試行錯誤を繰り返し、管理職までたどり着いた筆者が、
感情を言語化するのが苦手な人が、職場で実践できる改善法・対処法をわかりやすく紹介します。
読み進めて、小さな一歩を積み重ねれば、仕事も人間関係もぐっとスムーズになりますよ。


なぜ感情を言語化するのが苦手なのか
感情をうまく言葉にできないのは、決して珍しいことではありません。
多くの人が抱える共通の課題であり、いくつかの背景があります。
1. 感情語彙の少なさ


感情を言葉にするには、「どんな感情が自分の中にあるか」を認識できる必要があります。
しかし、そもそもその“感情の名前”を知らなければ、うまく言葉にできません。
多くの人は「嬉しい」「悲しい」「イライラする」「疲れた」など、限られた語彙の中で感情を処理しています。
けれど実際には「焦り」「戸惑い」「不安」「失望」「虚しさ」「安心感」「満足感」など、
もっと細やかな感情が存在します。
たとえば、「イライラしている」と思っていた気持ちが、
実は「不安」と「焦り」の混ざった状態であることも少なくありません。
語彙が少ないと、そうした感情のグラデーションを認識できず、
「なんとなくモヤモヤする」としか表現できなくなります。
さらに、感情が激しく動いたとき──たとえば怒りや不安が強いとき──は、
脳の思考領域が一時的に機能しにくくなります。
そのため「感じているけれど言葉が出てこない」状態になり、思考や言葉が追いつかないのです。


2. 感情より理屈を優先してきた習慣


もう一つの理由は、社会や環境の影響です。
多くの人は学生時代や職場で、「感情よりも理屈が大事」「論理的に説明できる人が優秀」という価値観の中で
育ってきました。
その結果、「感情を出すことは未熟なこと」「職場で感情を見せるのは恥ずかしい」と感じるようになり、
無意識に抑えるクセが身についてしまいます。
また、感情を共有する経験そのものが少ないというケースもあります。
他者と感情を分かち合う機会が少ないまま大人になると、
「何をどの程度話していいのか」「どう表現すれば角が立たないか」がわからず、
慎重になりすぎて言葉を選べなくなります。
さらに、内面で考える時間が長い人ほど、頭の中では整理できていても、
それを外に出す訓練が足りないことが多いです。
つまり「考えること」は得意でも、「伝えること」に慣れていないため、口に出すときに詰まってしまうのです。
加えて、「自分の感情を言葉にすること自体が苦手」という意識を持っている人も少なくありません。
「どうせ上手く言えない」「変に思われるかも」と思うと、最初の一言が出てこない。
そうした自己抑制の習慣が、言語化のハードルをさらに上げてしまいます。
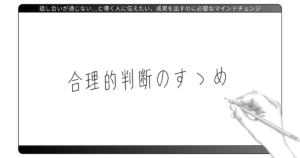
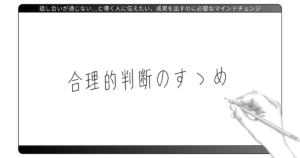
3. ネガティブな反応を恐れる


そして最も根深い理由の一つが、「他人の反応に対する恐れ」です。
感情を言葉にするとき、人は無意識に「相手にどう思われるか」を気にします。
そのため、恥ずかしさや失敗・批判への恐怖が先に立ち、「言わないほうが安全だ」と感じてしまうのです。
たとえば、意見を伝えたい場面でも「間違っていたらどうしよう」「反論されたら嫌だ」と考えるあまり、
感情を抑え込んでしまう。
こうした心理的なブロックは、特に真面目で責任感の強い人ほど起こりやすい傾向があります。
また、自己肯定感が低い人は「自分の気持ちを出したら嫌われるかも」「迷惑をかけたくない」と感じやすく、
言葉を選ぶうちに結局伝えられなくなります。
さらに、過去に対人関係で否定された経験やトラウマがある場合、「また傷つくのでは」という恐怖から、
感情表現そのものを避けてしまうこともあります。
「前に否定された」「感情を出したら笑われた」──そうした記憶が、
“黙ることが安全”という自己防衛反応につながっているのです。
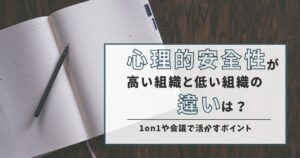
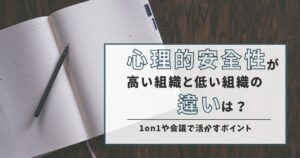
感情表現が苦手で会社員が被る不利益


- コミュニケーション
- 関係構築
- 周囲からの評価
- 自己肯定感
これらは感情表現がうまくいかないことによる直接的な不利益ですが、この状態が続くことで、
長期的には他にもさまざまなリスクが生じます。
モチベーションが低下して仕事そのものへの意欲を失いやすくなったり、
周囲からのフィードバックや支援が得にくくなって成長の機会を逃したりすることもあります。
さらに、「言語化できない=無能」といったレッテルや、ハラスメントが起こりやすい職場環境では、精神的な苦痛が増すおそれもあるでしょう。
こうした不利益を避けるためにも、感情や考えを適切に言葉で表現する力は、会社員にとって欠かせないスキルです。



適切な感情の言語化は、単純なコミュニケーションの技術としてだけでなく、幸福感の増加やストレスの軽減にもつながるセルフコントロールの側面も持っているのです。


感情を言語化するための改善法
感情を上手に言葉にするには、特別な才能や深い心理学の知識は必要ありません。
ここでは、職場で実践できるシンプルな方法を紹介します。
感情の原因を短く書き出す


言葉に詰まるときは、頭の中で考えすぎていることが多いものです。
そこで有効なのが「書き出し」トレーニングです。
A4用紙やノートに、テーマを決めて制限時間(1分など)を設け、
頭の中の思考や感情をひたすら書き出してみましょう。
書いた内容は読み返さなくても構いません。
目的は“整理”ではなく、“アウトプット”です。
頭の中がスッキリし、自然と感情の輪郭が見えてきます。



スマホのメモでもよいですが、「吐き出した」感のでる真っ白な紙やノートがおすすめです。
SNSで発信する


自分の意見や気づき、感情を文章として書き、発信してみましょう。
反応やコメントで得られるものはもちろんありますが、「他人の目に触れる」という緊張感自体が、
あなたの文章力やアウトプット力を成長させてくれます。
特にTwitter(現X)のような短文投稿では、140字以内で要点をまとめる力が鍛えられ、
「伝える本質」に集中する練習になります。



筆者もひっそり発信していますので、
よければフォローしてください。
読書の習慣をつける
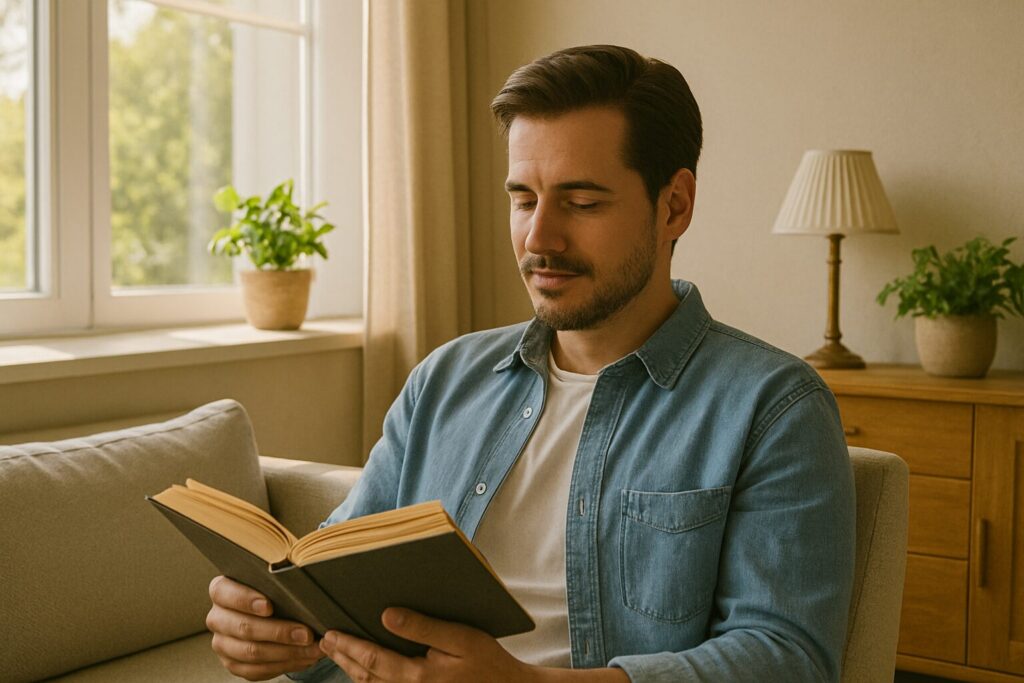
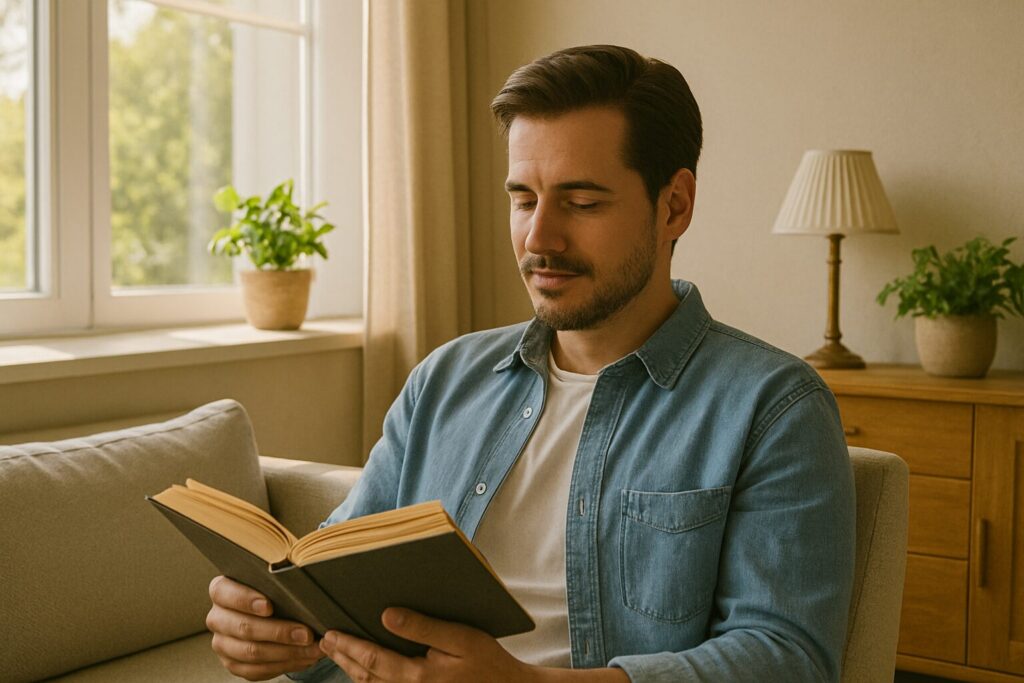
古典的ですが、語彙を増やす最も効果的な方法の一つは読書でしょう。
個人的な主観も入りますが、動画や音声でのインプットは思っている以上に「雰囲気」で
感じ取っている割合が多く、扱うワードのバリエーションを増やすには「活字」が有効なのです。
特に小説やエッセイは、人の感情描写や心の機微を言葉にする表現の宝庫。
感情表現のストックを増やすことで、自分の内面をより的確に言語化できるようになります。



小説などが苦手な場合は、新聞やビジネス書から入る形でもOK。
とにかく「音」ではなく「文章」としての言語を、生活に増やすところから始めましょう。
信頼できる人と意識的に”会話”する
職場の同僚や友人など、気軽に話せる相手に感情をアウトプットする練習を重ねると、
言語化の力が少しずつ身についていきます。
そもそも人と会話すること自体に慣れていない人におススメです。



パートナーと近しい相手とは、短い単語のみでコミュニケーションが成立してしまいがちです。そこを意識して正しい言語ルールや、自分の感情も言語化して話してみると、思った以上に効果的な訓練になりますよ。
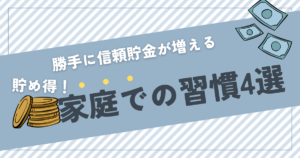
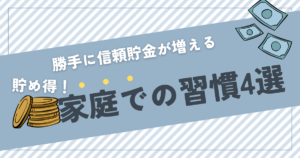
「なぜ?」で深掘りして言葉を磨く


普段の仕事で「熱中できた」「依頼する」と感じた時、必ず「なぜそう感じたのか?」を考えてみましょう。
理由を掘り下げることで、より具体的で再現性のある言語化ができるようになります。
日報・週報・ブログなどの定期的なアウトプットに組み込むのもおすすめです。
人に見せる前提で書くと、自然と構成力や精度も高まります。



感情の言語化は“筋トレ”に近いイメージです。
日々の生活に小さなトレーニングを取り入れ、継続することで、
自分の感情を正確に捉え、伝える力は着実に鍛えることができるのです。
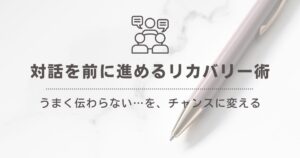
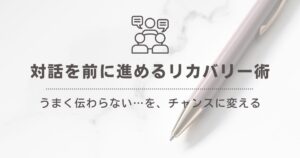
それでも苦手…という人向けのテクニック


これまで感情表現が苦手な人の理由と改善方法を説明してきましたが、
「それでも、どうしても苦手…」という人もいるでしょう。
そんな場合の、会社員としての社会性を発揮できる工夫を紹介します。
書いてから伝える
メールやチャットでまとめて送る。書く時間がある分、感情や考えを整理でき、伝えやすくなります。
文字にすることで冷静さも保てるので、口頭が苦手な場合は文章で補うことも大事です。
口頭でのコミュニケーションが必要な場合もメモや箇条書きで要点をまとめてから話すことで、
事前準備が心理的負担を軽減し、自信を持って話せる助けになります。
まずは事実を伝える
感情を言葉にできなくても、起こった出来事や状況を具体的に述べることで、誤解を防ぎやすくなります。
事実ベースの説明は相手も理解しやすいですし、自分も事実を言葉にすることで頭の中や自分の感情が整理され、
次につながり易くなる効果もあります。
非言語コミュニケーションの活用
表情やジェスチャー、うなずきなどで相手の話に反応を示し、感情のニュアンスを伝える補助手段として利用します。



私も普通にしていると”ドライ”と受け取られることが多いです。
部下への寄り添いで共感力や、クライアントへの提案でパッションが求められる場合は、オーバーリアクションととられるぐらいの身振り手振りを行うようにしています。
素直に時間が必要であることを伝える



今時点ではわかりません、考え中です。



すみません、整理できていないので、後でメールで送る形でよいですか
感情や考えが整理できないときは「今はうまく言葉にできません」や「もう少し考えたいです」と率直に伝え、
時間や余裕をもらうのも有効な戦術です。
言葉にすることで、世界は少しずつ変わる


感情を言葉にすることは、自分自身を理解することでもあります。
どんなに理性的で冷静な人でも、感情の影響を受けずに仕事を進めることはできません。
むしろ感情をうまく扱える人ほど、周囲との信頼関係を築き、合理的に仕事の成果を高めていけるのです。
最初は、思ったように言葉が出てこなくても構いません。
紙に書く、短く話す、人に伝えてみる──そんな小さな積み重ねが、少しずつ“言葉の筋力”を育てます。
続けていくうちに、「うまく言えない」モヤモヤが減り、
対話の場でも自分の感情を落ち着いて伝えられるようになるでしょう。
感情の言語化は、多くの人が悩む課題であり、誰にでもできるスキルでもあります。
このスキルは、あなたの心を守り、仕事や人間関係をより豊かにしてくれる大きな武器になります。
焦らず、今日からできる小さな一歩を始めてみましょう。
この記事が、あなたが一歩目を始める手助けになれば嬉しいです。
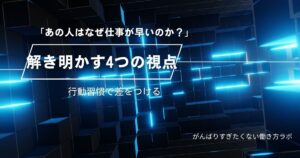
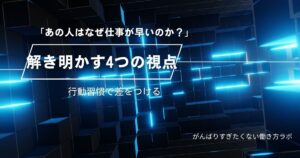
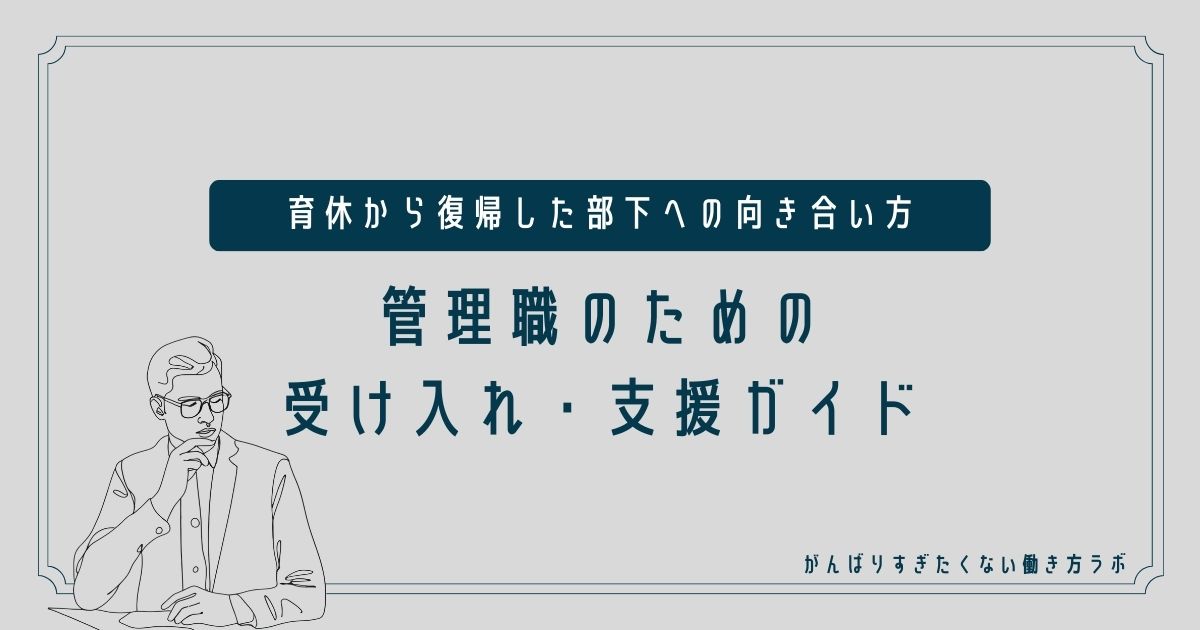
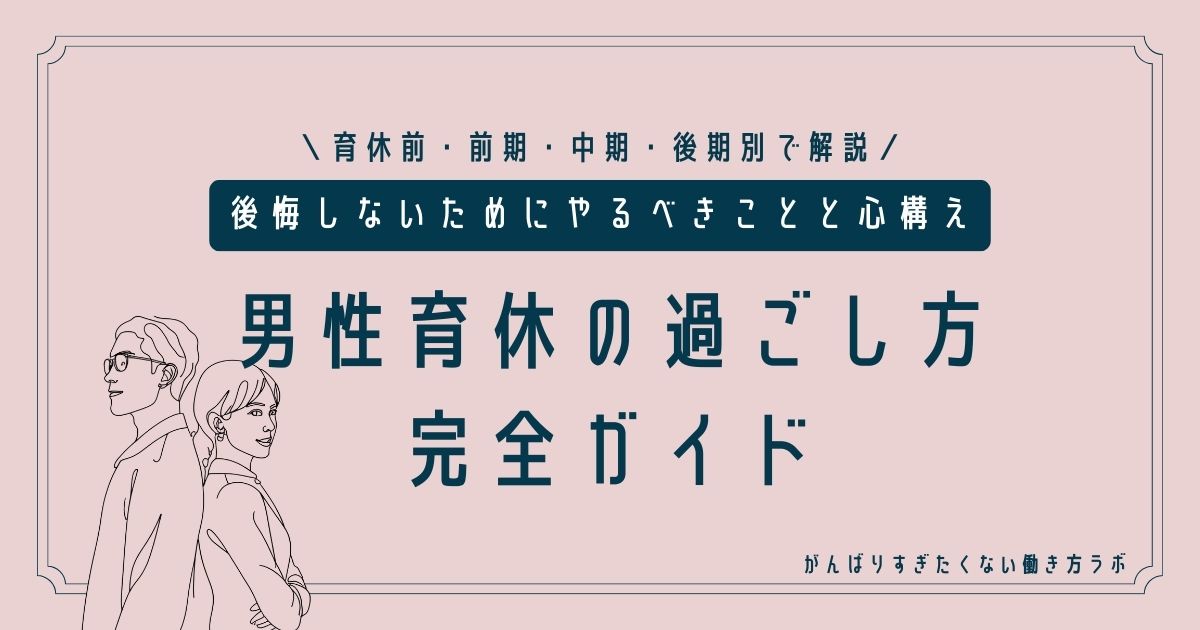
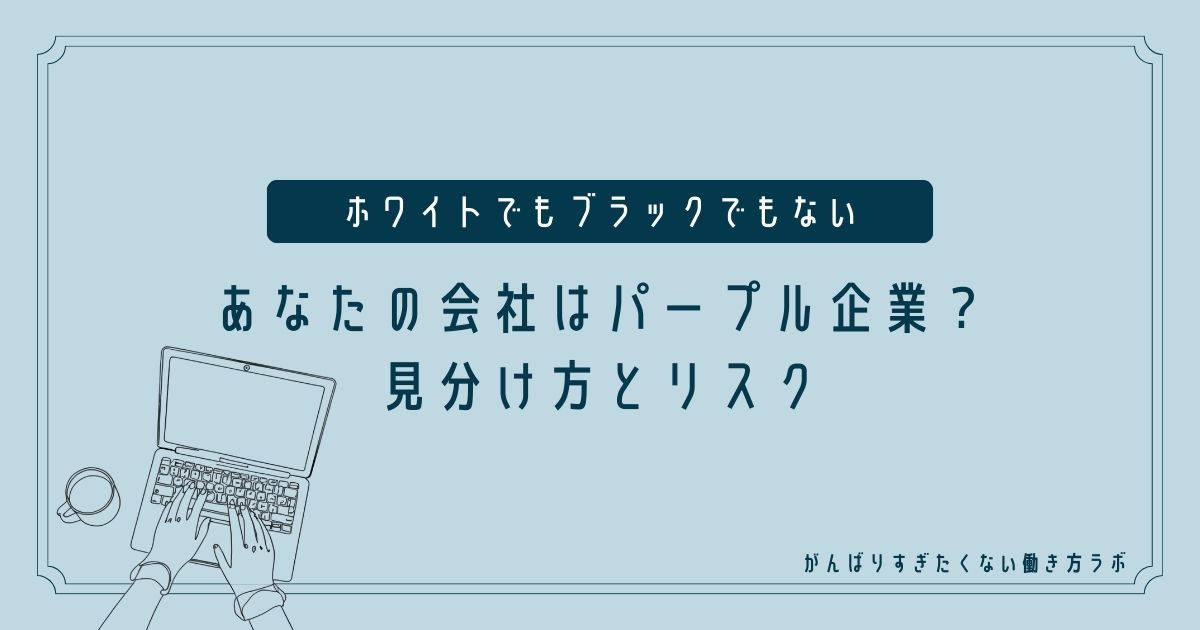
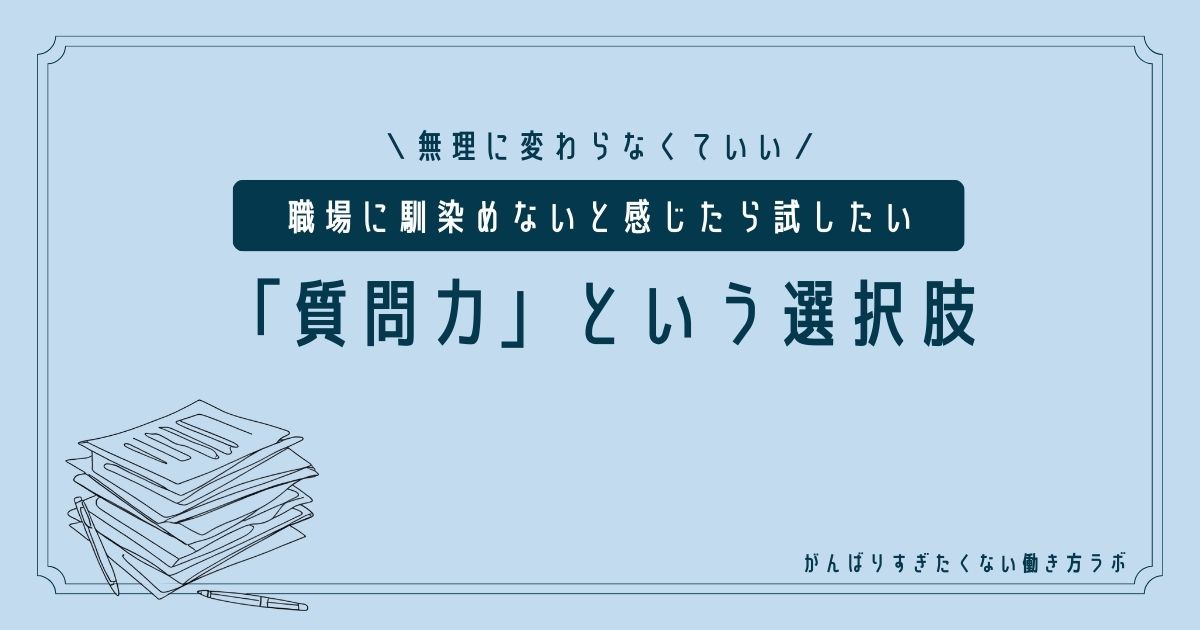
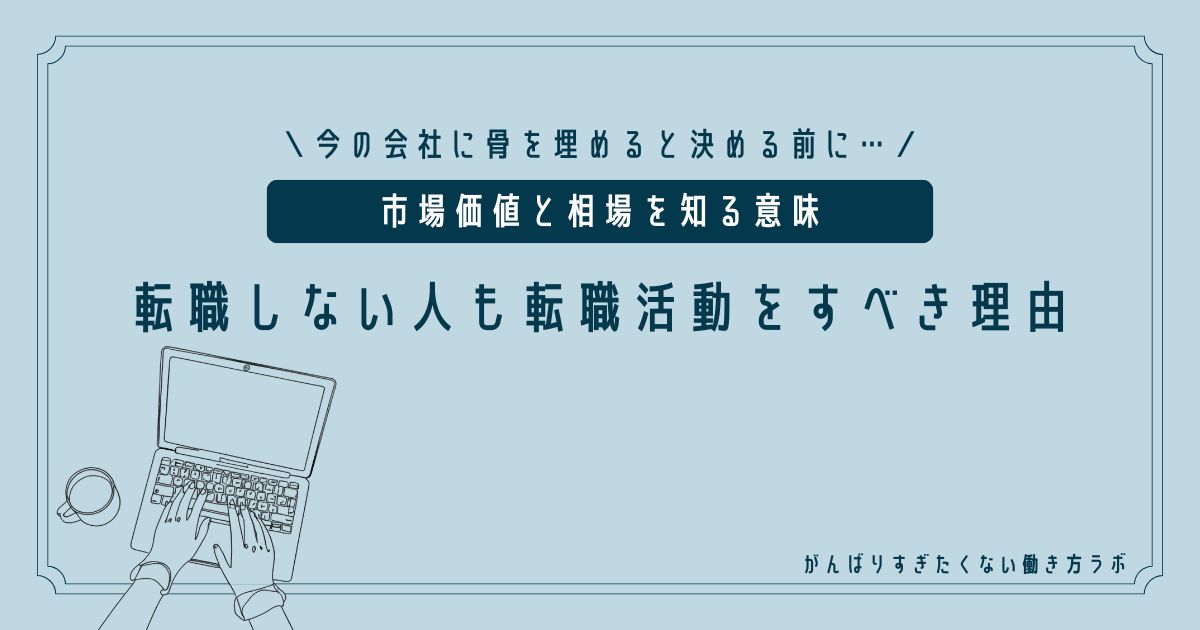
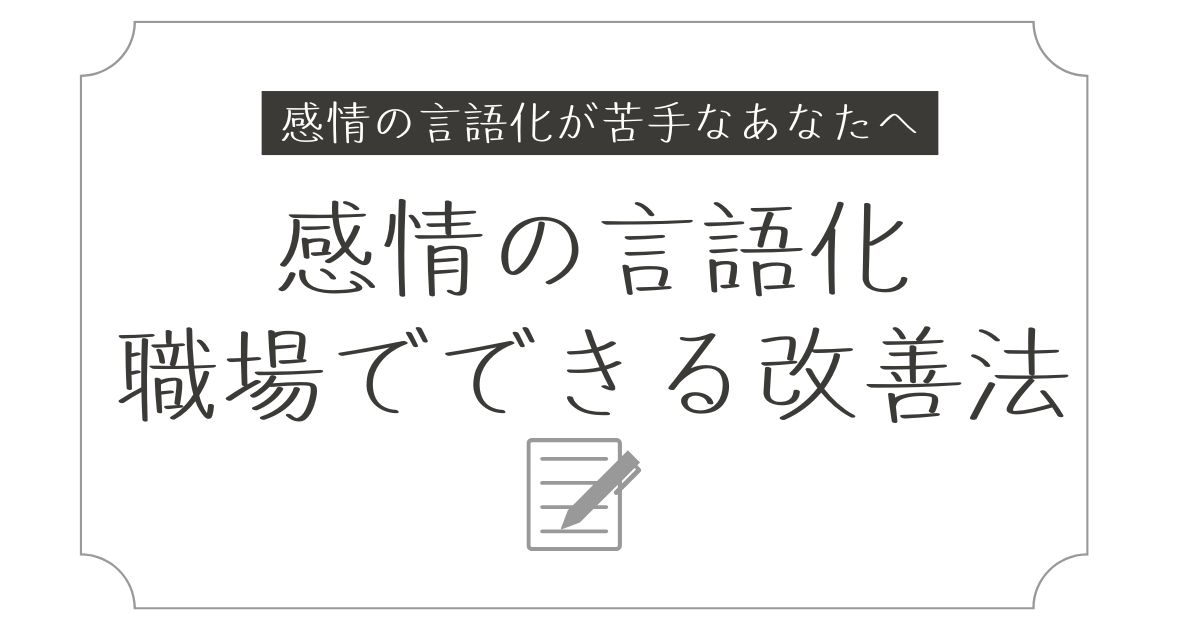
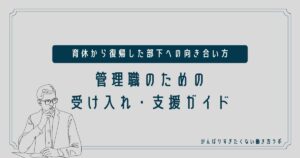
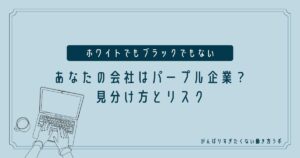
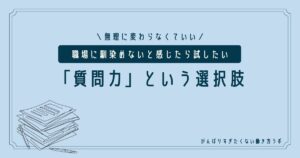
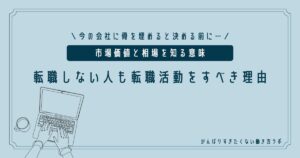
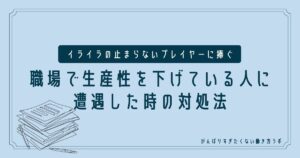
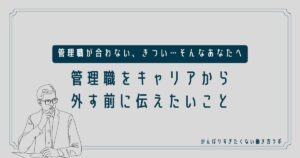
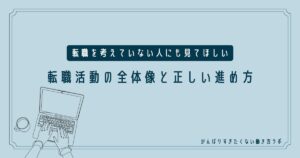
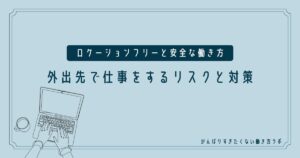
コメント